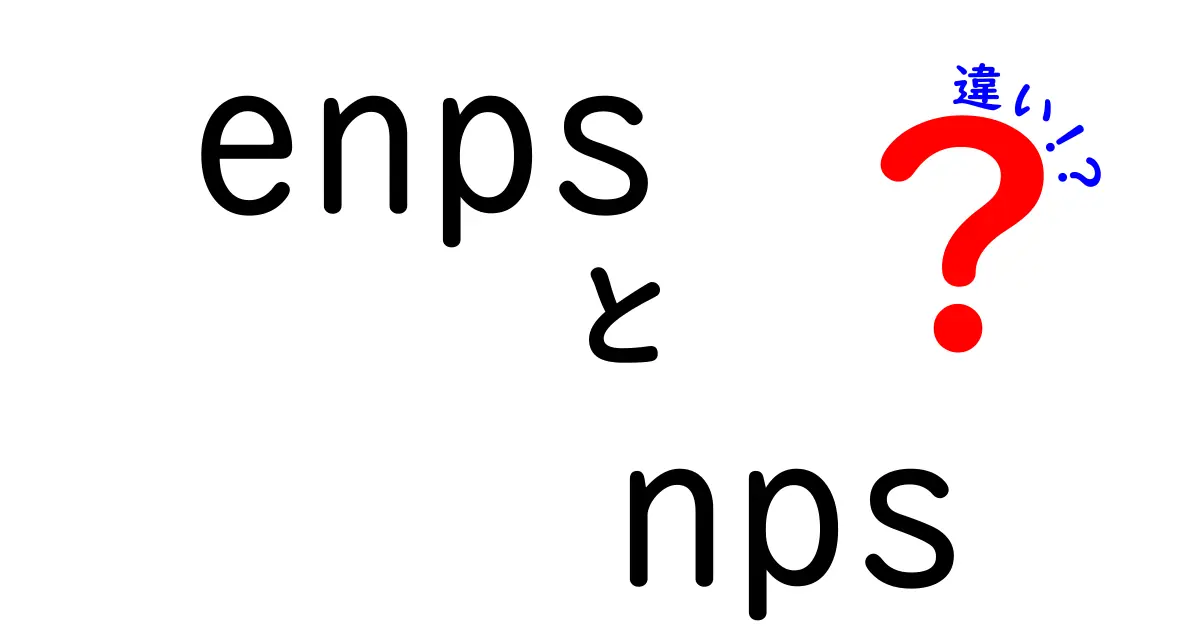

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
enpsとnpsの違いを正しく理解する
ENPSは従業員のエンゲージメントを測る指標であり、組織が従業員のモチベーションや職場への信頼感成長機会の認識、同僚との関係性といった内的な状態をどの程度把握できているかを示します。NPSは顧客の推奨意向を測る指標であり、製品やサービスを友人や同僚に勧めたいと思うかどうかを中心に問います。ここでの推奨は外部の視点を反映しており、ブランドの評判や市場の受容性を近い将来の売上につなぐ指標として働きます。つまりENPSは内部の声を、NPSは外部の声を映し出す鏡だと考えるのが分かりやすいというのが私の結論です。
次に計測の設計面を比べてみましょう。ENPSは従業員向けのアンケートで、カテゴリは人事系の質問が中心となります。匿名性と回答の自由度を両立させる工夫が必要です。NPSは顧客向けで、回答は1から10のスケールを用い、推奨者中立者批判者の3グループに分けてスコアを算出します。スコアの算出式はシンプルで、推奨者から批判者を引いた値を回答数で割り、100を掛ける方法が一般的です。
ただし、NPSが高くても顧客体験の改善が進んでいないケースもあり、逆に低いNPSでも特定のセグメントで長期的なファンが育つこともあるため、分解分析が欠かせません。
このような違いを踏まえると、指標の適切な使い分けと改善案の結びつき方が見えてきます。
エンゲージメントと推奨の視点を同時に活かすコツ
エンゲージメントと推奨の両方を同時に改善するにはどうすれば良いのでしょうか。私が実務で推奨するのは ENPSとNPS を別々に見るだけでなく、共通のダッシュボードで両方を並べて時系列で追跡する方法です。これにより従業員のエンゲージメントが上がると顧客の満足度も上がるのか あるいは逆に関係が薄いのかを見極めやすくなります。さらに回答の自由回答欄を活用して原因を特定する分析を加えると施策の優先度が見え、組織全体の改善サイクルが回りやすくなります。最後に実務では倫理的な配慮も忘れてはいけません。従業員情報を守るプライバシー対策 顧客データの取り扱い方針 透明性のある結果共有など 信頼を損ねない運用設計が鍵です。このような配慮を徹底することで ENPSとNPSの両方を健康に活かすことが可能になります。
今日はENPSについて友達と喫茶店で雑談するような雰囲気で深掘りします。ENPSは単なる点数ゲームではなく、職場の雰囲気や上司の声掛けの質、仲間の支え合いといった日常の体験を映す鏡のような指標です。ある日あなたがこのチームは頑張っているのに評価が薄い気がすると感じたとき、ENPSの数値はその感覚を数値化してくれます。すると具体的な改善案が出やすくなるのです。どうしても数字に引っ張られがちですが、自由回答を丁寧に読み解くこと、どの部署で課題が多いのかを属性別に見比べることが肝心です。





















