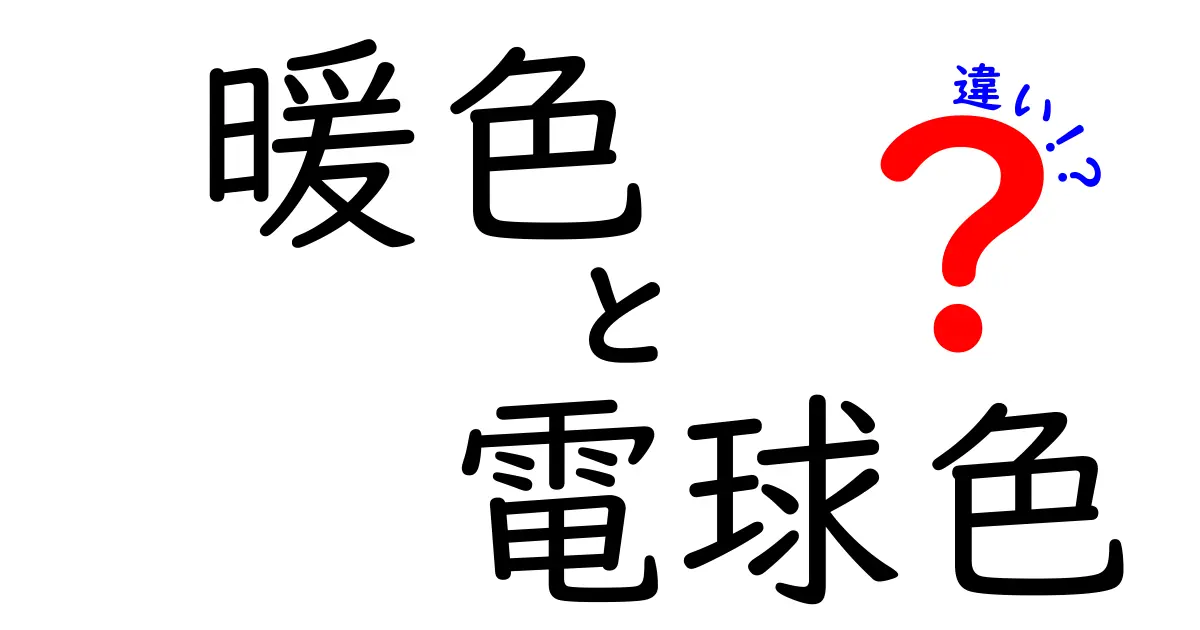

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
暖色と電球色の違いを徹底解説
ここでは「暖色」と「電球色」の意味を丁寧に分けて解説します。見た目の温かさを感じさせる色は、実は人の感覚や照明の性質で変わります。まず色の話を始めるときには“色温度”という考え方が基本です。色温度は Kelvin(K)で表され、数値が小さいほど赤味が強く、数値が大きいほど青味が強く見えます。色の印象はこの差で大きく変わります。実生活では、眠る前の部屋やリビング、勉強部屋など、場面に合わせて色温度を選ぶと心地よさが変わります。
写真や部屋の雰囲気を左右するのはこの温度の差です。
本記事では、まず「暖色」と「電球色」の意味を分け、次に具体的な違いを整理します。最後には実際の部屋づくりに役立つポイントをいくつか紹介します。読んでからすぐに使えるヒントが満載です。
なお、色温度はKで表すのが一般的で、電球色はおおむね2700K前後、昼白色は約4000K前後と覚えるとよいでしょう。数値の違いが、見え方だけでなく気分にも影響します。では、詳しく見ていきましょう。
電球色という言葉を友達と話しているとき、たとえば「この電球色、ノスタルジーを呼ぶね」とか「電球色って実は色温度が低いだけじゃなく、木の素材を温かく見せる力があるんだよ」という会話をよく耳にします。私たちは普段、写真や映像を見て色を判断しますが、実際には同じ暖色系でも光源の細かな違いが情緒に影響します。夜のリビングで電球色の光を使えば、家族の話し声が穏やかに聞こえ、落ち着いた雰囲気を作り出せます。一方、作業部屋では同じ暖色でも少し高めの色温度(たとえば3000K前後)を選ぶと、文字の読みやすさや視認性が向上し、日常の効率も上がることがあります。電球色は、単なる光の色味以上に、私たちの気分や行動パターンに影響を与える身近な“演出家”のような存在なのです。結局のところ、電球色は暖色の一種であり、木の温もりや家庭の懐かしさを引き出す力を持っていると覚えておくと、部屋作りの選択肢が広がります。





















