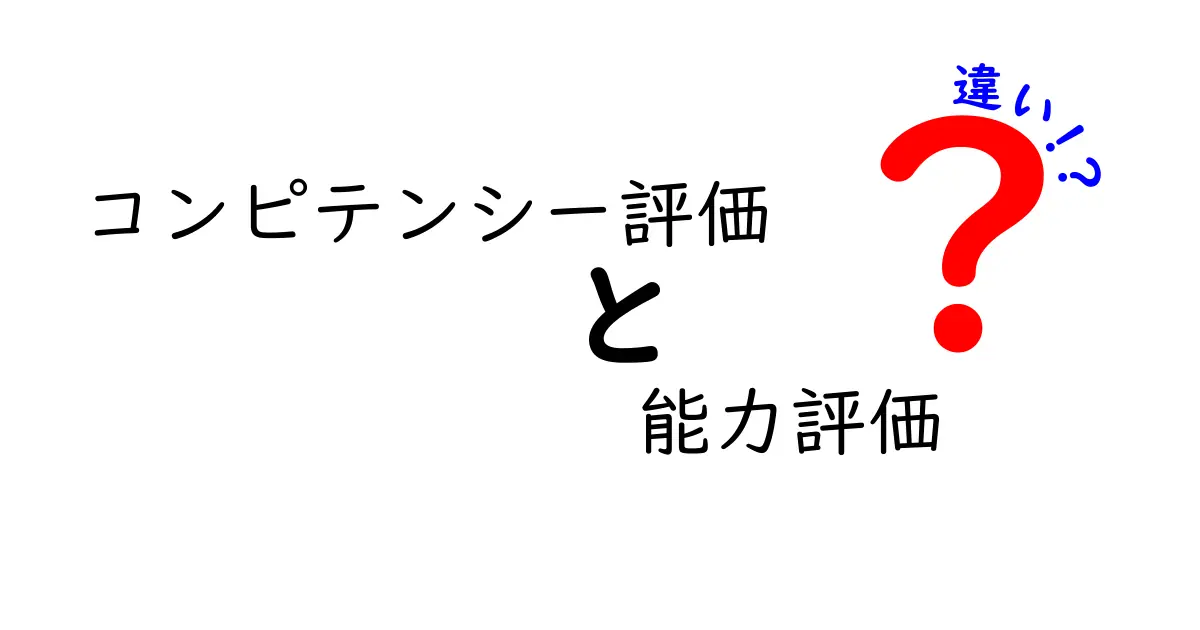

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コンピテンシー評価と能力評価の基本的な違いについて
まず、コンピテンシー評価と能力評価は、どちらも仕事や人の実力を測る方法ですが、その見方や目的が違います。
能力評価は、主に知識や技術、資格など、具体的に「何ができるか」を数値や結果で評価します。例えるなら、テストの点数や技能検定の合格のようなものです。
一方、コンピテンシー評価は、仕事で成果を出すための行動や考え方の特徴を見ます。つまり、「何をどうやって行っているか」を重視するのです。例えば、チームワークが得意だったり、問題を解決する力があるかどうかを評価します。
このように、能力評価は「できること」の量や質をチェックするのに対し、コンピテンシー評価は「行動の質」や「仕事における態度」を中心に見るのが違いです。
具体的な評価方法と使われる場面の違い
能力評価は主に試験や実技テスト、売上数字など、成果を数字や結果で示す方法が使われます。
会社では、資格試験の合格や販売実績、パソコンのスキルテストなどが代表的です。結果がはっきりと現れるため、新入社員のスキルチェックや技術力向上のために用いられます。
一方、コンピテンシー評価では面接やアンケート、行動観察が主な手段です。
例えば、上司が部下の仕事の進め方やコミュニケーションの取り方を詳しく観察し、評価するケースがあります。リーダーシップや問題解決力、計画性など目に見えにくい部分も評価されます。
そのため、管理職の選抜や昇進の判断、人材育成での指導方針決定に役立てられています。
コンピテンシー評価と能力評価のメリット・デメリット比較表
・短期間で結果が出る
・教育や研修の成果がわかりやすい
・一部分だけ評価しがちで全体像が見えにくい
・将来の成長可能性も評価できる
・行動の改善に繋がりやすい
・評価者の主観が入りやすい
・結果がすぐには出にくい
まとめ:うまく使い分けて成長と成果を目指そう
以上のように、能力評価は「何ができるか」を明確に示すために使い、コンピテンシー評価は「どうやって仕事をしているか」を把握し、行動面や将来性に注目します。
どちらも企業や組織、人材育成にはとても重要ですが、それぞれの特徴を理解して使い分けることで、より良い評価ができ、個人やチームの成長につながります。
例えば、新入社員にはまず能力評価を行い、技術や知識の基礎を確認し、その後コンピテンシー評価で仕事の進め方や態度などを指導すると効果的です。
このように両方の評価をバランスよく取り入れ、社員の強みを伸ばしていくことが大切です。
コンピテンシーって、ただのスキルや知識以上のものなんです。例えば、同じ仕事ができても、人によって『どうやって問題を解決するか』『周りとどう協力するか』は違いますよね。
コンピテンシー評価は、その『仕事を成功させる行動の特徴や考え方』を見ているんです。だから、結果だけじゃなくて、未来の成長やチームへの影響も評価できるんですよ。
この考え方を知ると、単に点数や数字だけじゃ人を判断できないことがよくわかりますね。
次の記事: キャリア面談と評価面談の違いとは?分かりやすく解説! »





















