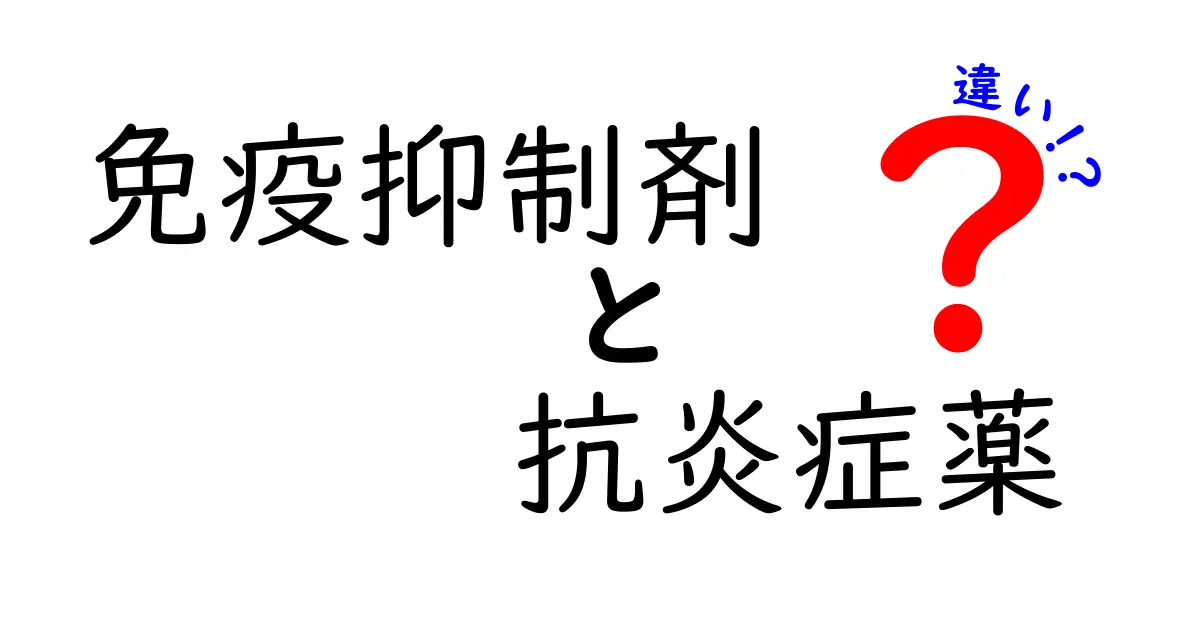

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
免疫抑制剤と抗炎症薬って何?基本を知ろう
病気やけがの治療でよく使われる〈免疫抑制剤〉と〈抗炎症薬〉ですが、名前が似ていてもその役割は全く違います。
免疫抑制剤は、体の免疫(病気やウイルス、細菌から体を守る力)を抑える薬です。免疫が強すぎて自分の体を攻撃する病気(自己免疫疾患)や、臓器移植後の拒絶反応を抑えるために使います。
一方、抗炎症薬は、体の炎症を抑える薬です。炎症は痛みや腫れ、熱を伴い、体の一部が傷ついていたり、感染しているときに起こります。抗炎症薬はその症状を和らげる役割を持っています。
このように、免疫抑制剤は体の免疫システムの働き自体を抑えるのに対し、抗炎症薬は炎症という症状を抑えるための薬だと覚えるとわかりやすいです。
免疫抑制剤と抗炎症薬の主な違いと使われる病気
免疫抑制剤と抗炎症薬はどちらも炎症に関係していますが、その使い方や対象となる病気には違いがあります。特徴 免疫抑制剤 抗炎症薬 主な役割 免疫反応を抑える
(過剰な免疫反応を抑制)炎症を軽減し、痛みや腫れを抑える 対象疾患 自己免疫疾患(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど)、臓器移植後の拒絶反応 けがや感染症に伴う炎症、関節痛、筋肉痛、花粉症など炎症が原因の症状 使い方 医師の指示で長期間使う場合が多い 症状があるときに短期間使うことが多い 主な副作用 感染症にかかりやすくなる、がんのリスク増加など免疫低下に関連するリスク 胃腸障害、肝臓への負担、長期使用で副作用も起こりやすい
このように、免疫抑制剤は免疫の根本的な働きを制御するため、副作用も強く注意が必要なのに対し、抗炎症薬は症状の緩和を目的に使われます。
実際の治療では、患者さんの症状や病気の種類によって、使い分けられます。
どんな場面でどちらの薬を使うの?実際の使用例と注意点
たとえば、関節リウマチの治療では、関節の炎症を抑えるために抗炎症薬が使われますが、それだけで十分でない場合には免疫抑制剤も併用されることがあります。
また、臓器移植を受けた患者さんは、移植した臓器が体にとって異物と認識されて攻撃されるのを防ぐために免疫抑制剤を長期間服用します。
一方、風邪や虫刺されなどの炎症に伴う痛みや腫れを抑えるには、主に抗炎症薬が使われることが多いです。
しかし、免疫抑制剤は免疫力が下がるため、感染症にかかりやすくなったり副作用が強く出ることがあるので、医師の管理がとても重要です。抗炎症薬も長期間使うと胃が荒れたり、肝臓の負担が心配されるため、用法と用量を守ることが大切です。
どちらの薬も自己判断で服用・中止せず、専門家の指示を必ず守ることが重要です。
免疫抑制剤という言葉を聞くと、「体の免疫を抑える=悪いこと?」と思いがちですが、実はそうではありません。免疫抑制剤は、自己免疫疾患のように体の免疫が過剰に働いて自分自身を攻撃してしまうときに使います。つまり、免疫が強すぎて“暴走”している状態を落ち着かせる役割を担っているのです。これはまるで、火事が燃え広がりすぎないように水をかけて火を抑える消防士のような役割と言えます。だから免疫抑制剤は、必要なときに体の免疫をコントロールするために使われている大事な薬なんです。
前の記事: « 成長痛と関節痛の違いは?子どもの痛みの正体を徹底解説!
次の記事: 方位と方角の違いとは?中学生でもわかる簡単解説! »





















