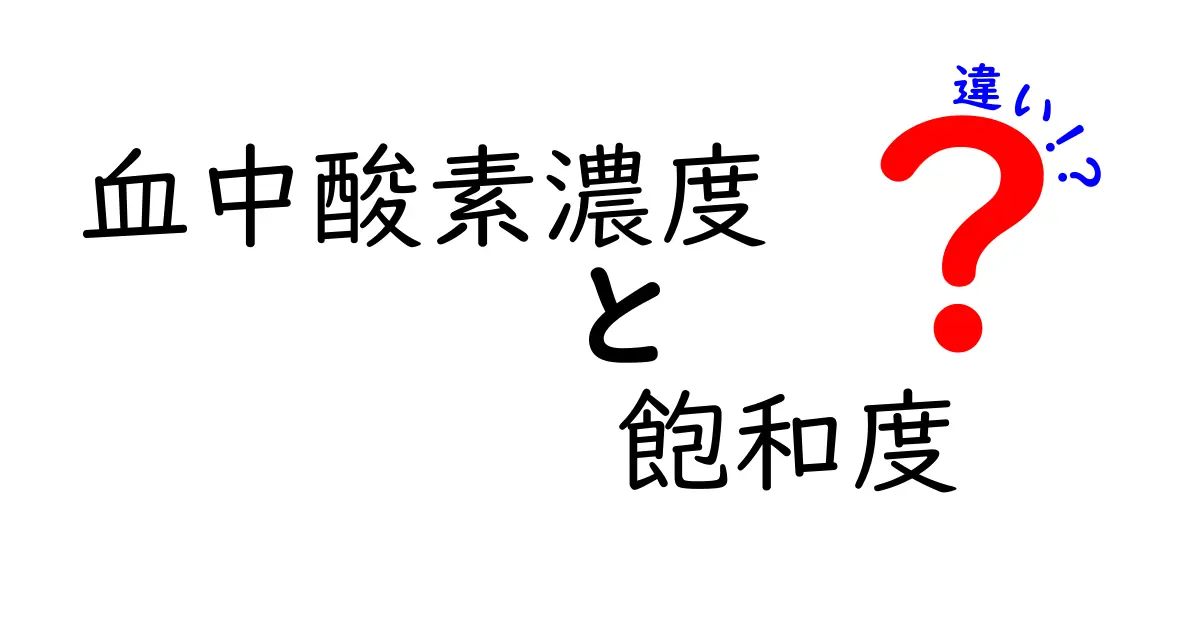

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
血中酸素濃度とは何か?
血中酸素濃度とは、血液の中にどれだけの酸素が溶けているかを示す指標です。酸素は私たちの体を動かすために必要なエネルギーを作る際に使われます。血中酸素濃度は"部分圧"とも呼ばれ、単位はmmHg(ミリメートル水銀柱)で表されます。この値は血液中の酸素分子がどのくらい存在しているかを直接示しています。
例えば、肺から取り入れた酸素が血液に溶け込み、その一部は赤血球にあるヘモグロビンと結びつきます。この溶けている酸素の量が血中酸素濃度です。血中酸素濃度は体の組織に酸素が届いているかを判断するための大切な値です。
血中酸素濃度は、血液検査などで調べられますが、日常的にはあまり簡単にわかるものではありません。その代わりに、「酸素飽和度」という簡単に測れる値を使うことが多いのです。
血中酸素飽和度とは何か?
血中酸素飽和度は、血液中のヘモグロビンがどのくらい酸素と結びついているかを表す割合です。一般的にパーセント(%)で表示され、「SpO2(エスピーオーツー)」という名前でパルスオキシメーターという機械を使って簡単に測れます。
例えば、酸素飽和度が98%なら、赤血球のヘモグロビンのほとんどが酸素と結びついているという意味です。逆に低いときは、酸素が十分に運ばれていないことを示し、体調不良や呼吸の問題が考えられます。
血中酸素飽和度は体の酸素運搬能力を簡単にチェックできるため、睡眠時無呼吸症候群や肺疾患などの診断や日常の健康管理に使われます。
血中酸素濃度と飽和度の違いまとめ
血中酸素濃度は血液中の酸素そのものの量(血液中に溶けている酸素の量)を指し、単位はmmHgで表されます。
血中酸素飽和度は酸素を運ぶヘモグロビンがどれだけ酸素と結びついているかを%で表す割合です。
つまり、血中酸素濃度は酸素の「量」、飽和度は赤血球中のヘモグロビンの「酸素の結びつき具合」を示しています。
以下にわかりやすい表でまとめます。
この違いを押さえておくと、体の酸素状態を正しく理解できます。
ぜひ日常の健康管理に役立ててください。
血中酸素飽和度(SpO2)はよく耳にしますが、実はパルスオキシメーターが動作する仕組みが面白いんです。赤血球のヘモグロビンに酸素がついているところとついていないところでは、光の吸収の仕方が違います。この性質を利用して、指先に光を当てるだけで酸素飽和度を測っているんですよ。中学生でも簡単に使えるので、自分の体調チェックにとても便利です。





















