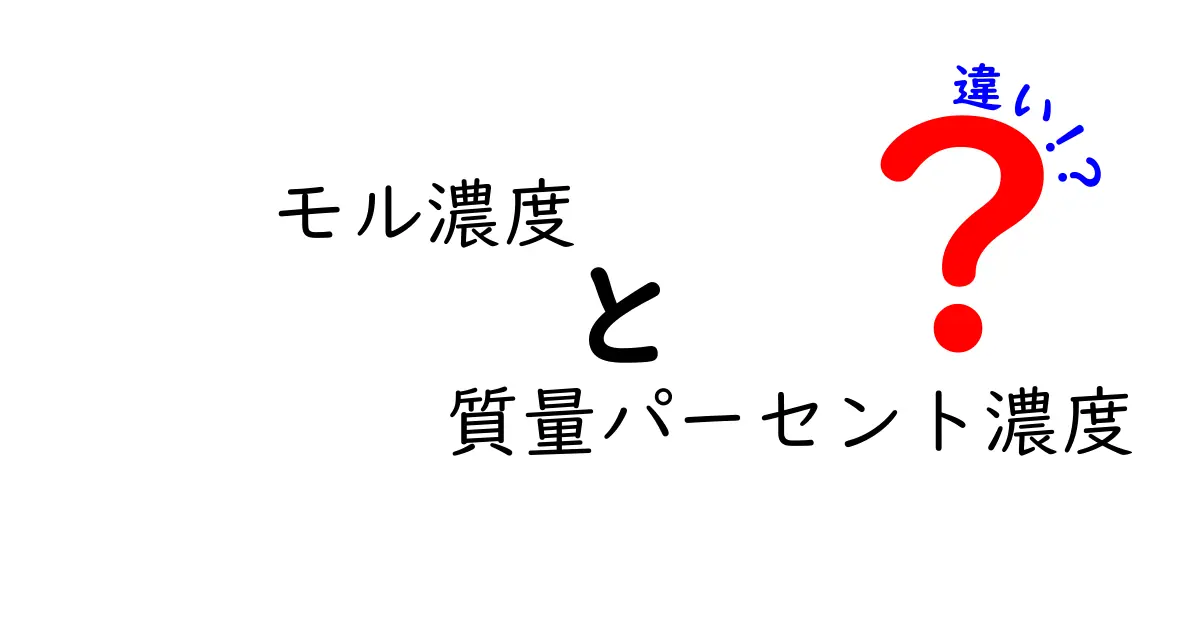

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
モル濃度と質量パーセント濃度の違いを徹底解説
まず、モル濃度と質量パーセント濃度は、どちらも「濃度」という水溶液の性質を表す言葉ですが、表す意味が違います。モル濃度は溶質のモル数を溶液の体積で割った値で、M = n / V、単位は mol/L です。質量パーセント濃度は溶質の質量が全体の質量に占める割合を%で表すもので、w/w% は (溶質の質量 / 溶液の総質量) × 100 という式で決まります。これらは同じ溶液を別の指標で表しているだけなので、用途に応じて使い分けるのが大切です。
例えば、薬品の濃度を正確に測って実験を再現する場合はモル濃度が役立ちます。一方で、食塩水のような液体の濃さを家庭で直感的に把握したいときは質量パーセント濃度が分かりやすいです。
密度の影響を受ける点も要点です。モル濃度は体積を、質量パーセント濃度は質量を基準にしているため、同じ溶液でも密度が変われば値が変わることがあります。ここを理解しておくと、実験ノートに正確な数値を書き残すのが楽になります。
次に、式と単位の違いを整理します。
モル濃度の公式は M = n / V で、n は溶質のモル数、V は溶液の体積です。単位は mol/L。質量パーセント濃度の公式は w/w% = (m_solute / m_solution) × 100 で、m_solute は溶質の質量、m_solution は溶液の総質量です。単位は % です。これらの式は、中学校の理科の授業で何度も出てくる基本形なので、覚えておくと良いです。
この先の実例で、これらの違いと使い分けが自然に見えてくるはずです。
モル濃度の基本とよくある誤解
モル濃度は「溶けている粒の数を水の量で割る」考え方に近いですが、ここでの注意点は「最終的にできあがった溶液の体積」を使うことです。溶質を加えると体積がわずかに増減します。実験ノートでは最終体積を使うのが原則です。たとえば NaCl を1モル、1リットルの溶液にするには、約58.44 g のNaClを使い、最終的な体積を1 LにしてM=1.0 mol/Lと表します。現実には密度の変化や溶解の過程で体積が変わることがあり、その場合は密度を使って体積を見積もる必要があります。これらの注意を覚えておくと、単位の切替えや理解が格段に楽になります。
さらに、濃度を混在させるときには、溶液の体積がどのように変化するかを事前に計算しておくと良いです。
日常の実験では、体積が1 Lに近いことを前提にすることが多いですが、厳密さが求められる場合には体積と密度の関係を数式で扱い、値を補正します。
日常の実践に役立つ比較と計算のコツ
ここでは具体的な例を用いて、モル濃度と質量パーセント濃度の違いを実感するコツを紹介します。
例1:水1 L中にNaClを1モル溶かすと、概算で溶液の質量は約1000 g付近になります。この場合、質量パーセント濃度は w/w% ≈ (58.44 / 1058.44) × 100 ≈ 5.5%程度となります。密度の影響を無視した近似ですが、日常の理解には十分です。
例2:質量パーセント濃度が5%の溶液を作るには、溶質の質量と溶液の総質量の比を計算します。例えば100 gの溶液を作るなら、溶質は5 g、溶媒は95 gです。モル濃度を求めるには、溶質のモル数を求め、溶液の体積を見積もる必要があります。これを実際の実験用のデータと照合すると、理解が深まります。
このように、モル濃度と質量パーセント濃度は、それぞれの情報から別々の答えを出す指標です。目的が「正確な比の説明」ならモル濃度、日常的な感覚の比較なら質量パーセント濃度を使うと良いでしょう。
表を用いて整理するとさらに分かりやすいです。
この表は記事の要点を一目で確認できるようにしたものです。
最後に覚えておきたいのは、濃度を「何を基準にするか」で決めるということです。体積を基準にするならモル濃度、質量を基準にするなら質量パーセント濃度です。
実験の設計図を作るときには、初めにどの指標を使うかを決めて、前提条件(密度、体積など)をそろえると、計算がスムーズになります。
放課後の理科室で友だちと雑談していたとき、モル濃度についてこんな会話をしました。『モル濃度って、塩を何グラム入れると何モルになるの?それを水の体積で割るとどうなるの?』その質問に答えるには、まず溶液の体積と質量がどうつながるかを知ることが大事だとわかりました。モル濃度は簡単に言えば『溶かした物質の粒を数え、それを液体の容量で割る』のが基本です。例えば、NaCl の1モルはNa原子と Cl原子の合計で約58.44 gです。これを1リットルの水に溶かすと、溶液全体の体積が1リットルになると仮定した場合、モル濃度は1.0 Mになります。もちろん実際には溶質と溶媒を混ぜると体積が少し変わることがあるので、厳密には現実の密度を使って計算します。こんな風に、モル濃度は“量の話”と“体積の話”を結びつける橋渡し役をしてくれます。





















