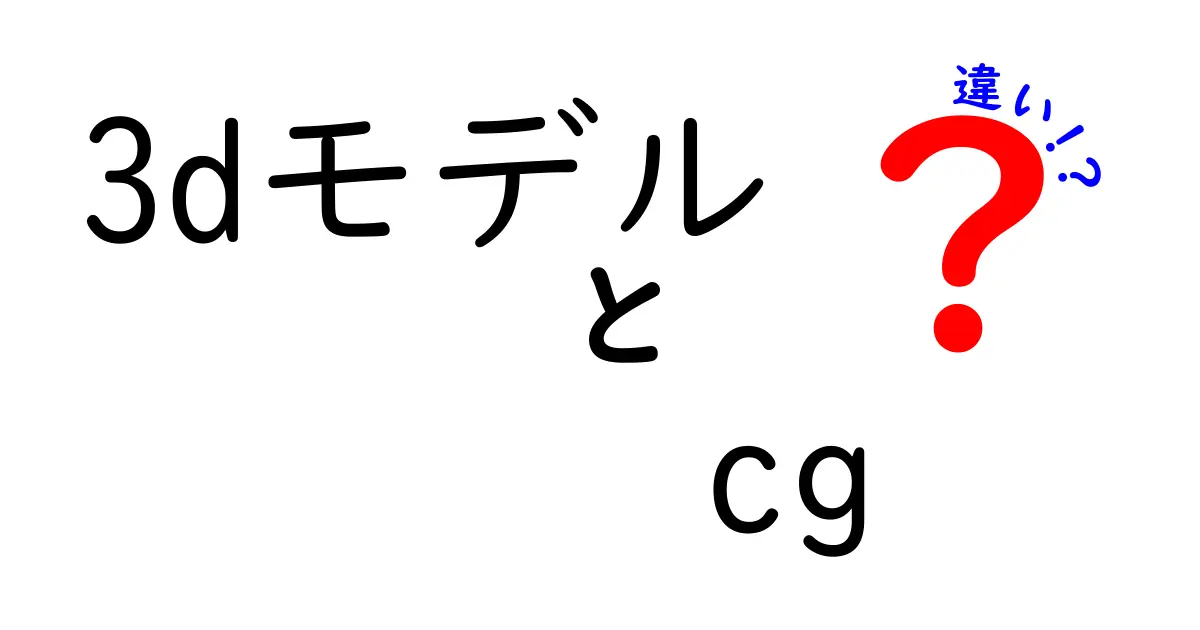

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3DモデルとCGの基本的な違いとは?
こんにちは!3DモデルとCG(コンピュータグラフィックス)は、どちらもデジタルで映像や画像を作るときによく使われる言葉です。でも、このふたつは実は意味が少し違います。
まず、3Dモデルとは、パソコンの中に作られた「立体の形そのもの」のことを指します。例えば、映画の中に出てくる恐竜やロボット、それを形作るのが3Dモデルです。これができて初めて動かしたり色をつけたりすることができます。
一方、CGは「コンピュータグラフィックス」の略で、コンピューターを使って作成されるすべての画像や映像を指します。2Dの絵も含まれるし、3Dモデルを使った映像もCGです。つまり、3DモデルはCGを作るための素材の一つなんですね。
このように、3DモデルはCGの中の一部分で、CGはもっと広い意味を持つ言葉です。3Dモデルは立体の形、そのままであり、CGは完成された画像や映像全体を指すのが大きな違いです。
3Dモデルの特徴と使われ方
3Dモデルはポリゴンと呼ばれる小さな面がたくさん集まって形を作っています。これを設計図のように作り上げることで、立体の形が完成します。
例えば、3Dゲームで動くキャラクターや映画の中の実際に動いている人物のCGなどは、みなさん3Dモデルから作られています。
3Dモデルの良いところは、自由に形を変えたり、視点を動かしたりできることです。例えば恐竜の3Dモデルを作ったら、正面からでも横からでも、さらにはアップにしても細かく見られます。
また、この3Dモデルに色や質感、光の当たり方などを設定すると、よりリアルな映像や画像を作れます。
たとえば、布の質感や金属のツヤも3Dモデルに対してコンピューターが計算して表現しているんです。この工程はモデリング、テクスチャリング、レンダリングと呼ばれています。
CGの特徴と活用範囲
一方CGはコンピューターを使って作成したすべての映像や画像を指し、多様な分野で使われています。ゲーム画面、アニメ、映画、広告、建築の設計図など、その範囲はとても広いです。
CGには2D(平面の絵)のものもあれば、3Dモデルを使った立体的な映像もあります。
たとえばジブリのアニメもCG技術を使っていますし、最新のハリウッド映画はほとんどCG映像でできています。これは、リアルな映像を作るのが難しいシーンをCGで作り出すためです。
CGは単なる画像や映像だけではなく、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)でも使われている技術です。このように、CGは非常に幅広い場面で活用されているのが特徴です。
3DモデルとCGの違いをわかりやすくまとめる表
| ポイント | 3Dモデル | CG(コンピュータグラフィックス) |
|---|---|---|
| 意味 | 立体的な形のデジタルデータ | コンピューターで作成した全ての画像や映像 |
| 形態 | ポリゴンで構成される立体オブジェクト | 2Dや3Dなど多様 |
| 使われ方 | 映像やゲームの素材 | 完成した映像や画像、その技術全般 |
| 例 | ゲームのキャラクターの形 | 映画のVFX、アニメ、広告映像 |
| 特徴 | 形を自由に動かせる | 見える映像全体を指す |
まとめ:3DモデルとCGを理解して映像の世界を楽しもう!
3DモデルとCGは似ているようですが、3DモデルはCGを作る素材の一部、CGはそれらを使って作られた映像や画像の全体と考えることが一番わかりやすいです。
映像やゲームをもっと楽しみたいなら、この違いを知ると制作過程にも興味がわくかもしれません。
これからも新しい技術でよりリアルな世界がパソコンの中に作られていきます。3DモデルとCGの違いに注目しながら、映像の世界を楽しく学んでいきましょう!
3Dモデルの話をするときに面白いのが、「ポリゴン」という言葉です。これは3Dモデルを作るときの「小さな面」のことで、まるで積み木のようにたくさん集まって形を作っています。でも、実はこのポリゴンの数が多ければ多いほど、細かくてリアルな形が作れるんです。ゲームや映画の進化は、このポリゴンの使い方と技術の発展が大きなカギなんですよ。だから、昔のゲームのキャラクターがカクカクして見えたのは、ポリゴンの数が少なかったからなんですね。
次の記事: ウォークスルーと再実施の違いとは?わかりやすく解説! »





















