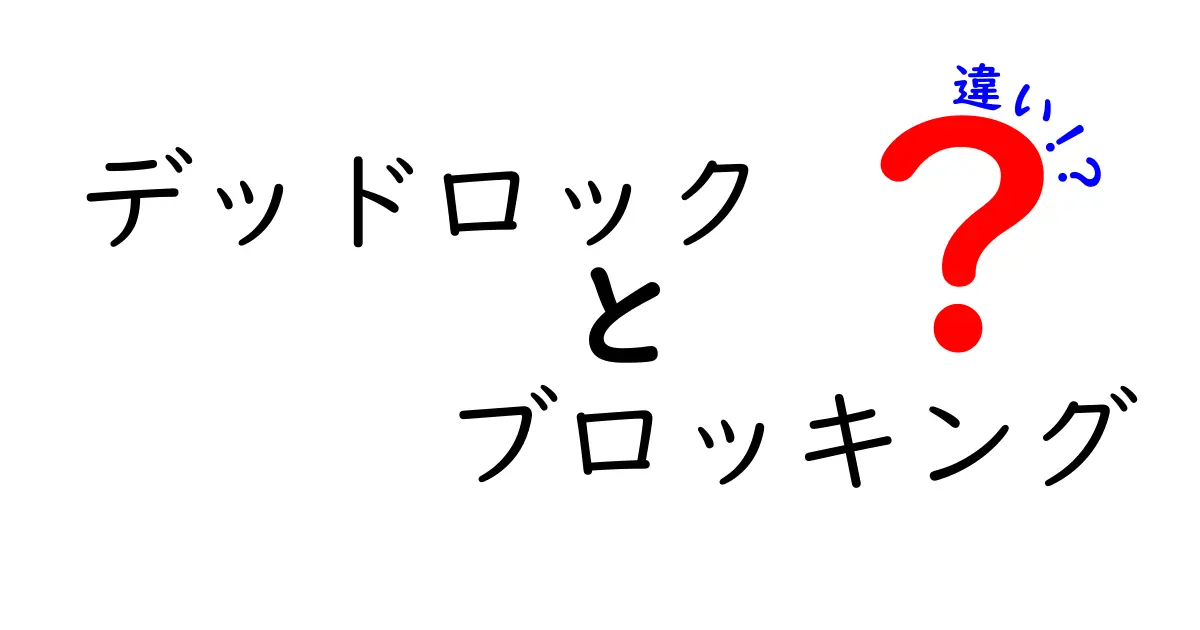

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
デッドロックとは何かを丁寧に理解する
デッドロックとは、複数の作業が同時に動いている場面で、 お互いが相手の持つ資源を待ち続ける状態 になり、結果として誰も前に進めなくなる現象を指します。日常の例を使うと、二人の生徒が同じ本を同時に取りに来て、Aが自分の本を開くにはBの本を閉じてもらう必要があり、同時にBもAの本を開けるのを待っている状態と似ています。こうした循環待ちが成立すると、処理全体が停止します。現実のコンピュータでは、データベースのロックやファイルの排他制御、CPU時間の割り当てなどを巡る複数のタスクが 互いの資源を譲り合えず、進行を止めてしまうことがあります。デッドロックが起こる条件には主に四つの要素が挙げられます。第一に 相互排他、第二に 資源の保持と待機、第三に 循環待ち、第四に 他の条件の同時発生 です。これらが重なるとデッドロックの可能性が高まります。デッドロックを完全に防ぐのは難しいこともありますが、設計次第で発生を抑え、発生しても早期検出と回復策を用意することが現場の基本です。
デッドロックを理解するためには、循環待ちがどんな状況で生まれるのかをイメージするのが近道です。資源を取得する順序を工夫する、保有時間を短くする、待ち状態の発生を制御するための信号やルールを設ける、といった具体的な対策を学ぶと、対処方法が見えてきます。デッドロックは遅延の原因にもなりますが、放置すればシステムの信頼性そのものを脅かす重大な問題になり得ます。まとめとして、デッドロックは「互いに資源を待ち続ける循環待ち状態が原因で全体が止まる現象」であり、発生条件を抑える設計と、発生時の検出・回復の仕組みづくりが鍵だという点を覚えておきましょう。
ブロッキングとは何かの基礎と発生の仕組み
ブロッキングはデッドロックとは別の現象で、資源が解放されるのを待つ状態を指します。待っている間に処理が止まるため、全体の応答性が落ちることがありますが、デッドロックのように必ず進まないわけではありません。例えばファイルの書き込みを行う処理が、ディスクの待ちや外部サービスの応答待ちで 一時的に進行を止めることがあります。ブロックは通常、一定時間の経過や資源の解放によって自然に解消しますが、待ち時間が長いとユーザー体験に影響します。実務ではタイムアウトを設けて待機を打ち切る、非同期処理を導入して待ち時間を有効活用する、待機をキューで管理して優先順位をつけるといった対策が有効です。
ブロックの影響を抑えるコツは、CPUを効率よく使い、待ち時間を最小限にする設計を心がけることです。I/O待ちやネットワークの応答待ちなどは日常的に発生しますが、設計次第でその影響を大きく削減できます。
デッドロックとブロッキングの違いと実務での対処法
デッドロックとブロッキングの違いを把握することは、システムの安定性を高める最初の一歩です。デッドロックは循環待ちによる全体停止の危機であり、発生すると自力で解決するのが難しい場合が多く、外部の介入や回復手段を用意する必要があります。一方、ブロッキングは待機自体の性質であり、適切な設計とタイムアウト、非同期処理の導入で影響を抑えられることが多いです。対処法としては、デッドロック予防の基本として資源取得の順序を統一する、ロックの保持時間を短くする、タイムアウトを設定して待機を打ち切る、デッドロック検出と回復の仕組みを組み込む、などを組み合わせます。ブロッキング対策としては、待機そのものを短くする工夫、非同期化、待機をキューで管理する設計、過剰なロックを避ける設計が有効です。以下に両者の特徴を分かりやすく比較する表を示します。 ある日のプログラム部活の雑談。デッドロックという言葉がホワイトボードに残っていた。友だちのA君とB君が、それぞれ自分の持ち場の鍵を握っていて、相手が自分の鍵を返すのを待っている。私はひと呼吸おいて、まずは現状の資源の数と取得順序を確認することを提案しました。小さなプログラムなら、デッドロックの発生パターンを再現するテストケースを作ってみるのも有効です。結局、デッドロックは人ごとの判断の積み重ねが原因となることが多く、設計の段階で「誰が何をいつ取るのか」を決めることが肝心だと説明しました。ブロッキングの話題に移ると、待機時間を短くする工夫が効くと伝え、非同期処理の良さや、待機をキューで管理する考え方を雑談として共有しました。そんな会話の中で、デッドロックとブロッキングは別物だという理解が深まり、日常のプログラミングにも活かせるヒントが生まれた気がしました。項目 デッドロック ブロッキング 性質 相互待機による全体停止 資源待ちによる一時的停止 発生条件 循環待ちを含む複数要因が揃う 資源待ちのみで発生することがある 対処法の例 資源取得の順序統一、タイムアウト、検出と回復 タイムアウト、非同期、待機列の最適化
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















