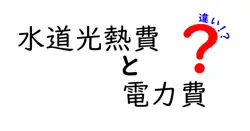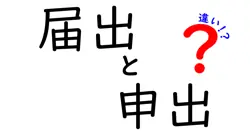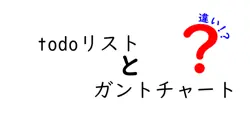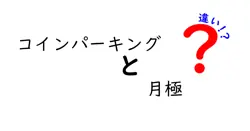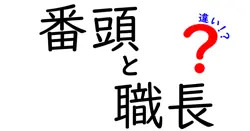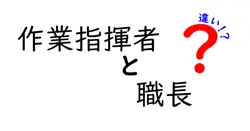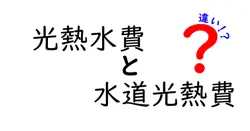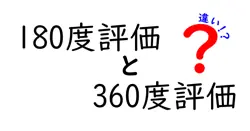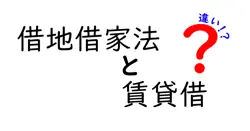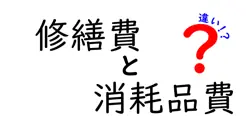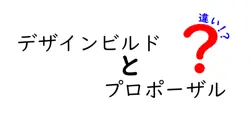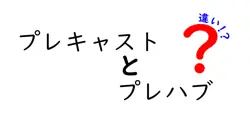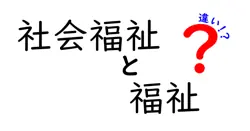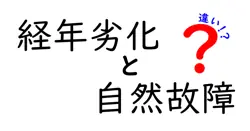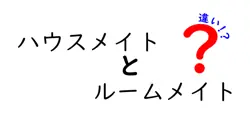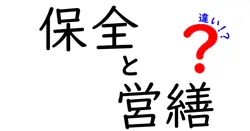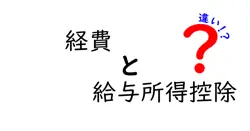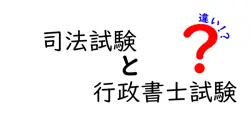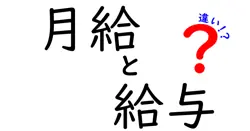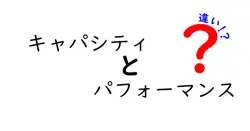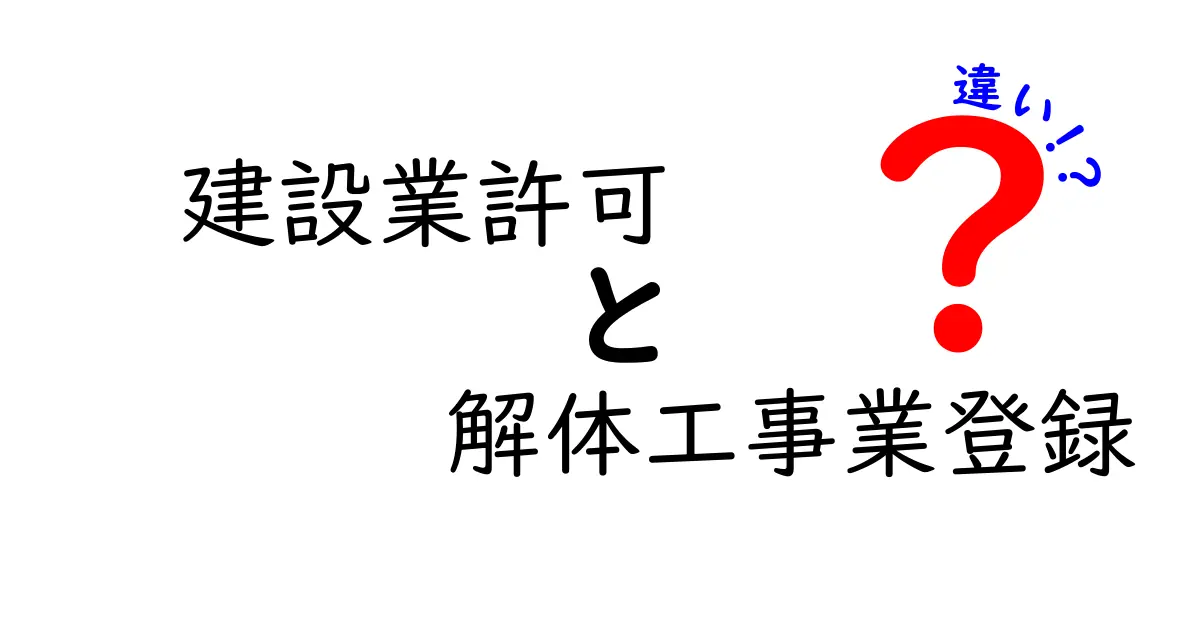
建設業許可と解体工事業登録の基本的な違いとは?
建設現場でよく耳にする建設業許可と解体工事業登録は、似ているようで実は異なる制度です。
まず、建設業許可は建物の新築や改修など幅広い建設工事を行う事業者が必要とする許可です。一方、解体工事業登録は特に建物の解体に特化した作業を行う事業者向けの登録制度となっています。
この2つは法律の目的や適用範囲も異なり、取得要件や申請方法、管理する行政機関も違います。
これらの違いをしっかり理解することで、建設や解体の仕事を始める際にどちらの手続きを進めるべきかが分かります。
次に、具体的な違いとそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
建設業許可とは?その役割と申請要件
建設業許可は建設工事全般を行うための法的な許可です。国土交通省や各都道府県知事が管轄しています。
例えば、ビルの新築工事やリフォーム、道路工事など、さまざまな建設作業を請け負う事業者はこの許可が必要です。
取得のためには経験者の配置や経営者の資質、財務状況の安定性など詳しい審査に合格しなければなりません。
また、2種類あり、5000万円以上の大きな工事も請け負う場合は特定建設業許可、そうでなければ一般建設業許可となります。
これにより、顧客は優良な施工会社を選びやすく、安全性と信頼性の確保につながっています。
解体工事業登録とは?手続きと求められる基準
一方、解体工事業登録は解体工事を専門に行う事業者向けの自治体登録制度です。2015年の建設リサイクル法の施行により義務化されました。
主に登録は都道府県単位で管理され、解体工事を行う際は各自治体での登録が必要です。
申請には事務所や作業員の配置、安全管理の体制、近隣への配慮など一定の基準を満たしていることを示す必要があります。
解体工事は騒音や粉じん、廃材処理など環境面の配慮が重要であり、この登録制度を通じて安全かつ適正に作業を実施することが期待されています。
なお、解体工事業登録は建設業許可とは別管理なので、解体専門業者が建設業許可を持つ必要はありません。
建設業許可と解体工事業登録の違いをわかりやすく比較!
以下の表で2つの制度の違いを整理してみましょう。
| 項目 | 建設業許可 | 解体工事業登録 |
|---|---|---|
| 対象工事 | 建設全般(新築、改修など) | 主に解体工事のみ |
| 管轄 | 国土交通省・都道府県知事 | 都道府県知事(建設リサイクル法) |
| 必要となる法令 | 建設業法 | 建設リサイクル法 |
| 許可・登録の種類 | 一般・特定建設業許可 | 単一の登録 |
| 申請要件 | 経験者の配置、財務基盤、経営管理能力 | 安全管理体制、作業員の配置、環境配慮 |
| 届出など | 許可証の更新義務あり | 登録証の更新義務あり |
このように、建設業許可は幅広い建設工事をカバーし、専門知識や経営面も問われる厳しい許可制度です。
一方で、解体工事業登録は解体作業に特化し、環境や安全面の管理を重視した登録という違いがあります。
どちらの制度も工事の質と安全を守り、市民の暮らしや環境を保護する重要な役割を担っています。
まとめ:どちらの許可や登録が必要かは工事内容で決まる
今回は「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いについて詳しく解説しました。
新築や修繕、幅広い建築工事をメインに行う場合は建設業許可が必要です。
解体作業を主に行う事業者は解体工事業登録を取得することが求められています。
どちらも工事の安全・適正な運営や近隣環境への配慮につながっており、建設業者や解体業者にとって重要な許認可です。
これから建設や解体の仕事を考えている方は、まず自分の行う工事の種類をはっきりさせ、該当する許可や登録を取得するための手続きを進めましょう。
正しい制度の理解が安全で信頼される企業経営の第一歩となります。
「解体工事業登録」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、実は解体工事の安全管理や環境保護のためにできた大事な制度です。
たとえば、重機の使い方や廃材の処理方法には法律の決まりがありますが、解体工事業登録を持っている会社はこれらをきちんと守っている証です。
こんな制度があるから、解体工事でも近所の人たちが安心して過ごせるんですね。
少しの違いですが、登録があるかどうかで工事の安全性や信頼性が大きく変わってくる面白いポイントですよ。
前の記事: « 建築の基本!構造計算と構造設計の違いをわかりやすく解説
次の記事: 一般建設業と特定建設作業の違いとは?わかりやすく解説! »