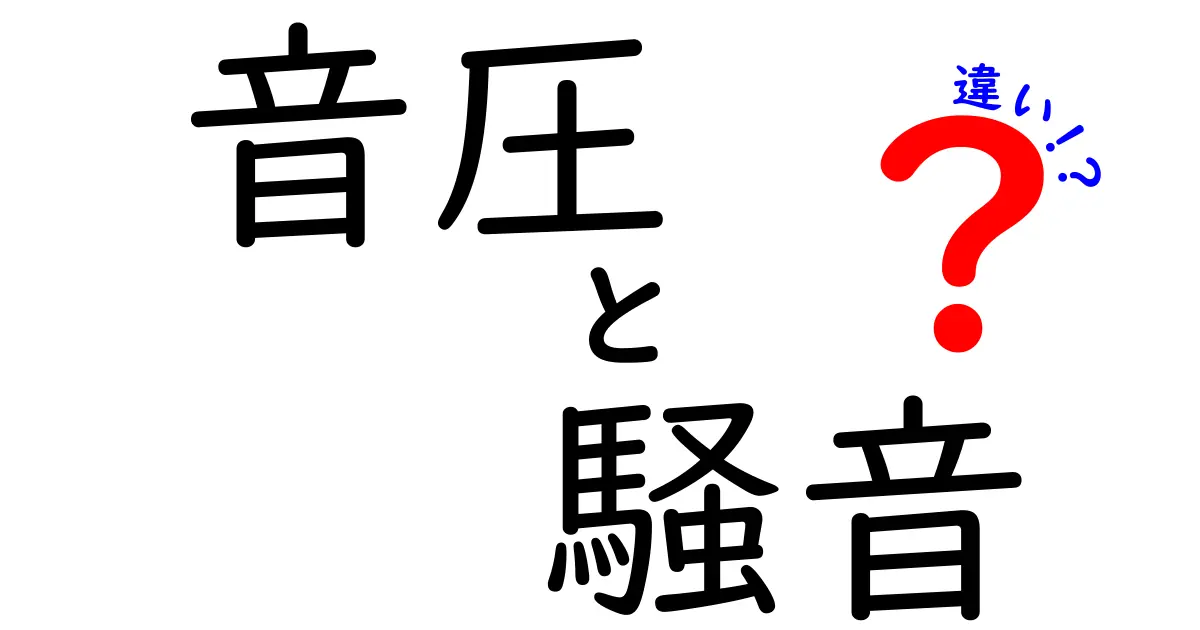

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
音圧と騒音の違いを知るための徹底ガイド
音は目に見えない波のように私たちの耳に届きます。普段は気づかなくても、音には強さを表す“音圧”という値があります。音圧は空気の圧力が波の形でアップダウンする大きさを示すもので、単位はパスカル(Pa)やデシベルという形で表されます。ここで大切なのは、音圧は物理的な現象そのものであり、私たちが感じる騒がしさは別の感覚で決まることです。たとえば同じ音でも近くで聞くと音圧が大きくなり、遠くにあると小さくなります。人が「うるさい」と感じるかどうかは、音の物理的強さだけでなく、耳の感じ方や集中している状態にも影響されます。
騒音という言葉は、人が不快に感じる音の総称です。音圧が高いからといって必ずしも全員が同じ程度に不快に感じるわけではありませんが、長時間の高い音圧は耳を傷つけることがあります。日常では通学路の車の音、学校の教室の空調、家の周りの工事音などが典型的な騒音の例です。音圧を測るときには、機械で数値を出します。私たちが耳で感じる騒音の強さを、科学的に扱うときには dB SPL という単位を使い、dBは感覚の強さを対数的に表す性質を持っています。
この違いを理解すると、日常生活での選択が変わります。例えば音楽を聴くときの音量の目安や、睡眠を妨げないための部屋作り、騒音の少ない時間帯を選ぶ工夫など、実用的な判断ができるようになります。
音圧とは何か
音圧は空気の圧力の波が私たちの耳に触れるときに生まれる、空気の押し引きの強さを表す値です。これを数値で表すと Pa または dB SPL になります。音圧の基本は p という圧力の振幅です。基準となる参照値 p0 は 20 マイクロパスカルで、これを p に対して 20 log10(p/p0) で dB SPL が決まります。身の回りの例を挙げると、静かな部屋は約 30 dB、話し声は約 60 dB、交通の近くは 85 dB 以上になることが多いです。だから同じ音でも距離や環境で感じ方は大きく変わります。
音圧は距離や環境で変化します。音源を近づけると音圧は上がり、遠ざけると下がります。また部屋の壁が厚いと音の反射を抑え、耳に届く音の強さが和らぎます。聴覚は個人差があるため、同じ音でも感じ方が違う点を意識しておくと良いでしょう。
この話の要点は、音圧は現象として現れる物理量であり、それを基準に生活の工夫を考えると、より安全で快適な環境を作れるということです。
騒音はどう測るの?
騒音を測るときは音響計という道具を使います。現場の空間で音の強さを測定し、dBA と呼ばれる人間の聴覚感度に合わせた重み付けをした値を用います。dBA は高周波の音を少し弱める設計で、私たちが感じる騒音に近い数値になります。
日常生活での例を挙げると、図書館は静かさを保つため約 30 dBA 前後、普通の会話は約 60 dBA、工事の騒音は 70〜90 dBA に達することがあります。距離や遮音、反射の有無によって実測値は変わるので、現場ごとに測定することが重要です。
測定には距離と設置位置が影響します。近くで測れば音圧は大きく、遠くで測れば小さくなります。表現の仕方として、dBは「比の大きさを示す対数スケール」である点を覚えておくと、音の大小を比較するのが楽になります。
違いを知ると生活はどう変わる?
この違いを理解すると、私たちの生活の質を上げる選択が増えます。音楽を聴くときには適切な音量の目安を守り、長時間の視聴でも適度な休憩を取り、イヤホンの選び方にも気をつけることができます。耳を守るためには、密閉性の高いイヤホンやノイズキャンセリング機能を活用するのも一つの方法です。睡眠を守る工夫としては、就寝前の騒音源を減らす、厚手のカーテンや二重窓を取り入れる、白色雑音を使って周囲の音を抑えるなどが挙げられます。
社会全体の視点では、都市計画や建築設計の段階で騒音を抑える努力が必要です。住環境の改善は長い目で見れば健康と生活満足度の向上につながります。私たちは日常の選択を通じて、より安全で快適な「音の世界」を作ることができます。
音圧の話を友達にする時、私はこう切り出します。音は見えない波だからこそ、測る道具が必要なんだと。音圧はその物理的な強さで、騒音は人が感じる不快さの総称だと伝える。距離を離すと音圧は下がるし、部屋の壁を厚くすると反射が減る。つまり、現実の生活には音圧と騒音の両方を意識する工夫が必要なんだ、という具合に話すと、友達も『なるほど』と納得してくれる。





















