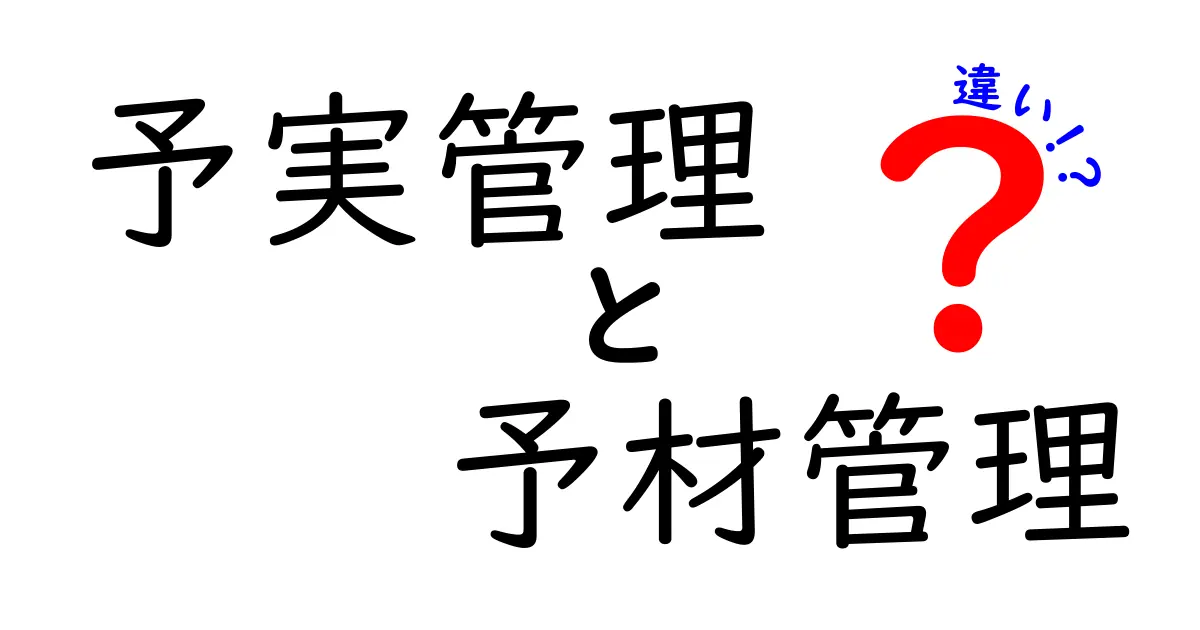

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
予実管理と予材管理の違いを徹底解説:数字と資材の計画でプロジェクトを成功へ導く実践ガイド
このブログは、企業の現場でよく耳にする「予実管理」と「予材管理」の違いを、中学生にもわかる言葉で丁寧に解説します。
まず結論から言うと、予実管理は“数字の世界”を見張る作業、予材管理は“資材の世界”を動かす作業です。
どちらも計画と実行の間にあるギャップを縮めるために必要な視点ですが、焦点とデータの種類、使う場面が異なります。
この2つを正しく使い分けると、予算オーバーを防いだり、資材不足で止まらないようにしたり、プロジェクト全体の安定性を高められます。
予実管理とは
予実管理とは、計画していた金額やスケジュールと、実際に起こった出来事を比較して差を分析する手法です。
たとえば、学校の文化祭を企画する時、当初の予算が100万円で、現時点までに使ったのが70万円、残りの予算は30万円とします。
ここでの作業は、実際の支出を日付ごとに記録し、どの項目が予定より多くかかったのか、どの工程が遅れているのかをはっきりさせることです。
この“差”を原因とともに把握することで、次の決定に生かすことができます。
予実管理には、以下のようなデータが中心になります:
予算・実績・差異・原因。
ここでのポイントは、データの正確さとタイムリーさです。
データが古かったり不正確だと、差が大きく見えて混乱します。
日次・週次・月次のいずれで見るかはプロジェクトの規模と性質で決め、関係者が同じ情報を同じタイミングで共有できるようにします。
予材管理とは
予材管理とは、材料や部品、納期、在庫量など“資材の動き”を計画・追跡する作業です。
例を挙げると、学校の文化祭で使う装飾用材料を、いつ発注するべきか、どのくらいの在庫を持つべきか、リードタイムはどのくらいか、などを決めます。
資材が足りなくなると作業が止まってしまいます。そこで、発注点・安全在庫・納期の管理を徹底すると、必要なときに必要な量が手元にある状態を作り出せます。
予材管理では、在庫量・発注点・リードタイム・納期管理といったデータが中心になります。
このデータを、購買部門・現場・調達担当者が共有することで、ムダと遅れを減らします。
違いのポイント
予実管理と予材管理は似ているようで、求めている情報と意思決定の場面が異なります。
以下のポイントを押さえると、どちらを使うべきかがわかりやすくなります。
- 目的の違い: 予実管理は「計画と実績の差を把握して予算や日程のズレを修正すること」が主目的。予材管理は「資材の過不足を防ぎ、納期遅れを防止すること」が主目的。
- 対象データ: 予実管理は費用・日付・進捗の実績データを扱う。予材管理は在庫量・発注点・納期といった資材データを扱う。
- 頻度とタイミング: 予実管理は月次・週次での報告が多い。予材管理は日々の在庫チェック・週次の発注計画が中心。
- 関係者: 予実管理は経営者・プロジェクトマネージャー・会計部門が関与。予材管理は購買・現場・サプライチェーンの担当が中心。
- 成果の見え方: 予実管理は「コスト削減・納期遵守・利益率改善」の数値で現れる。予材管理は「材料不足による遅延の回避・ロスの削減・在庫コストの低減」で現れる。
両者を同時に見られると、プロジェクトの全体像が見やすくなります。
例えば、予実管理で「予定より支出が増えた」ことが分かったとしても、予材管理のデータで資材の遅延が原因かどうかを突き止めることで、対策を的確に選ぶことができます。
つまり、数字と物の動きをつなぐ橋渡し役として、2つの管理が互いを補完し合う関係です。
実務での活用例
実務では、まず日常の習慣としてデータを正しく収集し、定期的に見直すことが大切です。
以下の例は、企業の小規模プロジェクトを想定した簡易ケースです。
予実管理のポイント例:
① 予算の根拠を明確にする(どの item がどれだけかかったのかを個別に記録する)
② 実績が出たら原因を分析する(なぜこの費用が増えたのか、作業の遅れはどこで発生したのか)
③ 週次で差異を報告する(差異の大きい項目を重点的に改善する)
予材管理のポイント例:
① 納期の厳守を目指す資材は発注点を下回らないよう管理する
② 安全在庫を設定し、急な需要増にも対応できる体制を作る
③ リードタイムを短縮するためのサプライヤーとの連携を強化する
今日は友だちとの雑談風に、予実管理について深掘りしてみます。僕らが日常生活で使う“計画と実際”の差を、学校行事や部活の活動に置き換えて考えると、自然と理解が深まります。予実管理は、“何にいくら使ったか”を記録して、予定と現実のズレを見つけ出す作業です。差が出たときには原因を探り、次にどう動くべきかを決めます。つまり、未来を良くするための地図づくりですね。私たちの部活の活動計画でも、予算や時間配分を適切に管理することで、練習と試合の両方をスムーズに進められます。





















