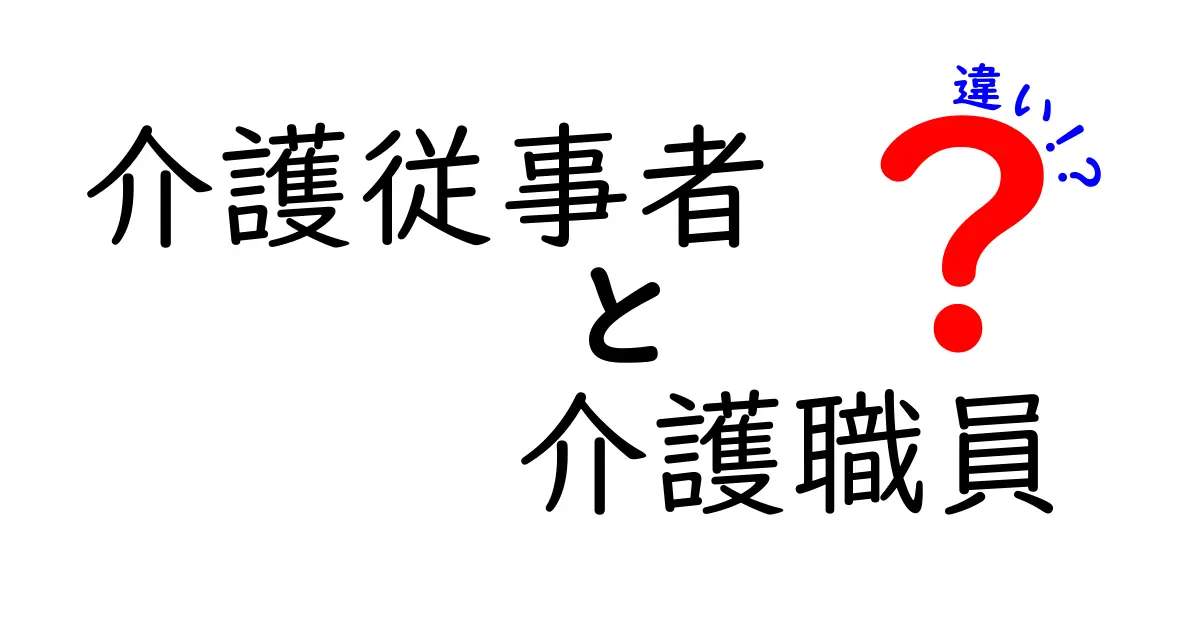

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
介護従事者と介護職員はどう違うの?
介護の現場でよく耳にする「介護従事者」と「介護職員」。この2つの言葉は似ているため、混同されがちです。実は意味や使われ方に微妙な違いがあるのです。
まず、「介護従事者」というのは、介護に関わる全ての人を指す広い言葉です。たとえば、介護施設で働く人はもちろん、訪問介護をする人や家族の介護をしている人など、介護に関わる人すべてが含まれます。
一方、「介護職員」は、介護サービスを提供する仕事として働く人のことをさします。つまり、介護施設や訪問介護事業所などで雇われている専門のスタッフを指します。
まとめると、介護従事者はもっと広い意味で、介護職員はその中の業務に従事する専門スタッフを指す言葉と言えます。
では具体的にどんな人たちがいるのか、さらに詳しく見ていきましょう。
介護従事者に含まれる人とは?
介護従事者は文字通り「介護に従事する者」。
そのため以下のような人たちが含まれます。
- 介護職員(施設や訪問で働く専門スタッフ)
- 家族介護者(家族で介護をしている人)
- ボランティア(介護支援をするボランティア活動者)
- 看護師やリハビリスタッフ(介護現場でサポートに関わる専門家)
実は、介護に関わっているすべての人が「介護従事者」といえるわけです。
行政や法律上の文書でも「介護従事者」という言葉は、幅広く使われることが多いです。
だから「介護の仕事に関わるすべての人」というイメージを持つとわかりやすいでしょう。
介護職員の役割と特徴
介護職員は「介護サービスを提供するスタッフ」という意味です。具体的には施設や訪問介護事業所に所属し、以下のような仕事をします。
- 利用者の身体介護(食事・入浴・排せつ介助など)
- 生活支援(買い物や掃除などの手伝い)
- 介護記録の作成や報告
- 介護計画の実施
なお、介護職員には「介護福祉士」や「介護職員初任者研修」など、資格を持つ人も多く、専門知識や技術を身につけています。
つまり、介護職員は専門的に介護サービスを行う職業の人。
そのため賃金を得て働き、働き方も雇用契約に基づいていることが多いのが特徴です。
わかりやすい表で違いをチェック!
まとめ
今回は「介護従事者」と「介護職員」の違いを解説しました。
どちらも介護現場に欠かせない言葉ですが、介護従事者は「介護に関わる全ての人」、介護職員は「介護サービスの専門職にあたる人」と覚えておくと良いでしょう。
介護の世界はチームで支え合うことが大切です。両者の違いを理解することで、より働きやすい環境や理解が深まるでしょう。
ぜひ、この記事を参考にして介護の仕事や役割を理解してみてください。
介護職員という言葉を聞くと、資格を持ったプロフェッショナルだけを指すイメージがありますが、実は介護福祉士や初任者研修を修了した人など、さまざまな資格レベルのスタッフが含まれます。たとえば、初めて介護の仕事に就く人でも「介護職員」と呼ばれ、現場で経験を積むうちにスキルアップしていくのが一般的です。つまり、介護職員は単なる職業名であり、資格や経験の段階に応じてさまざまな人がいるのです。
また、雇用形態も正社員からパート、派遣まで多様です。現代の介護現場はチームワークが大切なので、それぞれの特色を活かして役割分担がされています。介護職員という言葉一つでも、奥深い世界が広がっているんですね。思ったよりも身近な仕事だと感じませんか?
次の記事: 人間ドックと生活習慣病検診の違いを徹底解説!どちらを選ぶべき? »





















