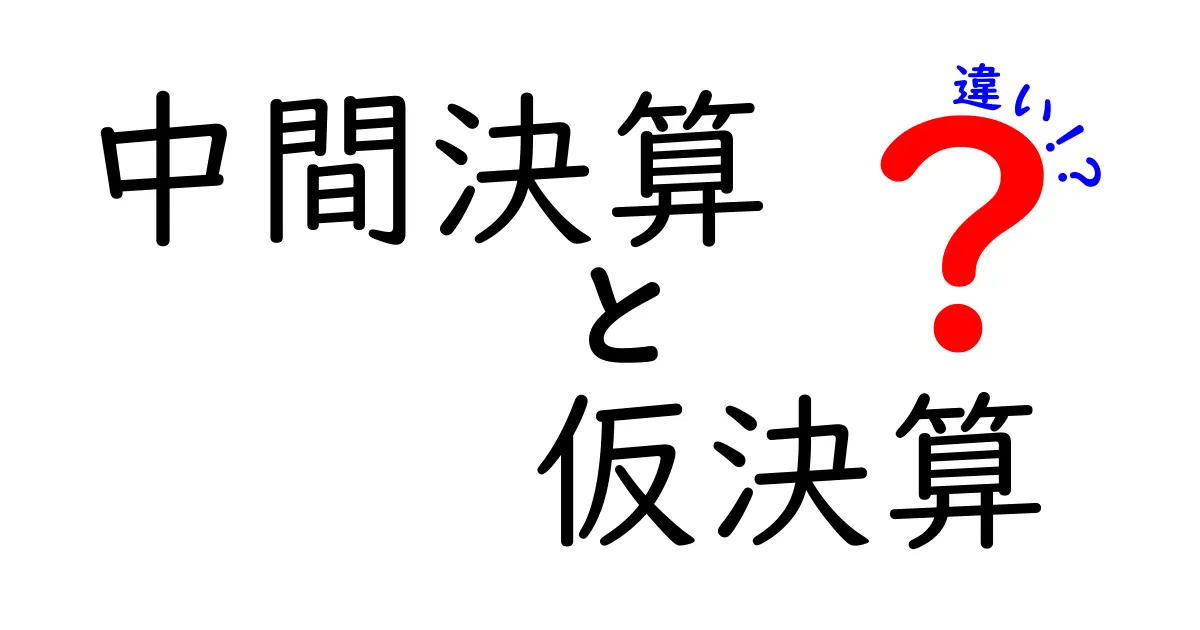

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中間決算と仮決算の違いを徹底解説
中間決算と仮決算は、会計の世界でよく混同されがちな2つの用語です。中間決算は、年の途中の会計期間までの成績を正式な形に整え、外部の関係者へ向けて公表する準備を整えます。仮決算はその前段階で、まだ確定していない数字を使って「概算」を作る作業です。中間決算は通常、財務諸表としての整合性が高く、監査を受ける場合も多く、株主や金融機関など外部の関係者に影響を与えやすいです。一方、仮決算は経営判断の材料として使われることが多く、月次の予算の見直しや資金計画の作成、運用の改善などに役立ちます。ここでポイントなのは、仮決算の数字は最終的な確定値ではないという点です。公表される前に修正されることが普通で、正確さを優先する場合には正式な中間決算の公表を待つ必要があります。
日本の企業は特に、株主や取引先、銀行などの利害関係者に対して、途中経過を示すことが重要です。中間決算は「今どれくらいの利益が出ていて、資産はどうなっているか」を具体的な数値で示します。これにより、資金繰りの計画が立てやすくなり、投資判断の材料にもなります。仮決算は、それより前の時点での見積もりで、最終決算の準備として使われます。
この二つは、期間の区切りがどこにあるか、公開・監査の有無、そして数字の確定性という点で大きく異なります。
以下の表では、ポイントを整理しておきます。
これを読むだけで、声を大にして「仮決算は仮、中間決算は確定」と覚えるのに役立つでしょう。
違いのポイントを3つに整理
ここでは、中間決算と仮決算の違いを理解するための3つのポイントを詳しく解説します。
まず第一は「期間の区切りと数字の確定性」です。中間決算は年の途中で区切られ、数字は一般的に確定しています。一方、仮決算は終わりの時点で確定していないため、後日修正されることが普通です。
次に「公表の義務と監査の有無」です。中間決算は外部へ公表されることが多く、場合によっては監査が入ります。仮決算は内部用が多く、外部公表の水準には達していないこともあります。
最後は「実務での使い方」です。中間決算は資金調達や投資判断など、外部のステークホルダーへ説明する材料として使われます。仮決算は予算の精度を上げるための内部資料として活用され、最終決算に向けた動きを予測します。
実務での使い方と注意点
現場での実務としては、仮決算を作るタイミングと中間決算を作るタイミングを区別することがとても大切です。
仮決算は月次の予算の見直し、資金繰りの改善、経営計画の仮置きなど、早期の意思決定を促す目的で用いられます。数字が確定していない分、実務上は「保守的な見積り」を避け、現実的で根拠のあるデータを使うことが求められます。
また、中間決算は完成度の高い資料として、株主総会や銀行との交渉に使われることが多いです。監査法人の指摘を受けることもあり、過去の実績と照合して「整合性」を保つ作業が欠かせません。
注意点としては、仮決算の数字を過大評価したり過小評価したりすると、後の決算で大きな修正が生じ、信頼を損ねる可能性がある点です。常に「最終的な数字は後日確定する」という前提を全関係者と共有し、記録を残しておくことが重要です。
仮決算って、ちょっと聞くと難しそうだけど、実は現場の人が早く数字の見通しを立てるための道具なんだ。仮決算は“いまのところの数字の見積もり”みたいな感じで、正式な決算にはまだ届いていない。だから、後で数字がずれることも普通にある。けっこう大切なのは、仮決算を見ただけで結論を出さないこと。仮決算はあくまで材料の1つで、最終決算と照らし合わせて判断するのが正解。もしズレが大きくなれば、すぐに修正しましょう。学校の財務の授業でも、友達と喋るくらいの気軽さで説明できるように練習するといい。仮決算の重要な役割は、経営者が来月の方針を決めやすくする点で、費用の計画と資金の流れを先に俯瞰できる点だ。
次の記事: 当期と期中の違いがひと目で分かる!中学生にもやさしい解説ガイド »





















