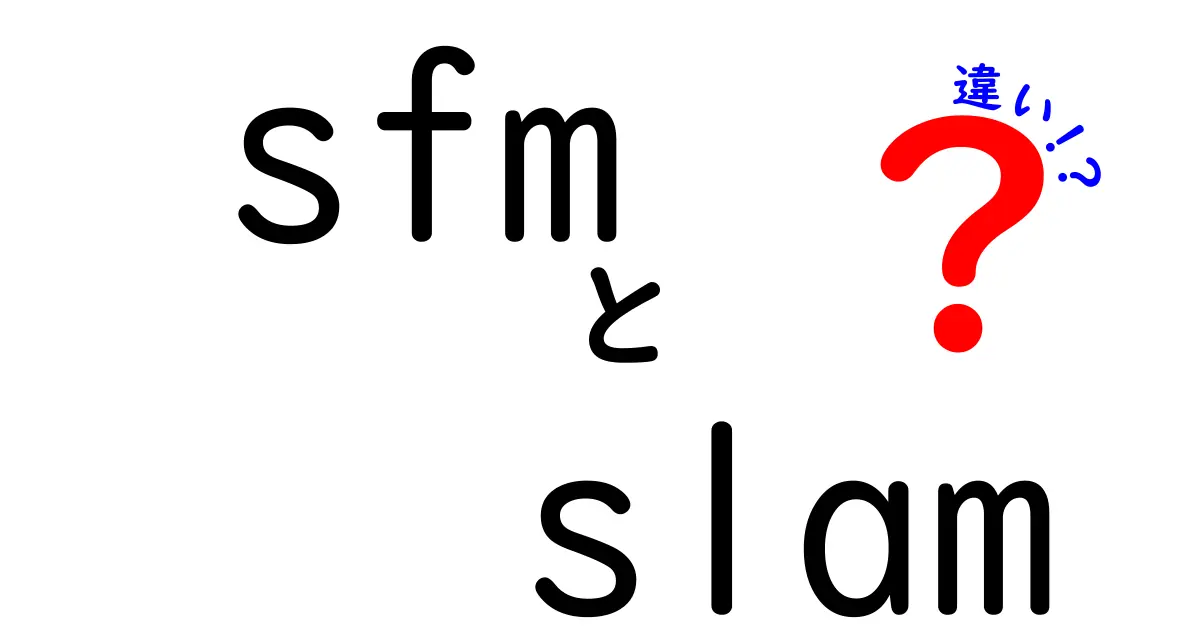

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
SFMとSLAMの違いを正しく理解するための3つのポイント
SFMとSLAMはどちらも3次元の世界を扱うための技術ですが、使われる場面と前提が大きく異なります。まずポイントとして、入力データの性質、目的、出力の種類、そして時間軸の扱いです。SFMは静止している環境の3Dモデルを作ることが多く、写真や動画から点群を復元します。動画の連続性は利用されますが、基本は“過去の視点から現在の場景を再現する”作業です。SLAMは移動体の現在位置を推定しつつ、周囲を地図化します。つまり“今ここにいる自分”を常に見失わないよう、経験則と計算を組み合わせて地図を更新します。これらの違いを知ると、どの技術がどの場面に適しているかが自然と見えてきます。
次に、処理の難しさやリアルタイム性、スケールの扱いといった要素も重要です。SFMは高品質な写真データがあれば高精度のモデルを比較的短時間で作ることが可能ですが、対象が動くと再現性が低下します。SLAMは動く対象に強い一方、リアルタイム処理の制約が厳しく、センサのノイズやループ閉鎖の問題をどう克服するかが課題になります。最後に、今の技術動向として、ビジュアルSLAMの研究が活発で、深層学習を使った特徴抽出やマッピング手法の統合が進んでいます。
SFM(Structure from Motion)とは何か
SFMとはStructure from Motionの略で、カメラの動きを推定しつつ複数の写真から3D情報を復元する技術です。基本的な流れは、まず画像中の特徴点を検出し、次に異なるフレーム間で対応点を見つけ、これを使ってカメラの姿勢とシーンの3D点を同時に推定します。パンやズーム、距離の変動など、視点の変化が大きいほど推定は難しくなりますが、適切に補正すれば高精度な点群を作ることができます。
SFMでは、通常、静止したシーンを前提にして、スケールの決定を外部情報(既知の距離や物体サイズ)で行うことがあります。入力としては主に写真が使われ、計算リソースが許す範囲で最適化を行うため、数十枚〜数百枚の写真が必要になることもあります。現場でのコツとしては、撮影時の均等な視点、十分なオクルージョンの管理、露出の整合を意識することです。
SFMの実務は、静かな風景や建物の内部など“動かないもの”をきれいに3D化する用途に強く、観察者が自由な視点で眺められるモデルを作るのに適しています。写真の品質と撮影計画次第で、非常にディテールの細かいモデルが得られます。現場のデータを丁寧に整えることが、最終的な成果物の出来を大きく左右します。
SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)とは何か
SLAMは同時定位・地図作成の略で、移動体が周囲の情報を同時に使って地図と自己位置を推定する技術です。RGBカメラだけで行うビジュアルSLAMや、LiDARと組み合わせるLiDAR-SLAM、深度カメラを活用するRGB-D-SLAMなど、センサの組み合わせにより派生が生まれます。基本は、連続するフレームから特徴点を追跡し、位置の変化を積分して地図を更新します。
SLAMの難しさは、移動中の環境での光の変化、動的な物体、センサのノイズ、そしてループ閉鎖時の最適化誤差の蓄積にあります。リアルタイム性が求められる場面では、計算の最適化とアルゴリズムの安定性の両立が課題です。現代のSLAMは、深層学習を使った特徴量の頑健化や、地図のグローバル整合性を保つアルゴリズムの改善が進んでいます。
実務での使い分けとポイント
実務での使い分けは、最終的な目的とデータ取得条件で決まります。静止的な対象を高精度に3D化したい場合はSFMが適しています。反対に、動くロボットが未知の場所を走行するシナリオではSLAMが不可欠です。表現の尺度感(ミリメートルから数十メートル)、リアルタイム性、計算リソースの可用性を考慮して選択します。
派生技術も考慮しましょう。SFMは後処理での3Dモデル作成に強い一方、SLAMはリアルタイム処理と自己位置推定の安定性を重視します。実務では両者を組み合わせるケースもあり、たとえば走行中の車がSLAMで地図を作り、停止後にSFMでその場の高品質モデルを生成するといった応用が考えられます。
今日はSFMとSLAMの違いを雑談風にまとめてみた。SFMは写真から3Dを作る作業で、静かな風景を美しい3Dモデルに変える魔法みたいな感じ。SLAMは車が街を走る時に“自分は今ここにいるよ”と地図を同時に作る仕組み。つまりSFMは“何がどうなっているかを再現する技術”、SLAMは“自分の位置を把握しつつ周りを描く技術”という理解でOK。どちらも視覚データを扱うが、対象と目的が違うため、使い分けが重要だという話になる。





















