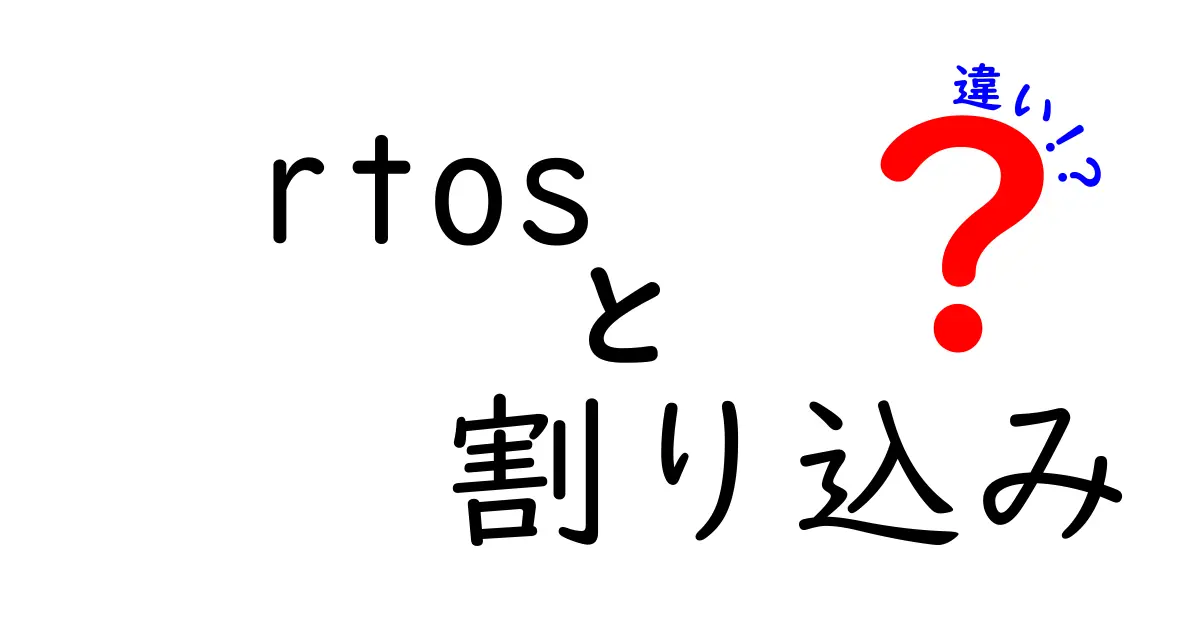

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:RTOSと割り込みの基本を押さえよう
まずは言葉の意味をそろえましょう。RTOSとは「リアルタイム性を重視したオペレーティングシステム」のことです。自動車の衝突回避装置や工場のセンサーなど、決められた時間内に反応することが命を左右する場面で使われます。ここで大切なのは「デッドライン」という期限を守ることと、同時にいくつもの仕事を公平に処理する能力です。
RTOSはこうした要件を満たすため、タスクの実行順序を決めるスケジューラと呼ばれる心臓部を持っています。
次に「割り込み」についてです。割り込みはハードウェアからの信号で、今CPUが別の仕事をしていても「今すぐこの出来事に対応してほしい」と知らせてくれる仕組みです。たとえばボタンを押したり、温度センサーが危険な値を読み取ったりすると、CPUは現在の処理を一時停止し、割り込みサービスルーチン(ISR)と呼ばれる短い処理を優先的に実行します。ISRは長い処理をすると全体の遅延を引き起こすため、基本的には「短く、すばやく終える」ことが求められます。
RTOSにおける割り込みの特徴には、優先度の概念やプリエンプション(高い優先度の割り込みが来たら、現在の作業を一時停止して優先処理を行う仕組み)があります。これにより、危険なイベントが起きてもデッドラインを破らないように動くのです。ただしISRの実装は慎重に行う必要があります。ISRが長引くと他のタスクの応答が遅れてしまい、全体のリアルタイム性を失ってしまうからです。
実務での使い方のイメージをつかむには、次のポイントを覚えておくとよいでしょう。
1. 割り込みは事件の「入り口」として短く設計します。
2. ISR内では長い計算やメモリ確保を避け、必要な情報を保存して後でタスクに渡します。
3. 実際の処理の多くは「デファード処理(後回し処理)」として別のスレッド/タスクで行います。
この3つを守るだけで、安定したリアルタイム性を保つことができます。
ポイントまとめ:リアルタイム性を確保するにはISRを短くする、優先度を正しく設定する、データ競合を避ける、デファード処理を使う、という3点が基本です。実世界のアプリではこの考え方を土台に、適切なデータ共有の設計やデバッグ手法を追加していきます。
割り込みの仕組みとRTOSの実務的ポイント
割り込みが発生すると、CPUは現在の作業状態を「コンテキスト」と呼ばれる情報を保存して、中断した場所からISRを実行します。ISRが完了すると、元の作業に戻ります。ここをうまく設計すると、レスポンスの予測性(最悪応答時間の保証)を高めることができます。RTOSはタスクの優先度と同期機構を使って、ISRからデータを受け取った後の後続処理を適切な順序で走らせます。
実務でのコツは以下のとおりです。
・ISRはできるだけ短く。ハードウェアからデータを受け取って共有データを守るための最小限の処理だけを行い、長い処理は別スレッドへ渡します。
・共有リソースの保護を徹底します。割り込みが発生しているときにもデータが壊れないよう、ミューテックスやセマフォなどの機構を使います。
・デファード処理の活用。ISR内ではキューへデータを入れる、イベントフラグを立てるなど、後で実行するタスクに通知して処理を分離します。
もう少し具体的な場面を考えてみましょう。センサからの1kHzのデータを読み取るとき、ISRはデータを受け取ってリングバッファに格納し、後で別のタスクがそれを取り出して処理します。これにより、ISRは「すぐに反応する」役割に徹し、長時間の計算を避けられます。この考え方は、制御系やロボット、IoTデバイスの多くで同じです。
要点を再整理します。
1. ISRは短くする。
2. 共有データは保護する。
3. デファード処理を活用して、リアルタイム性と安定性を両立させる。
4. RTOSのAPIはISR内でも安全に使えるものを選び、ISRと通常タスクの境界をはっきりつける。
この設計を通じて得られるのは、予測可能性と信頼性です。デバッグの際にはISRの実行時間を測定し、最悪応答時間を計算する練習をしましょう。現場では、テストと検証を重ねることで、突発的なイベントにも耐えられるソフトウェア設計が身についていきます。
友だちA: ねえ、割り込みってなんでそんなに大事なの? B: だって、車のブレーキが急に効かなくなると困るでしょ。割り込みはすぐ反応する仕組みだよ。けれどISRは短くって言われる。なんでかっていうと、長い処理をしていると他の大事なイベントを逃しちゃうからさ。だからデファード処理を使って、すぐにはデータを集めて、後でまとめて処理する。そんな設計のコツがRTOSにはあるんだ。
前の記事: « ビットと量子ビットの違いを徹底解説!中学生にも分かる基礎知識





















