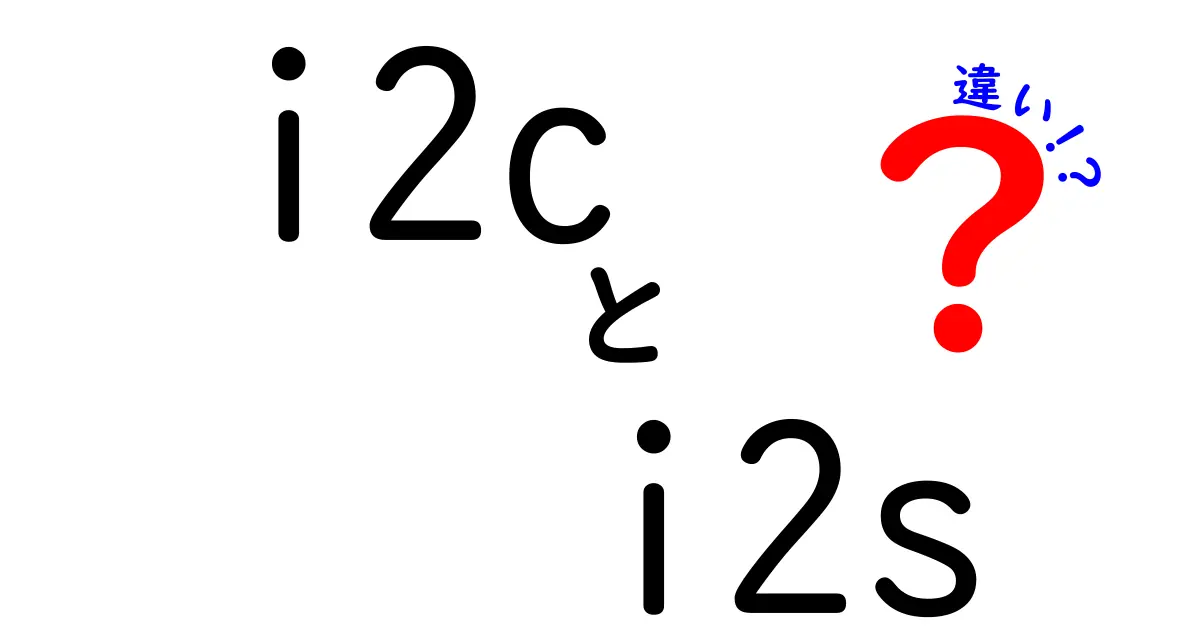

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
i2cとi2sの違いを理解する基礎講座
まず、i2cとi2sは、私たちが電子機器と話すときに使う“約束事”の名前です。
i2cは2本の線だけで複数の機器を接続する汎用的な通信バスで、SDAとSCLという線を使い、マスター役のデバイスがアドレスを指定して特定のスレーブ機器とデータを交換します。小さな部品同士を手早くつなぐのに向いており、センサー、EEPROM、レジスタなどを同じバス上で扱えます。速度は一般的に100kHz〜400kHz程度が多く、最近の機器では1MHz程度の高速モードもありますが、音声データの連続転送には向きません。
このため、目的は“設定情報のやり取りや小さなデータの読出し/書込み”で、複数デバイスを配線点数を抑えつつ管理する場合に最適です。
一方、i2sは音声データを連続して転送するための専用の規格です。データ線(SD)、ビットクロック(SCK)、ワードセレクト(WS)という3つの信号で、左チャンネルと右チャンネルのデータを順番に流します。
この方式はタイミングの正確さが命で、サンプルレート(例: 44.1kHz, 48kHz, 96kHzなど)とビット深度(例: 16bit, 24bit)が合っていれば、ノイズやズレを最小限に抑えつつ高品質な音声を再現できます。
また、i2sはアドレス指定を使いません。送るデータの意味は機器間の“音声ストリーム”として認識され、DACやADCといった音声系機器が受け取って再生・変換を行います。長い距離を走る場合でも、規格に沿った配線と適切なボード設計で安定します。
総じて説明すると、i2cは“制御と情報のやり取り”を担う汎用バス、i2sは“音声データを正確に運ぶ音声インターフェース”です。名前が似ていて混同しやすいですが、目的と使い道がまったく違います。覚え方のコツとしては「i2cは制御の道、i2sは音楽の道」と覚えると混乱が減ります。さらに、両方を同時に使う場面もあり、設計者は信号のタイミングと配線設計をよく考える必要があります。
ある日の放課後、友人とガジェットをいじっていたときのことです。私たちはi2cとi2sの違いを混同していたので、実際に小さな工作で確かめることにしました。i2cでは温度センサーを1つずつアドレスで読み取り、別のセンサーを同じバスに接続してみると、配線が少なくても複数機器を管理できる点に驚きました。一方、i2sは音声データの流れを体験することで、データのタイミングがいかに大事かを痛感しました。音が途切れないようにクロックを合わせる作業は、まるでリズムの練習のようでした。結局、i2cは設定や制御、i2sは音声の流れを担うと理解でき、これを覚えると授業での設計案が描きやすくなると実感しました。





















