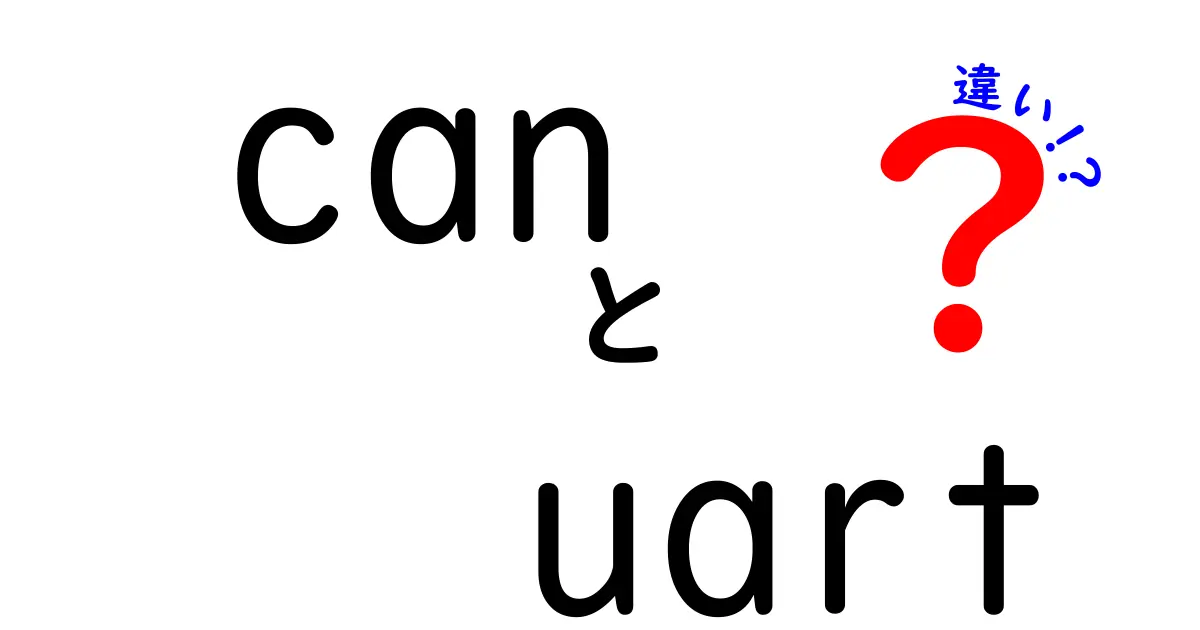

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
can uart 違いを徹底解説!初心者にも分かるポイント3選
はじめに、CANとUARTはどちらも「データを送る仕組み」という点では同じですが、実際には役割や使われる場面、信号の形、そして動作の仕組みが大きく異なります。ここでは、中学生にもわかるように、3つのポイントを軸にCANとUARTの違いを整理します。まず大切なのは「どんな場面で使うのか」という視点です。自動車の内部で複数の部品が同時に情報を交換するのがCAN、マイコンとパソコンのように1対1で会話するのがUART、というように、基本の発想が違います。
次に、信号の作り方と伝送の仕組みを見ていきましょう。CANでは信号が差動で流れ、ノイズに強く距離が長くても安定します。UARTは単一の信号線でデータを送るため、ノイズに弱く、長距離を送るには別の工夫が必要です。これらの特徴は、どんな伝送距離や接続台数を想定しているかに影響します。こうした基本を押さえると、CANとUARTの“適している場面”が自然と見えてきます。
この章では、信号の性質の違いと設計上の影響をさらに深掘りします。CANは差動信号で、+と−の差を読みます。
このためノイズを打ち消す力が強く、金属箱の中を走る車の環境や工場のノイズの多い場所でも信頼性が高いです。 UARTは通常、TTL相当の単一端子を使い、ノイズの影響を受けやすいので、距離が近く、ケーブルが短い環境で使うと良いです。これらの性質の違いが、配線の長さやデバイス数、必要な信頼性の水準を決める大きな要因になります。
先生と生徒が机の上で一緒に学ぶ場面を想像してみてください。CANは「皆で読み取り・共有する」感じで、車のECU同士の会話、産業機器のセンサ群の情報伝達、建物内の監視システムなどに適しています。UARTは「1対1の会話」を前提とするので、マイコンとPCをつなぐ開発用接続、センサモジュールとマイコンの短距離データ送信、モジュール間のデバッグ用通信などに向いています。つまり、CANは多地点・長距離・信頼性重視、 UARTは少地点・短距離・自由度高の組み合わせです。
CANと UART の基本的な違い
CANとUARTの基本的な違いを知るには、まず「通信の仕組み」を比べると分かりやすいです。CANはマルチマスタ方式と呼ばれ、複数の機器が同時に通信できます。データは識別子とデータ部で構成され、送信権の争奪はビットの優先順位で自動的に行われます。このため、複数のセンサーやECUが同じ線を使って情報をやり取りしても、衝突して混乱することが少なく、信頼性が高いのです。UARTは一対一の基本形です。片方が送信、もう片方が受信します。データの送受信は「開始ビット・データビット・パリティ・停止ビット」といった段階を踏み、相手が受け取り確認を返してくれるまで次のデータを送れないようにすることが多いです。こうした違いが、使う場面を大きく変えます。
もう一つの大事な違いは「信号の物理的な性質」です。CANは差動信号と呼ばれる方法を使い、2本の線で−と+の差を見ます。これによりノイズを打ち消し、長い距離でも誤りを減らせます。UARTは通常、単一の線(または2本の線)を使ってデータを直列に送ります。端末のレベルはTTLや電圧レンジに依存し、長距離になると電圧が落ちたり、ノイズの影響を受けやすくなります。これらの点を理解すると、通信距離や設置場所、周りの機器の数といった条件を見ながら適切な方法を選ぶヒントになります。
この部分では、それぞれの特徴を「実際の機器例」でイメージしてみましょう。CANの実例としては、車のECU同士の通信、産業機器のセンサ群の情報伝達、建物内の監視システムなどが挙げられます。UARTの実例としては、マイコンとPCをつなぐプログラミング用の接続、センサモジュールとマイコンの短距離データ送信、モジュール間のデバッグ用のシリアル通信などが挙げられます。つまり、CANは「多点・長距離・信頼性重視」、UARTは「1対1・短距離・実装の自由度が高い」という感じです。
伝送方式とバスの違い
伝送方式の違いを具体的に見ると、CANは「バス型の多点通信」が基本です。多くの端末が同じ2本の線を共有して情報をやり取りします。ある機器が話そうとすると、他の機器が話していない時間を見つけて自分のデータを送ります。このとき、衝突を避けるための自動的な衝突回避機能が働き、複数機器が混雑しても安定します。 UARTは原則として1対1の通信です。1つの送信ラインと1つの受信ラインがあり、基本的には誰も邪魔をしません。ただし、長距離や複数機器と話す場合には、RS-232/RS-485といった拡張規格を使って距離やノイズの問題を解決します。これらの違いを覚えると、設計の初期段階で「どの配線を使うべきか」「どう配線を回すべきか」が自然と決まってきます。
この部分では、それぞれの特徴を「実際の機器例」でイメージしてみましょう。CANはバス型通信の代表例で、車のECU同士の会話、産業機器のセンサ群の情報伝達などに使われます。UARTは長距離の伝送には適さないことがあるため、短距離のデバイス間での通信に最適です。こうした違いを知っておくと、設計段階での前提条件が整理され、後の検証やデバッグもスムーズになります。
用途別の選び方と注意点
用途を決めるときには、まず「接続できる機器の数」と「距離」を考えます。車のように多くのセンサーが同時に情報を出す環境ではCANが向いています。自動車だけでなく、産業機器の複数の装置の協調動作にも適しています。一方、マイコンとPC、あるいは小さな開発ボード同士のテストにはUARTが手軽で効率的です。次に考えるのは「信頼性と誤り検出」です。CANはエラー検出・再送・衝突回避機能が組み込まれており、ノイズが多い環境でもデータの正確性を保てます。UARTは単純で高速にデータを送れますが、誤り検出は最低限のレベルにとどまりがちです。最終的には予算・設置場所・運用上のニーズを総合して判断します。
この章の要点は、設置場所の環境と接続機器の数を基準に、CANとUARTのどちらが現場に適しているかを判断する力を養うことです。さらに、実務では規格の違いだけでなく、信号終端やグラウンドの取り方、適切なケーブル配線ルール、デバッグ時のツール選択など、現場の細かな運用が結果を左右します。これらを押さえると、設計の初期段階から実装・検証・運用までの工程がスムーズに流れるようになります。
要点のまとめと表での比較
ここまでを整理すると、CANとUARTにはそれぞれ長所と短所があることが分かります。CANは「多点・長距離・高信頼性・自動衝突回避」が強みで、車や工場などの複雑なネットワーク向けです。UARTは「1対1・シンプル・低コスト・設定の自由度が高い」が魅力で、個別のデバイス間の素早い通信や小規模な開発に適しています。次に、より分かりやすい比較表を用意しました。以下の表は、要素ごとにCANとUARTの違いを一目で見られるようにしたものです。
このように、設計条件に応じて選択肢を絞ることが大切です。最後にもう一つの大事なポイントとして、学習の順序があります。まずはUARTを使った小さな通信から始めて、次にCANの環境を整える練習へ移ると、理解が深まりやすいです。分からない専門用語が出てきても、焦らずに一つずつ意味を確認していくと、電子回路の世界がだんだん身近に感じられるようになります。
今日はCANとUARTの違いについて、友だちと休み時間に雑談しているイメージで深掘りしてみます。私が一番気にしているのは“信号の読み方が変わると設計がぜんぜん違う”という点です。CANは差動信号のおかげでノイズに強く、複数の機器が同時に会話できるので、車のECUのような大きなネットワークには欠かせません。一方UARTは1対1の会話が基本なので、距離が短いときはとても手軽で速く作れる。で、その中間の状況はどうするの?という質問もよく出ます。そんな時には、RS-485やロジックレベルシフタを使って距離を伸ばす方法や、信号ラインを分散させる設計のコツがあるよ。実際のプロジェクトでは、まずはUARTで動作確認をしてからCANのような複雑な環境へ移行するケースが多い。つまり、学習の順番としては“まずはシンプル→次に多点・信頼性”というのが王道なんだ。
前の記事: « UARTとUSBの違いを解説!中学生にもわかる実践ガイド





















