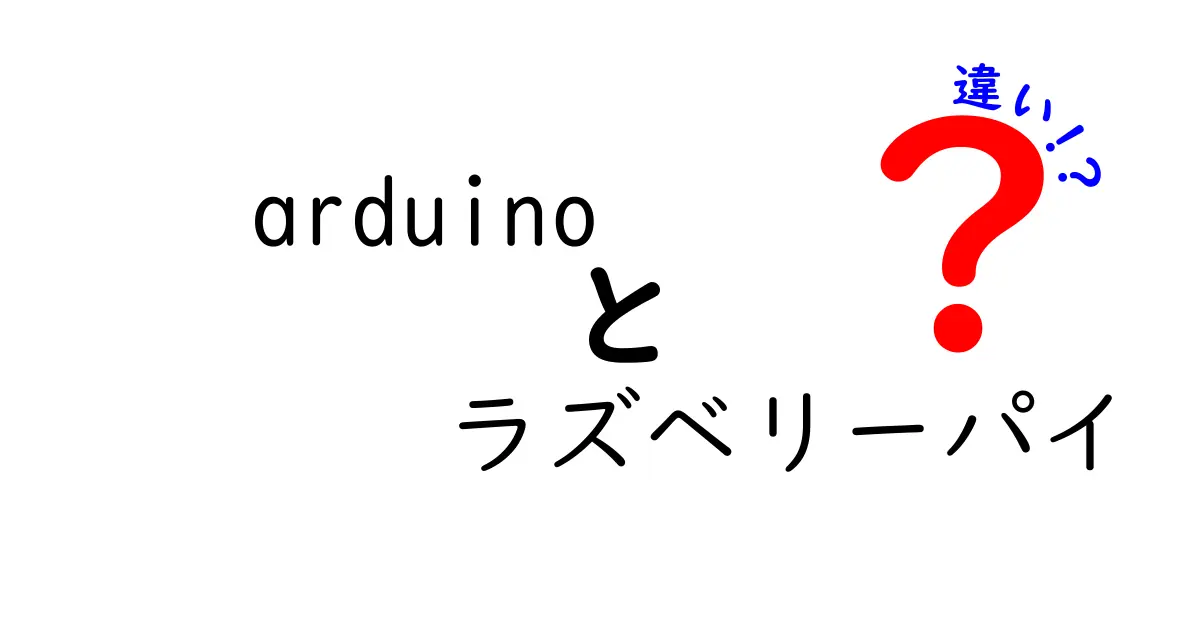

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
Arduinoとラズベリーパイの違いを理解する基礎
この二つはよく比較されますが、それぞれの得意分野が異なります。Arduinoはマイクロコントローラーとして動作の確実性に強みを持ち、リアルタイム性が重要な小規模な制御タスクに向いています。例えば温度センサの読み取り、LEDの点灯、モータの回転制御など、決まった動作を決まった順序で確実にこなします。OSはなく、プログラムはボードの中に詰まっています。開発環境は主にArduino IDEを使い、C/C++風の言語で記述します。安価で小型、消費電力も低いので、手頃な実験や学習の入口として最適です。
一方、ラズベリーパイは小さなパソコンとして動くのが大きな特徴です。OSが動くためファイル管理やネットワーク、画像処理やウェブアプリの実行も可能です。PythonやScratchなど複数の言語を使える点も魅力で、ウェブカメラを使うプロジェクトやミニサーバー、メディアセンターの構築などが現実的になります。電源は通常USB供給程度で済みますが、Arduinoに比べて消費電力は大きめです。RAMは数百MB〜数GB、ストレージはSDカードやUSBメモリで拡張できます。
差が生まれる根拠はOSの有無と処理能力の大きさです。Arduinoはマイクロコントローラー中心でリアルタイム性を強く求める場面に適しています。Piは多機能で多様なアプリを同時に動かせますが、熱管理や電力の管理にも気を配る必要があります。重要なポイントはOSの有無とリアルタイム性と電力消費です。目的をはっきり決めて選ぶと迷いが減り、学習の効率も上がります。
以下は代表的な違いを一目で比較できる表です。実際のプロジェクトでの判断材料として活用してください。
なお、下記は初心者にも分かりやすい要点だけを抜粋しています。
どちらを選ぶべきかを決めるコツは 「OSが必要かどうか」と 「リアルタイムな制御が必要かどうか」を基準に考えることです。
この表を見て分かるとおり、OSの有無と処理能力の差が選択の分かれ道になります。まずは自分の作りたいものが リアルタイムな制御中心かOSを使ったアプリ中心かを考え、そのうえで予算や入手性、学習の進め方を決めるとよいです。
最近友人と話していて Arduino の話題が出ました。Arduino は小さな回路の世界の入口みたいな存在で、最初の一歩を踏み出すハードルがとても低いんです。私も最初は LED を点灯させるだけの課題から始めましたが、回路図とコードが一つづつ動く瞬間のワクワク感は今でも覚えています。
それに、Arduino は部品が安く、失敗しても傷が浅いのも魅力。だからこそ気軽に触って学べる点が学生にも人気なんですね。とはいえ Arduino だけで完結することは少なく、 Raspberry Pi や他の機器と組み合わせると表現の幅がぐっと広がります。結局は、”やってみる”ことが最も大事だという結論にたどり着きます。





















