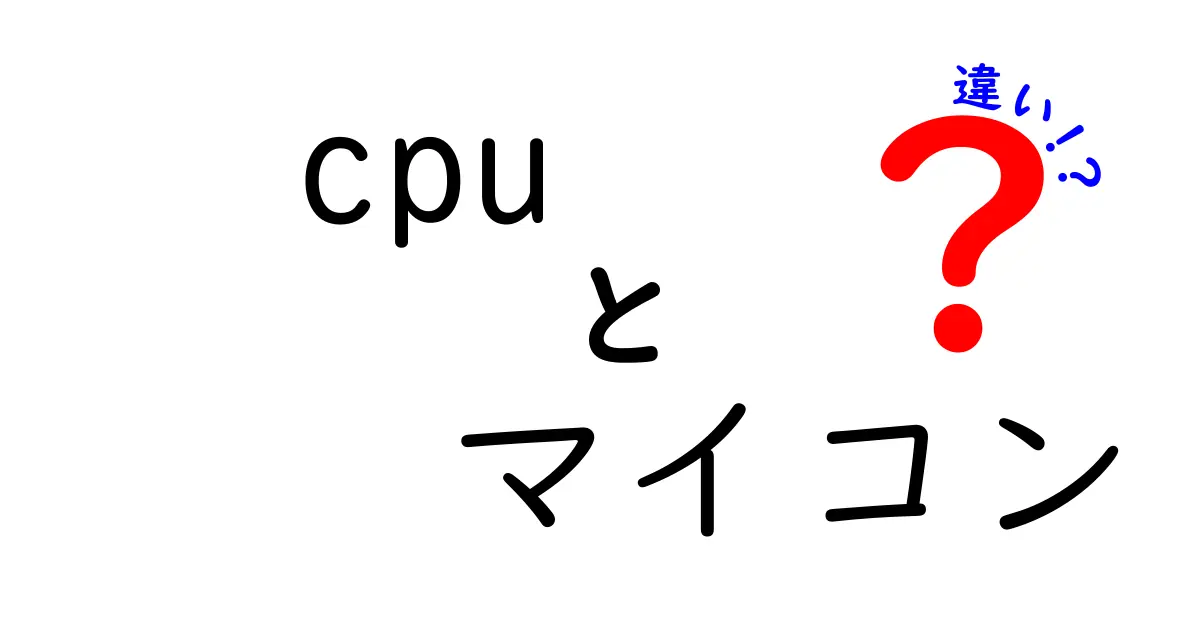

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CPUとマイコンの違いを知ろう
まず言葉の意味から始めます。CPUとはCentral Processing Unitの略で、パソコンやスマホの頭脳です。高い汎用性を持ち、さまざまなソフトウェアを動かすことができます。一方で、マイコンはマイクロコントローラの略で、センサーやボタン、LEDなどの機器を直接動かすための小さな頭脳と周辺部品がセットになった一体型のICです。CPUは通常、複数の部品(メモリ、周辺機器、バス)と連携して動作しますが、マイコンは一つのチップに「CPU」「メモリ」「入出力」が集約されているのが特徴です。
この違いを理解するだけで、IT機器がどう動くかを少し身近に感じられるようになります。
次に設計の観点を見ていきましょう。CPUは多くの場合大量のソフトウェア資源を前提に作られており、OSやアプリの組み合わせで性能が決まります。対してマイコンは組み込み用途に特化したソフトウェアが中心で、リアルタイム性や省電力が求められる場面が多いのが特徴です。つまり、CPUは「何を動かすかを選ぶ自由度が高い」道具、マイコンは「何を作るかを直接形にする道具」と言えるでしょう。
この差を押さえるだけで、デバイス設計の初期段階でどちらを選ぶべきかの判断がぐっとしやすくなります。
実際の使い分けと選び方のコツ
ここでは、実務での使い分けのコツを解説します。組み込み製品を作る場合は、まず要求機能をリスト化してからCPUかマイコンかを絞ります。もし外部の周辺機器との連携やOSが必要であればCPU系の開発環境になります。一方、センサーだけで完結する低電力デバイスを作るときにはマイコンの方が適しています。
また、学習の観点から言えば、マイコンはIoTの「入り口」として最適です。入門用のボード(例: Arduino系、Raspberry Pi Picoなど)は安価で、初学者が回路とソフトウェアの両方を同時に体験できます。これは理解を深めるための最短ルートであり、理論だけでなく実際の動作を見ることで記憶に残りやすくなります。
長くなるときは、実際の製品例を見てみましょう。スマートホームのデバイス、車載情報システム、産業用機器などはそれぞれの用途に合わせてCPU寄りの設計かマイコン寄りの設計かが決まっています。企業や研究機関はこの判断を通じて、コスト、消費電力、信頼性の三つのバランスを取ります。ここで覚えておきたいのは「同じ目的でも部品の選択方法が違う」という点です。適切な選択ができれば、性能を最大化しつつ開発期間を短縮することができます。
ある日の放課後、先生がCPUとマイコンの違いを尋ねたとき、友達の一人はこう答えました。CPUは“頭脳そのもの”で、マイコンは頭脳と体が一体になった小さな機械だ、と。私はその表現がとても腑に落ちました。スマホの内部で動く処理も、家庭の温度計を動かす回路も、結局はCPUと周辺の部品の組み合わせです。マイコンは、用途がはっきり決まっている道具箱。CPUは、何を作るかを自由に決められる巨大な道具セットです。初めての回路づくりで迷ったとき、この考え方が進む道を示してくれました。





















