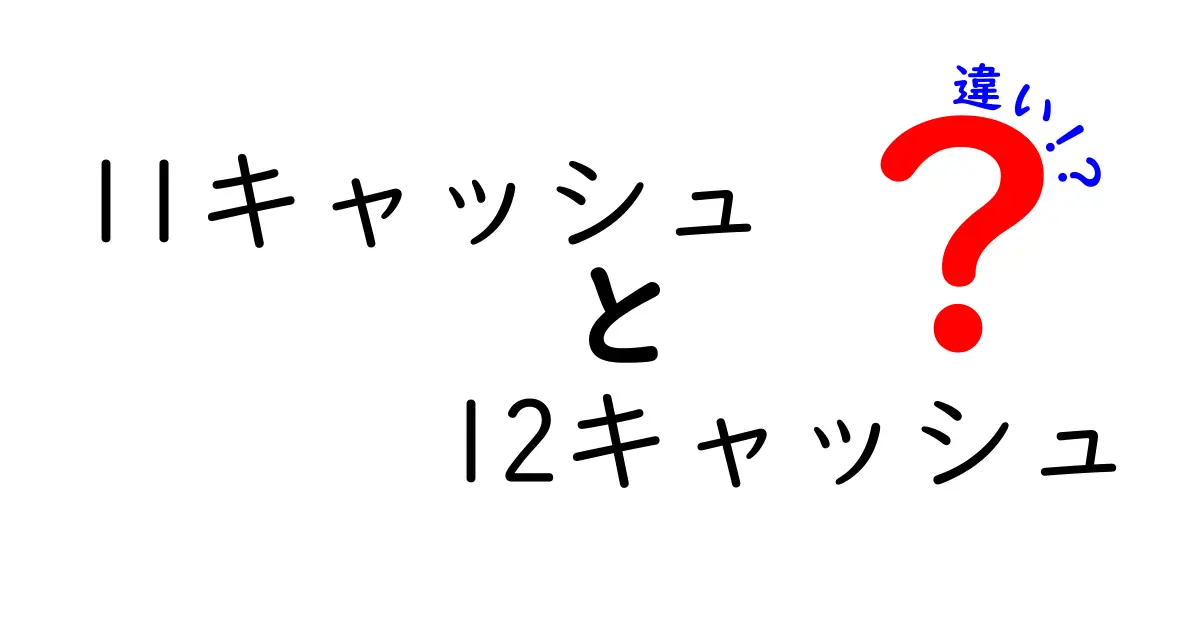

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
l1キャッシュとl2キャッシュの基本を押さえる
この章ではまず L1キャッシュ と L2キャッシュ の基本的な役割を押さえます。CPU のキャッシュはデータを素早く取り出すための「小さな引き出し」のような仕組みです。L1キャッシュ は作業中に最も頻繁に使うデータや命令を格納し、CPU コアに最も近い場所に配置されます。そのため、アクセス速度が信じられないほど速く、ヒットすると数サイクル程度でデータを取り出せます。ただし容量はとても小さく、詰め込めるデータは限られます。これに対して L2キャッシュ はもう少し大きく、複数のコアが共有して使う設計が多いです。 L2キャッシュ は L1キャッシュ が失敗したデータを補い、RAM への頻繁なアクセスを減らす役割を果たします。つまり、L1キャッシュ は「超近くて超速いが小さい」、L2キャッシュ は「少し離れていて大きいが遅い」という基本的なトレードオフを持つのです。現代の CPU では、L1キャッシュは命令とデータを分けて管理する場合と、データキャッシュだけを持つケースが多く見られます。これにより、同じプログラムでも使われるデータの性質によって、L1・L2 のヒット率の差が生まれ、全体の処理速度に大きな影響を与えます。なお、具体的な容量は世代や設計によって異なりますが、L1は数十キロバイト程度、L2 は数百キロバイトから数メガバイトの範囲に収まることが一般的です。こうした特徴を知っておくと、プログラムを作るときにデータの並べ方を工夫して計算を速くするヒントが見つかります。
この知識は、日常のプログラミングだけでなく、ゲームの最適化やスマホ・パソコンの動作を理解するうえでも役立ちます。なぜなら、キャッシュの動きは実際の体感速度に直結するからです。例えば、同じゲームでもキャッシュの活用次第で描画が滑らかになったり、バックグラウンド処理が遅くなることを避けられたりします。中学生のみなさんが将来、ゲーム作りやアプリ開発をする時にも、この差を意識してデータの配置を考えれば、効率のよいソフトウェア設計につながります。最終的には、L1と L2 の二つの引き出しをどう組み合わせて使うかが、使い手の「速さの体感」を決めるのです。
友達Aと私の会話。A: ねえL1キャッシュって本当に速いの?どういうデータがそこに入るの?B: うん、それは“近さ”と“容量”のせいだよ。L1はCPUに一番近い引き出しで、頻繁に使うデータを入れておく。だから取り出しが一瞬。だけど容量が小さくて、すぐにパンパンになる。そこでL2の出番。L2はもう少し離れた場所にあり、大きなデータを蓄える倉庫みたいな役割。必要なデータがL1にないとき、L2が代わりにデータを渡してくれる。二つの引き出しをうまく使えば、ゲームの動作も滑らかになる。私たちは、データをどう並べて走査するか、配列を連続したメモリに置くかを考えながらコードを書く。これが現代のソフトウェアの秘密で、少しの工夫で体感速度が大きく変わる。
前の記事: « ramとsheepの違いを徹底解説|意味と使い方を完全ガイド





















