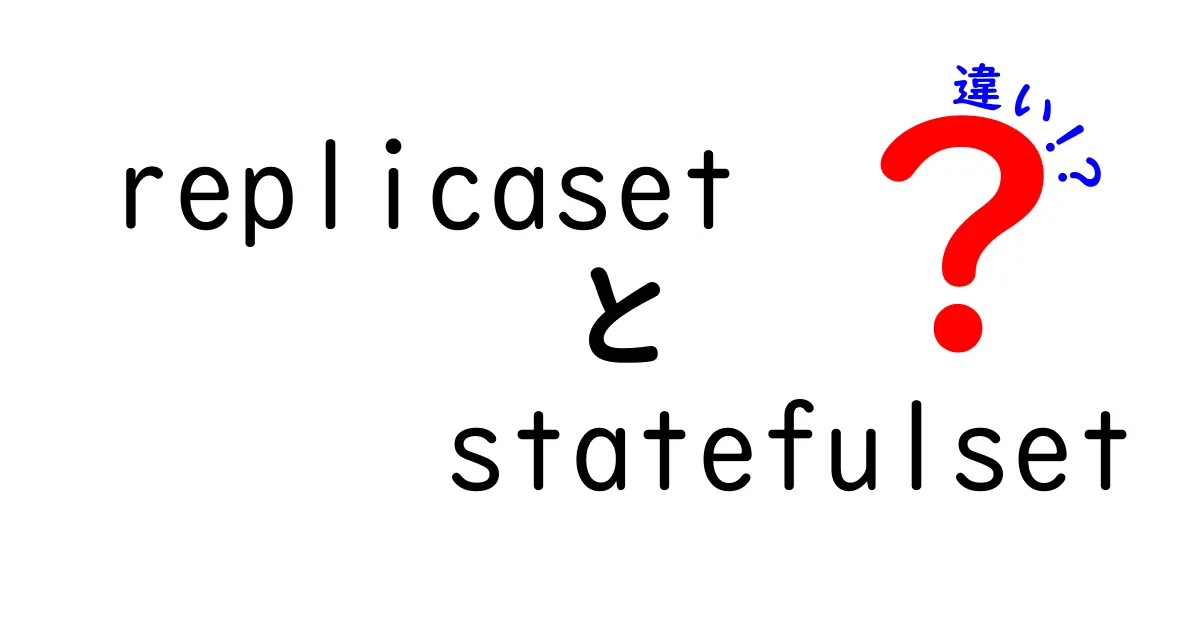

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:ReplicasetとStatefulSetが出てくる理由
Kubernetesを使うとき、ReplicasetとStatefulSetは似ているようで大きく違います。Replicasetは「同じ仕様のポッドを複製して数を維持する仕組み」で、横に同じポッドを増やしたり減らしたりするのが主な目的です。対してStatefulSetは「名前付きのポッドに安定した識別子とストレージを割り当て、順序を守ってデプロイと削除を行う」ことを目指します。これらはどちらもスケールアウトのための機構ですが、設計思想が異なるため、使い分けを誤ると「データの喪失」「ネットワークの不安定」「アップデートの失敗」といった問題に繋がります。この記事では、まず基本の違いを整理し、次に実務での使い分け方を具体例とともに解説します。
学習のコツは「どの要素を安定させたいのか」を軸に考えることです。例えばアプリがステートレスならReplicaset+Deploymentで十分なことが多く、状態を持つデータベースや分散ストレージを扱うならStatefulSetが向いています。
この区別を理解すると、クラスタの信頼性と運用の難易度のバランスを取る判断が速くなります。
このセクションの要点として、識別子の安定性、ストレージの扱い、デプロイの順序、スケーリングの挙動、そしてユースケースの代表例を覚えておくと良いです。
基本概念の違いを押さえるポイント
まず大事なのは「識別子の安定性」と「ストレージの永続性」です。Replicasetが作るポッドには名前がつかず、デプロイのたびに新しいポッドIDが割り当てられることが多いです。これがどういう問題になるかというと、ポッド間のステートレス性が前提なので、データをローカルに保持する設計のアプリには適さない場合があります。一方、StatefulSetは各ポッドにordinalな識別子を割り当て、ネットワーク名が固定されるため、データベースのノードやキャッシュ層など、同じノードが再起動後も同じ役割を担い続ける場面に強いです。さらにStatefulSetはストレージをポッドごとに永続化する仕組みを備えています。
スケーリングの挙動にも差があり、ReplicaSetは基本的に同時にスケールしますが、StatefulSetはポッドの起動順序と削除順序を守るため、スケールアウト時に多くのケースで順次起動します。これにより、外部リソース(データベース接続数、負荷テストの影響、バックアップの整合性など)を安全に管理できます。このような性質の違いを頭に入れておくと、設計段階で「どちらを使うべきか」を間違えにくくなります。
実務での使い分けと具体例
現場での判断は、アプリの性質と運用要件で決まります。Statelessアプリ(例:ウェブフロントエンド、計算処理のジョブなど)は、ReplicasetをベースにしたDeploymentで問題なく動作することが多いです。これらはスケールアウトとロールアウトの更新が比較的自由度高く、ポッドの一部に障害が起きても全体としての機能に影響を最小限に抑えられます。逆に状態を持つアプリ(データベース、キーバリューストア、ファイルストレージを扱うサービスなど)はStatefulSetの方が安定します。なぜならデータはポッドのライフサイクルと切り離せず、再起動時にも同じストレージボリュームと識別子が確保されるため、整合性が保たれやすいからです。実務では、まずアプリが「ステートをどこまで持つか」を評価し、次にデプロイ戦略を決めます。もしデータベースのリーダー/フォロワーの役割分担や、シャーディングの設計があるならStatefulSetと組み合わせたStorageClass、VolumeSnapshot、PVCのテンプレート化を検討します。
また、運用面ではバックアップの取り扱い、スケーリングスケジュール、障害時の復旧手順を事前に設計しておくことが重要です。StatefulSetでは特に「ホットスタンバイの最小化」「障害時の再同期の仕組み」を意識して設定を行いましょう。
具体的な運用例と注意点
例えば、Redisのようなインメモリ型であっても永続ボリュームを使う場合にはStatefulSetの安定性が役立ちます。なぜなら再起動後も同じデータを参照でき、クラスタリングのノード番号が固定されることで、外部システムが接続先を再構成せずに済む。ここがStatefulSetの大きな強みです。対して、Web APIの番人のような役割を担うアプリは、ReplicaSetとDeploymentの組み合わせで十分です。ここで大事なのは「アップデート戦略」と「ヘルスチェック」の定義です。更新の際にはReadinessProbeやLivenessProbeを適切に設定し、失敗時のロールバックを検討します。最終的には、個々のケースに合わせて、StatefulSetだけを使うのか、それともDeployment+ReplicaSetで代替するのか、あるいは他のオーケストレーション機能と組み合わせるのかを判断する力が求められます。
違いをざっくり表で比較
この章では要点を短く再整理します。表を参照するだけでも、視覚的に違いを理解する助けになります。まずは基本的な相違点を数値的・性的に比較しておくと、実務で迷ったときにもすぐ判断材料になります。
まとめ:状況に応じた選択を
ReplicasetとStatefulSetは、それぞれ得意な領域が違います。アプリがステートレスかどうか、データの永続性がどの程度必要か、デプロイの順序とアップデートの挙動をどう管理するかを軸に考えると、最適な選択が見えてきます。初学者のうちは「とりあえずReplicaSetでいこう」と思いがちですが、実務では状態を扱う場面が増えるため、StatefulSetの理解は避けて通れません。覚えておきたいポイントをまとめると、以下の3点です。1) 識別子とストレージの安定性、2) デプロイの順序とスケーリングの挙動、3) 代表的なユースケース。これさえ押さえれば、クラスタ運用の設計図がスッキリと描けます。今後もアップデートが進むKubernetesの世界で、基礎を固めることが最も有効な投資になるでしょう。
ねえ、StatefulSetの話を雑談風にしてみよう。StatefulSetは名前付きのポッドと永続ストレージをセットで扱うユニットって感じで、起動順序を守るから、データベースみたいな“私の役割”を変更せずに再起動できるんだ。最近のクラスタ運用で、アプリケーションの挙動を少しでも安定させたいときにはStatefulSetの設計思想が役立つよ。例えば、キャッシュが落ちても再起動後にすぐ同じノード名で復活することで、外部システムが接続先を再構成せずに済む。こうした“名札が変わらない”特徴が、運用の鍵になる――そんな感じの雑談です。





















