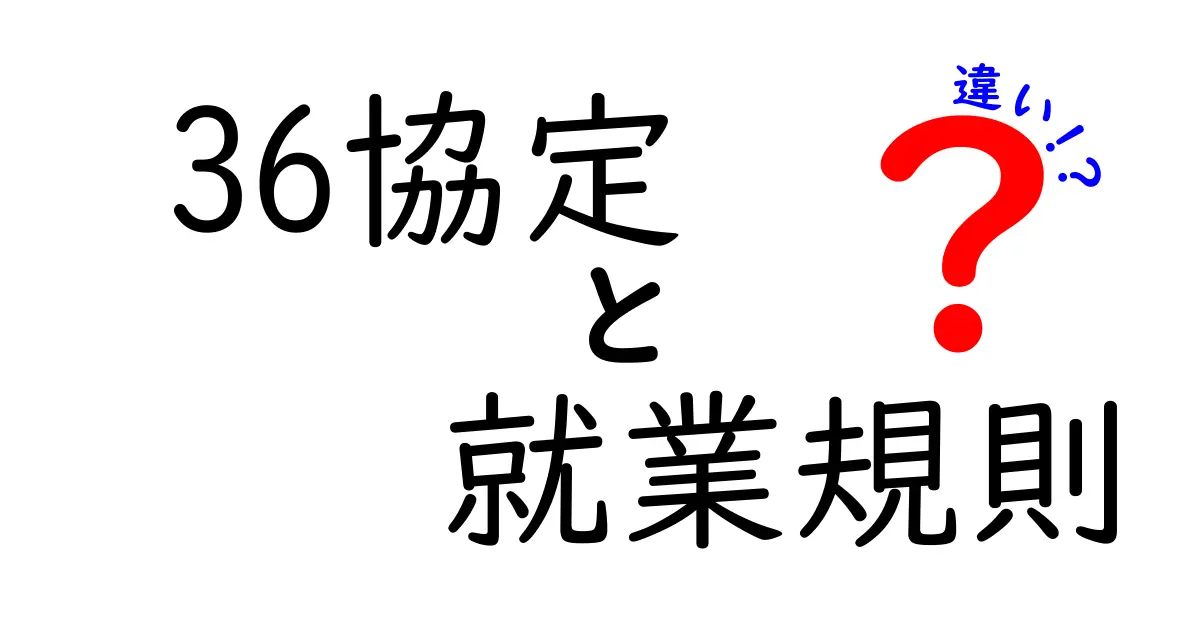

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:36協定と就業規則の違いをしっかり把握しよう
日本の職場にはさまざまなルールがあって、特に「36協定」と「就業規則」はよく似た言葉のように見えますが、役割や使われ方が大きく違います。ここでは、中学生にもわかる言い方で、両者の基本的な意味、適用範囲、実務での運用の差を整理します。まずは結論から言うと、36協定は「時間外労働の上限を決める労使間の協定」、就業規則は「社内で働く人のルールブック」という性質があり、どちらも違う目的と手続きで成り立っています。
36協定は労働基準法の下で定められ、個々の労働時間を超える残業を行うには必ずこの協定が必要になります。就業規則は、主に勤務時間、休日、賃金、休暇、懲戒等を取り決める社内の規程で、従業員が働く際のより具体的で日常的なルールを示します。
両者は補完関係にあり、目標が異なるため、混同すると法的なトラブルやトラブル回避の判断ミスにつながりやすいのです。ここから、それぞれの特徴、違い、実務での注意点を、わかりやすく順番に見ていきます。
1. 基本の意味と法的根拠
36協定は「時間外労働・休日労働」に関する基本的な取り決めを、労使の代表者と会社が結ぶ協定です。日本の労働基準法は、1日の上限と週の上限を原則として定めており、これを超えて働くには労働基準監督署への届出と適用労使協定が必要です。特に、繁忙期やプロジェクトの締め切り前など、一時的に長時間勤務が必要になる場合、36協定に基づく特別条項を設けることがあります。ルールとしては、上限を必ず守ること、超える場合は別途協定を結ぶこと、そして超過分には割増賃金が発生することなどが挙げられます。ここで重要なのは、36協定は「残業を許す制度」ではなく「残業を合法的に認める条件を定める」制度だという点です。つまり、会社が長時間働かせる権利を勝手に作るのではなく、労働者と話し合って定めるものです。
2. 適用範囲と対象
就業規則は、会社の内部で働く人々の勤務時間・休日・賃金・休暇・規律などを網羅的に決める「社内ルールの骨格」です。これに対して36協定は、時間外労働・休日労働の許容範囲を具体的に定め、どれだけの残業が可能か、どのような場合に特例があるかを、労使の代表者と会社が合意します。適用範囲としては、就業規則が全員に適用されるのに対し、36協定は残業が発生する場面に限って適用されます。これらが混同されると、実務で「残業の許可があるのに就業規則に違反している」といった矛盾が生じ、労働者と会社の間でトラブルが起こることがあります。
3. 実務での違いと運用のポイント
現場での違いを押さえると、適切な運用が可能になります。就業規則は社内の日常ルールで、昇給・賞与、勤務割の組み方、有給の取り扱い、育児・介護休暇、懲戒手続などを含み、全員が同じ基準で働くことを保証します。
一方、36協定は時間外労働の法的な土台として機能します。長時間労働が必要になる局面で、労使代表と協議のうえ、具体的な上限時間や休日の取り扱い、休日出勤の扱い、割増賃金の支給要件を決め、所轄の労働基準監督署へ届出します。運用のポイントとしては、協定の更新期限を守ること、超過残業を避ける努力をすること、そして就業規則と36協定の整合性を保つことが重要です。これらを同時に適切に管理することで、法令遵守と従業員の負担軽減の両立が可能になります。
4. 表で整理:36協定と就業規則の違い
この表を見れば、両者が果たす役割の差が一目で分かります。就業規則は日々の働き方を決める“ルール本”、36協定は長時間労働を認める場合の“手続きと上限の合意書”と覚えると混乱を防げます。実務では、これらを別々の書類として管理し、更新時には必ず両方の整合性をチェックします。たとえば繁忙期には36協定の期限を意識して作業計画を見直し、通常期には就業規則の改定が必要かを検討する、といった運用が現場での適正な対応です。
おわりに:実務の要点を押さえよう
本記事で伝えたように、36協定と就業規則は別物ですが、職場を健全に保つためには両方を正しく運用することが大切です。法令遵守はもちろん、従業員の健康と安全を守る観点からも、適切な手続きを踏んで、透明性の高い運用を心がけましょう。
ある日の放課後、友達と学校の図書室で『36協定って難しそうだね』と言い合い、私は『でも、考え方はとてもシンプルだよ。残業をどう許すか、誰と決めるか、どんな場合に超えるのかをみんなで決める、ということだ』と伝えた。友達は『権利と義務のバランスだね』『学校の授業時間割みたいに、守るべきルールがあるから安心する』と頷いた。私はその後、宿題に戻りながら、働く人の権利を守る仕組みについて、日常の中にも学べる要素がたくさんあると実感した。





















