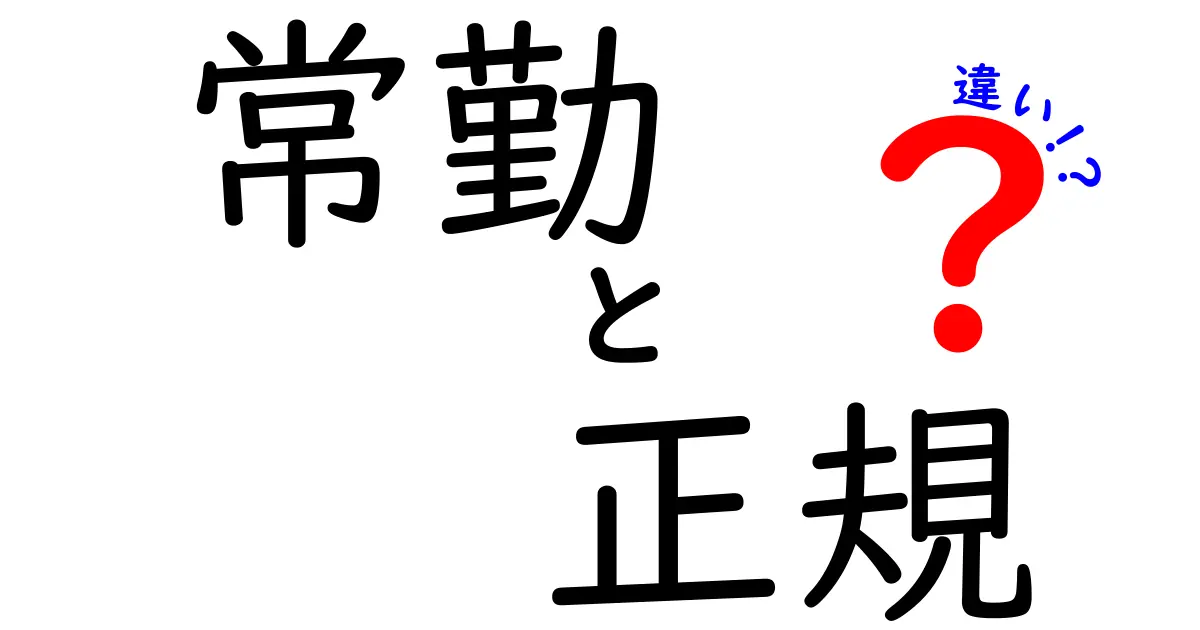

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:常勤と正規の違いを整理する基本の理解
「常勤」と「正規」は、日常の会話でも求人情報でも混同されやすい言葉です。ここでは、まず両者の基本を整理し、次の章で実務の現実にどう現れるかを見ていきます。
常勤は時間と出勤日数を前提にした働き方のことを指すことが多く、週40時間前後の勤務を想定するケースが一般的です。学校や病院、企業の人事の現場では、出勤日数や勤務時間を長くとることで、チーム運用の安定を図るために用いられます。
一方、正規は雇用契約の形態を表す語であり、正社員としての雇用が通常含まれます。正規雇用は、解雇手続きの安定性、福利厚生の対象範囲、昇給・昇進の機会などの点で優遇される傾向が多いのが実情です。とはいえ、両者は同時に成立することもあります。たとえば、正社員として採用され、かつ長時間の勤務を求められるケースがそれにあたります。
この二つの言葉は“時間の長さ”と“雇用の安定性”という異なる軸で語られることが多く、同時に成立するケースもあります。就活・転職のときには、求人票の表記をよく読み、どのニュアンスを指しているのかを見極めることが大切です。次の章では、実務上の違いを具体的な例で見ていきましょう。
実務と制度で見る違いの実例と注意点
実務の現場では常勤と正規の違いが、待遇や安定性、転職時の影響などの形で現れます。以下では、代表的なポイントを三つの軸で整理します。
- 観点1:勤務時間と契約の両立 - 常勤は時間の長さを重視するケースが多く、正規は契約形態の安定性が軸になります。
- 観点2:福利厚生の適用範囲 - 正規は福利厚生の対象範囲が広い傾向がありますが、企業ごとに差があります。
- 観点3:キャリアの道筋 - 正規職は昇進・長期のキャリア設計に有利な場面が多い一方、常勤だけでは計画が難しい場合もあります。
ここまでの話を日常の就職活動に結び付けると、求人票の表現をその場の文脈で読み分ける力が重要になります。正規という言葉が必ずしもすべての職場で同じ意味ではないことも理解しておくと良いでしょう。雇用条件の細かな違いは、職場の文化や部署の運営方針にも大きく左右されます。
次に、実務での注意点をいくつか挙げます。
1) 面接時には「常勤かつ正規」か、それぞれの意味を具体的に確認する。
2) 福利厚生の適用条件を事前に質問する。
3) 転職時には過去の雇用形態が新しい職場でどう扱われるかを確認する。
正規って何かを友達とカフェで話していたとき、私はこう答えました。正規とは企業と結ぶ長期的な雇用契約の形を指すことが多いですが、実際には福利厚生や昇進の機会など、待遇の広がりを含むことが多いのです。ところが常勤という働き方は時間の長さを軸にしており、正規と同じ職場でも常勤で非正規のケースもありえます。だから大切なのは求人票の言葉をその場の文脈で読み解く力です。私の友人は正規として採用が決まり、休日の取り扱いが改善されたと喜んでいましたが、同僚の中には正規でも残業が多く疲れるという声もありました。こうした話を聞くと、安定と実際の働き方は別物という感覚が生まれ、就職先を選ぶときには両方のバランスを見極める力が必要だと感じます。





















