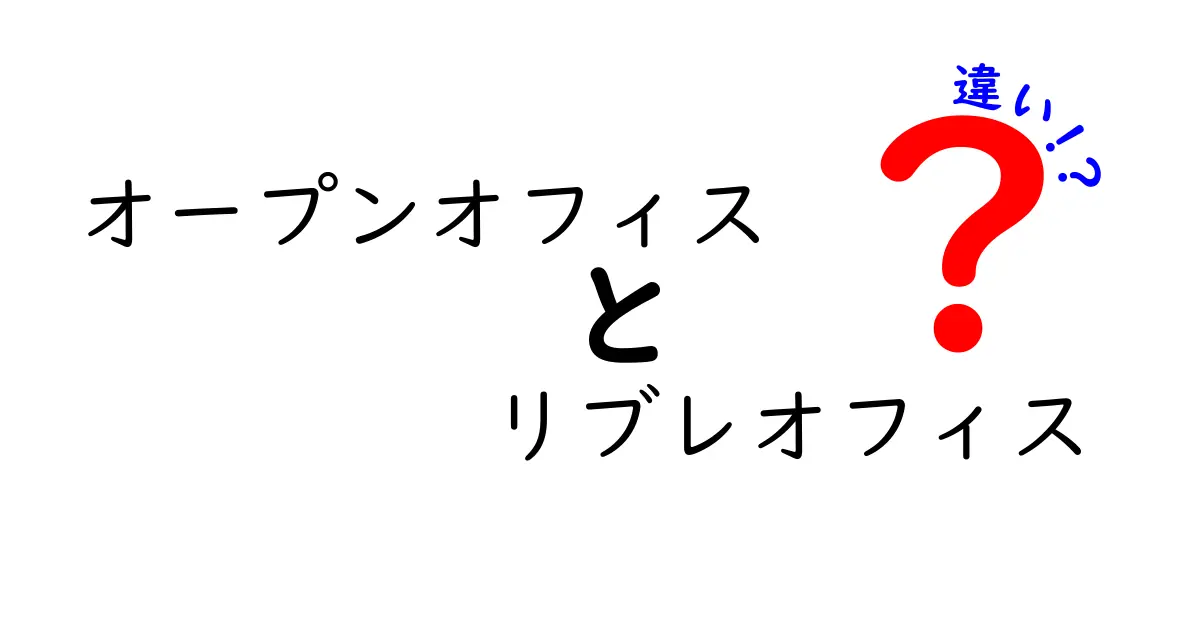

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
オープンオフィスとリブレオフィスの違いを総ざらい
オープンオフィスとリブレオフィスは似た名前を持つオフィスソフトですが、開発の方針や使い勝手には大きな違いがあります。本記事では初心者でも分かるように歴史的背景から機能の差、ファイルの互換性やサポート体制、そして日常の使い勝手までを丁寧に解説します。まず大枠として覚えておくべき点は二つは別個のプロジェクトであることです。オープンオフィスは過去にオフィスソフトの流れを受け継いできたプロジェクトであり、リブレオフィスはその派生として現在も活発に開発が続く現役のソフトです。
それぞれのソフトはワープロの writer 表計算の calc プレゼンテーションの impress など基本的な機能はほぼ同じです。しかし開発の現場での優先事項や標準対応の進み方が異なるため、実際の動作や細かな設定で違いを感じる場面が出てきます。ここからは具体的な違いを順に見ていきます。
歴史と背景
オープンオフィスはかつてのオフィスソフトの流れを受け継いだオープンソースのスイートとして始まりました。元々はサンマイクロシステムズのスターオフィスの流れを引く形で成長し、後にオラクルやアドミンの手を経て Apache 財団の管理下へ変更されました。一方リブレオフィスはこの流れの中で派生したフォークプロジェクトであり、開発の主導権を The Document Foundation が握っています。フォーク以降はより活発な更新と透明性の高い開発プロセス、そしてユーザーコミュニティへの参加機会の拡充を目指して進化を続けています。歴史的背景の違いは、機能の追加速度やバグの修正の頻度、サポート体制の柔軟性にも影響を与えます。結局のところ、どちらを選ぶべきかはそれぞれの利用ケースや所属するコミュニティの活動状況に左右されるのです。
機能と互換性
この二つのソフトの核となる機能は Writer Calc Impress Draw などの基本アプリが揃っている点です。文書の作成形の自由度、表組みの使い勝手、画像の挿入、図形の描画など日常的なオフィス作業に必要な機能はかなり共通しています。
ところが細かな機能の実装や拡張の点で差が現れます。例えばデータベース機能の取り扱い方法やマクロ言語のサポート状況、既存の拡張機能の互換性などです。LibreOffice は長年の間に多くの拡張機能を取り込み、最新のファイル形式やクラウド連携の対応にも前向きな姿勢を見せることが多いです。OpenOffice は基本機能の安定性と長い互換性を重視する場合があり、企業の安定運用を重視する人には信頼性が高いと感じられることがあります。ファイルフォーマットの互換性は双方ともに OpenDocument Format を基本としていますが、表現や数式の扱い、フォントの埋め込みの挙動など微妙な差が出ることがあります。
実際に使う場面を想像してください。学校の課題や部活動の資料作成、企業の報告書作成などです。綺麗な表を作るには Calc の機能が、見やすいレイアウトには Writer の機能が役立ちます。互換性の高いファイルを長い期間にわたって運用したい場合は、両方を試して自分の環境での再現性を確認するのが一番確実です。
使い勝手とデザイン
使い勝手は個人の感覚に依存する部分が大きいですが、実際の操作性には違いが出やすい領域です。LibreOffice は新しい機能を取り込みやすい反面、初期設定やメニュー構成が複雑に感じられることがあります。その一方で OpenOffice はシンプルで安定した操作感を保つ傾向があり、初めての人でも迷いにくい設計がされています。UI の微調整はリブレオフィス側がより現代的なデザインを採用することが多く、アイコンセットや配置の変更が頻繁に行われることもあります。自分の作業スタイルに合わせてツールバーの配置をカスタマイズできる点は両方とも共通しますが、細部の動作速度や描画の滑らかさには端末性能の影響も大きく、低スペックの PC では違いを感じる場面があります。
サポートとコミュニティ
サポートの受け方も選択の大きな要素です。LibreOffice は公式のサポートドキュメントの充実度が高く、フォーラムやQAサイトでの質問の回転率が高く、初心者向けのチュートリアルが豊富です。ユーザーコミュニティの活発さが更新の速さにつながることが多く、使い方のヒントやトラブル時の解決策を見つけやすい環境があります。OpenOffice は長年の実績に基づく安定運用を好む組織や教育機関に根強い支持があり、古い資料や互換性の検証結果が未だに役立つ場面が多いです。サポートを受ける場所としては公式サイトのガイド、コミュニティフォーラム、そして日本の技術者グループなどが挙げられます。どちらを選んでも、最近はオンラインのサポートが中心となりつつあり、自己解決力を高めるチャンスにもなるでしょう。
価格とライセンス
オープンソースの特性上、両方とも基本は無料で利用できます。個人利用はもちろん学校事務や中小企業の利用でも費用を抑えられるのが魅力です。LibreOffice は非営利団体の支援を得て開発が進み、最新版の機能を比較的早く取り込む傾向があります。一方 OpenOffice は Apache 財団のもとで運用されることが多く、長期的な互換性保証の観点から導入を検討する企業もいます。ライセンスはどちらもオープンソースの原則に沿い、商用利用や改変の自由度も高いです。ただし企業利用時にはサポート契約や導入サポートの有無を確認することが重要です。結局のところコストは低いものの、導入規模やサポートニーズによって最適解が変わる点は忘れてはいけません。
簡単な表による比較
ここではわかりやすく表形式で違いをまとめます。
下の表は開発主体と機能の傾向を並べたものです。
この表だけでは細かい差は伝わりませんが、どちらを選ぶにせよ自分の作業に合うかどうかを試すことが大切です。特に学校や職場での互換性テストを前提に動作を確認しておくと後で困りません。
今日は互換性というキーワードについて友達と雑談した話を少し。友達の学校の課題は古い形式の文書ファイルで渡されて、私たちは LibreOffice を使って編集している。ところが相手は OpenOffice を使っていて、同じファイルを別のソフトで開くと段組みが崩れたりフォントが変わったりすることがある。ここで大事なのは互換性を過大評価しすぎないこと。OpenDocument形式を基盤にした両方のソフトは高い互換性を持っているが、微妙な差異は残る。だからこそ実際の作業前に代表的なファイルを両方のソフトで開いて簡単な編集を試しておくと、予想外のトラブルを防げるのが実感として分かる。





















