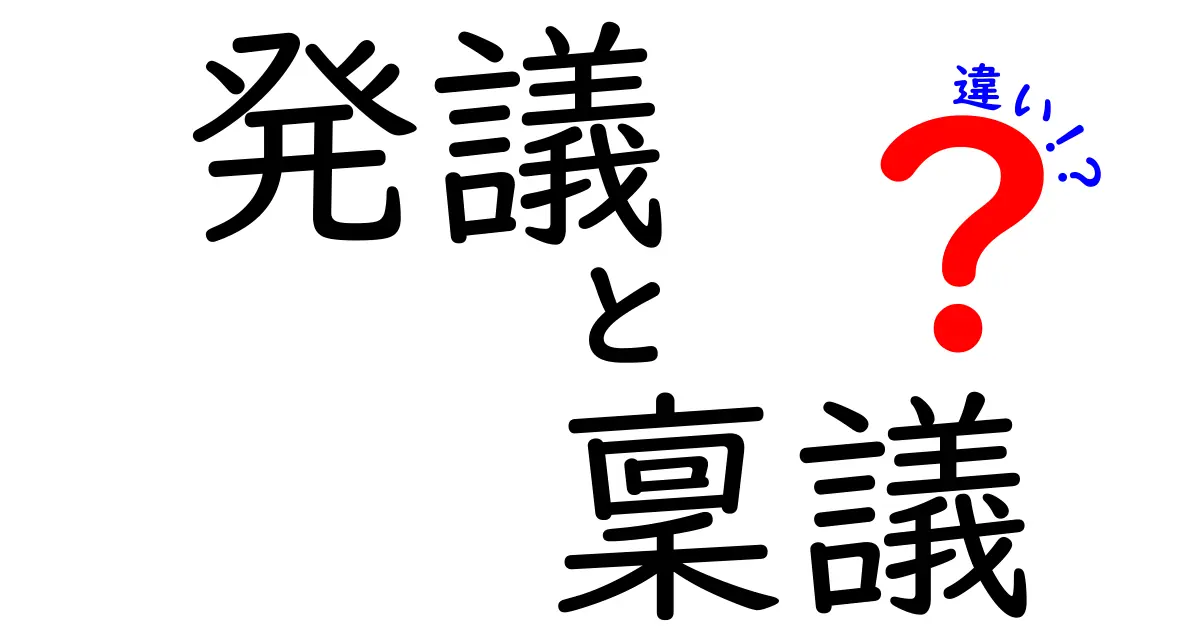

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
発議と稟議の基本の違いを最初に知ろう
発議と稟議は日本の組織でよく出てくる言葉ですが、意味は似ていても役割や流れが大きく異なります。まず大切なのは発議が「提案そのもの」を指す行為であり、発案者の意思を形にする第一歩だという点です。発議を起こすときには、どう実現したいか、何を変えたいか、どのくらいの影響があるかといった点を正確に整理します。発議は、誰かが新しい方針を示すときの最初のステップであり、承認を得る前の準備段階です。
この段階で大切なのは、案の意図と影響を正確に伝えること。齟齬があると稟議の段階で修正が多くなり、時間が伸びます。
つまり、発議は提案の形を整える作業として理解すると分かりやすいでしょう。
発議とは何か?どんな場面で使われるのか?
発議は、個人や部門が新しいアイデアや方針を「提案として公的に表明する行為」です。学校の自治会、部活、会社の部門会議など、様々な場面で使われます。発議が行われると、最初の提案者はその案の目的、背景、実現方法、費用、スケジュールなどを整理して相手に伝えます。重要なのは、発議が「決定の入り口」であり、結論を自動的に決める手段ではない点です。提案された案は、関係者の反応を受けて修正されることが普通です。発議は提案の第一歩であり、決定を左右する大切な土台です。
稟議とは何か?どんな場面で使われるのか?
稟議は、発議された案を組織の中で回覧し、承認を得るための「承認の連鎖」です。一般には複数の人が順番に承認のハンコ代わりのサインをします。稟議は特に大きな変更や高額な予算、影響範囲が広い場合に用いられ、署名者が承認を与えると案は次の段階へ進みます。日本の多くの企業では、稟議書という文書自体が公式の証跡となり、どういう根拠で、誰が、いつ承認したのかを後から追えるようにします。稟議の良さは多様な視点を集められる点ですが、時間がかかることと、形式的になりすぎるリスクもあります。
「違い」はどこに表れるのか?実務の観点
ここでの「違い」は、単に言葉の意味ではなく、実務の流れと責任の分担に現れます。発議は提案の「作成者の意図」を最初に明確化する作業であり、主にリードを取る人の判断基準が重視されます。一方の稟議は、提案を実際に動かすまでの「責任の所在を明確化する仕組み」です。高額な費用、法令や規約の遵守、影響範囲の大きさなど、実務リスクを分散させ、組織としての同意形成を促します。違いを混同すると、発議だけが終わってしまい、実際には承認を得るのに時間がかかってしまう、あるいは逆に稟議が形式だけの作業になってしまう、という状態を招くことがあります。
実務での流れを例で見てみよう
具体的な例として、学校の部活動で新しい道具を導入するとします。部長が「この道具を使えば練習の効率が上がる」と感じ、発議として提案します。発議では、どんな道具か、費用はいくらか、導入の目的と期待効果、導入時期、使い方の基本案を整理します。その後、部員の同意を得るための説明をし、次に稟議へ進みます。稟議では、部費の予算承認、顧問の同意、学校の購買手続き、保護者への周知と安全対策など、複数の承認が必要な項目を順番にクリアしていきます。最終的に全員の合意が得られれば、正式な導入が決定します。
この流れは会社でも似ており、部門長、総務、財務、法務などの関係者が段階的に確認を行います。
ここで覚えておきたいのは、発議と稟議の両方をうまく使うと、提案の実行までの時間を短縮できるという点です。
発議で案を明確に伝え、稟議で責任と根拠を固めることで、組織全体の理解と協力を得やすくなります。
表で見る発議・稟議の特徴
今日は稟議という言葉を部活の部長と顧問の関係に置き換えて、雑談風に深掘りします。発議が“この案、いいと思う”と声にする瞬間なら、稟議は“この案を実際に動かすための承認の連鎖”です。私の経験では、承認が遅くなると練習時間が削られ、道具の納期が間に合わないこともあります。だから発議の段階で情報をきちんと共有し、稟議の段階でリスクを洗い出すことが大切です。結局、二つの作業は対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。





















