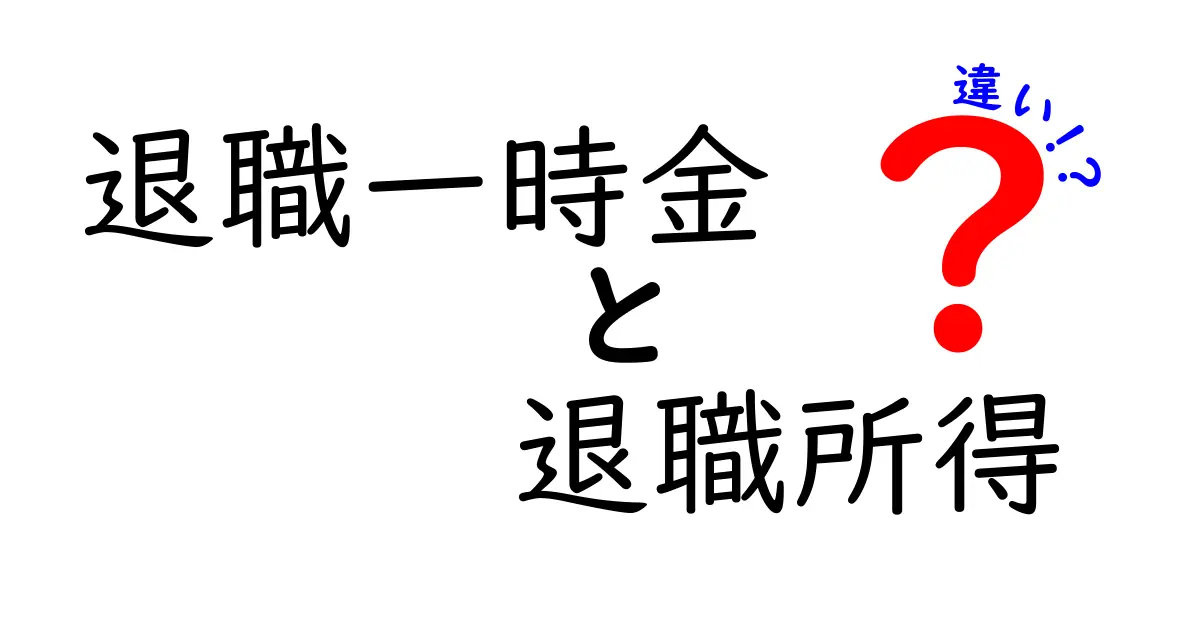

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
退職一時金と退職所得の違いとは?基本をしっかり理解しよう
退職一時金と退職所得、この2つの言葉はよく似ていますが、実は意味や税金の扱いが異なります。
退職一時金とは、会社を辞めるときに一度だけもらえる特別なお金のことです。会社からの感謝の気持ちとして支払われるため、毎月の給料とは別で支給されます。
一方、退職所得は退職一時金が税金の計算上どのように扱われるかを示す言葉です。つまり、退職一時金はもらうお金の名前で、退職所得は税金の計算に使う所得の種類の名前なのです。
この違いを理解すると、退職金がどのように課税され、手取りがどれくらいになるかがわかりやすくなります。
では、次の章で詳しい税金の仕組みについて見ていきましょう。
退職一時金の税金「退職所得」の計算方法とは?分かりやすく解説
退職一時金をもらうと、そのお金は一度税金の対象になります。
この時の所得の種類が「退職所得」です。退職所得の計算は他の所得と少し違っていて、
退職所得の計算式は次の通りです。
退職所得=(退職一時金-退職所得控除額)÷2
ポイントは「退職所得控除額」という特別な控除があり、基本的にはかなり大きな控除が適用されるため、課税対象になる金額が少なくなることです。
控除額は勤務年数によって変わり、たとえば勤続20年なら800万円の控除が適用されます。
これにより、実際に課税される額が大幅に減るため、退職金を受け取ったときの税負担が軽くなる仕組みになっています。
以下の表は控除額の例です。勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
このように、退職所得の計算は退職金をもらう際の大きなメリットになるためしっかり覚えておきましょう。
退職一時金と退職所得の違いを知ると節税や将来設計に役立つ理由
退職一時金と退職所得の違いを理解すると、いくつかの大きなメリットがあります。
まず、退職一時金はもらったそのままの金額ですが、退職所得として計算することで税金が軽くなり、手取りが増えます。
また、税金の計算方法や控除の仕組みを知ることで、退職金の受け取り方を工夫することができるようになります。
たとえば、一度に全部を受け取る方法、分割で受け取る方法など、会社と相談する際に役立ちます。
さらに、退職所得は他の所得と分けて計算されるため、退職金による税金の負担が抑えられ、老後の資金計画を立てやすくなります。
退職一時金と退職所得の違いを押さえておくことは、自分の働き方や老後の生活を豊かにする大切なポイントです。
ぜひ今日から理解を深めて、賢く将来に備えていきましょう!
退職所得控除って聞くと難しそうですが、実は意外とシンプルなんです。勤続年数に応じて一定の額を控除してくれるので、長く勤めるほど税金が安くなる仕組み。これって会社への感謝としてもらう退職金を、国も応援している証拠なんですよ。だから長く働いた人ほど得をする制度なんです!





















