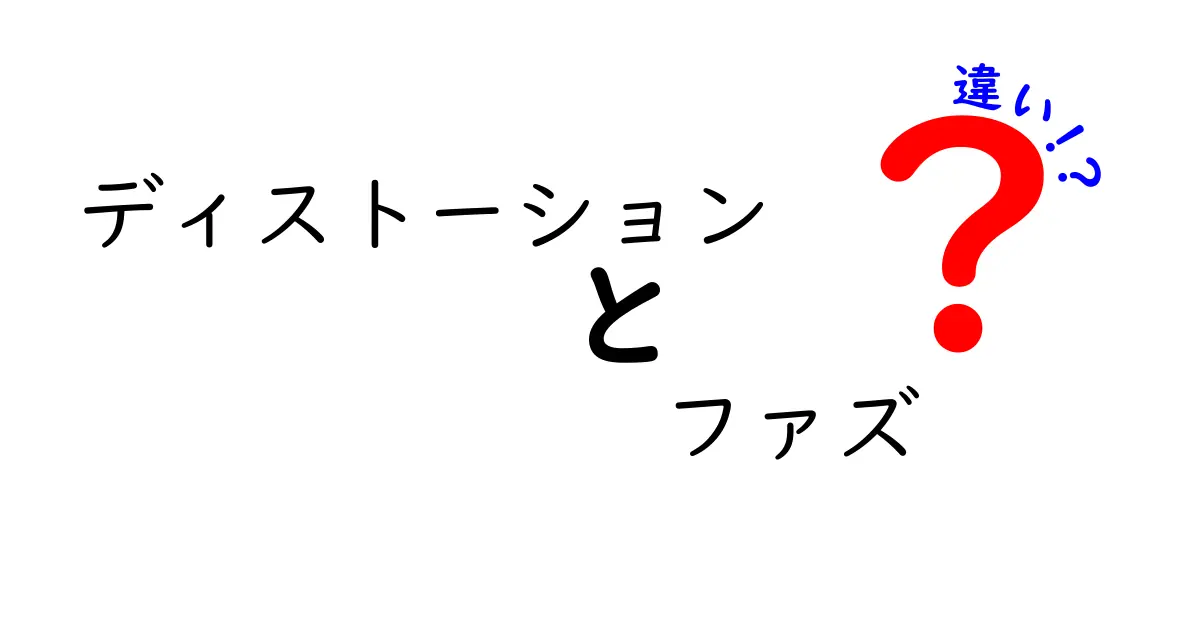

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ディストーションとファズの違いを徹底解説
ここではディストーションとファズの基本的な違いから、実際のサウンドの聴き分け、曲作りでの使い分けまでを、中学生にも伝わるように丁寧に解説します。
まずは結論を簡単に言うと、ディストーションは「パンチのある歪みを作る」タイプ、ファズは「粘度が高く、ノイズ感が強く、耳に残る尾鳴りを作る」タイプです。これだけでも雰囲気はかなり違いますが、実際には回路設計やクリッピングの仕方、ゲインのかけ方、そしてギターアンプとの関係が深く関わっています。
この記事を読めば、初心者でも何を選べばいいのか、どんな音作りができるのかが見えてきます。
まず、ディストーションとファズの音の根本を押さえることが大切です。ディストーションは主に波形を「鋭く平面的に削る」クリッピングを用いることが多く、歪みの量を増やしても音の特徴は比較的安定しています。対してファズはノイズの多い不安定なクリッピングを使い、音の立ち上がりと尾鳴りに特徴的な粘りを出すことが多いです。この違いは、演奏するジャンルや求める雰囲気を大きく左右します。
具体的には、ロックのリフを分厚く聴かせたいときにはディストーションが有効で、70年代風のファンキーなリフやサイケデリックなリフにはファズが良い場合が多いです。サウンドの厚さ、アタック感、尾鳴りの長さなど、聴こえ方の違いは実際の演奏で体感しやすく、EQの設定やアンプのボリューム、ギターのピックアップ選択とも組み合わせ次第で無限に変化します。
重要ポイントとしては、ディストーションは比較的扱いやすく、ミックスの中で存在感を出しやすいのに対し、ファズは個性が強く扱いを間違えると全体の音が埋もれてしまうことがある点です。つまり、初心者はまずディストーションから始めて、慣れてきたらファズに挑戦するのが安全な順序です。
さらに、実際の機材選びでは、ペダル本体の回路設計(オペアンプ型かトランジスタ型か、どのくらいのゲインがあるか)や、バッファの有無、ボリュームの効き方などが音の印象を大きく変えます。ここを理解すると、同じ「歪み」という言葉でも音が全く違って聴こえる理由が分かってきます。
小ネタ: ファズの深掘り conversation
友達との雑談風に深掘りしてみると、ファズって実は“音楽のコントラストを作る道具”なんだなと感じます。たとえば、ファズはノイズが混ざることで演奏のニュアンスを押し上げ、同じコード進行でも音色の個性に大きな差をつくります。ある日、教室で同級生が「ファズで遊ぶと曲全体がオールド70年代風に感じる」と話していたのを思い出します。その時私たちは、ファズは時代性を呼び起こす魔法のスパイスだと実感しました。
とはいえ、家で練習するときには音量を下げつつ試すのがコツです。音がうるさくなると隣の人に迷惑が掛かるので、ヘッドホンやイヤホンで聴くのが安全です。ファズの魅力は、ピンポイントで強い「尾鳴り」の粘度と、瞬間的な音の崩し方にあります。鳴らし方を変えるだけで、同じギターでも全く違う表情を得られるのがファズの面白いところ。
だからこそ、友だちとセッションするときは「どの音が主役になるか」をみんなで共有しておくと、雑談の中で音作りがスムーズに進みます。ファズを使いこなすには、音の輪郭を意識して、ゲインとトーンのバランスを少しずつ変えながら聴き分ける練習が最短の道です。これを繰り返すと、耳がファズの微妙なニュアンスにも敏感になり、曲作りの幅がぐんと広がります。





















