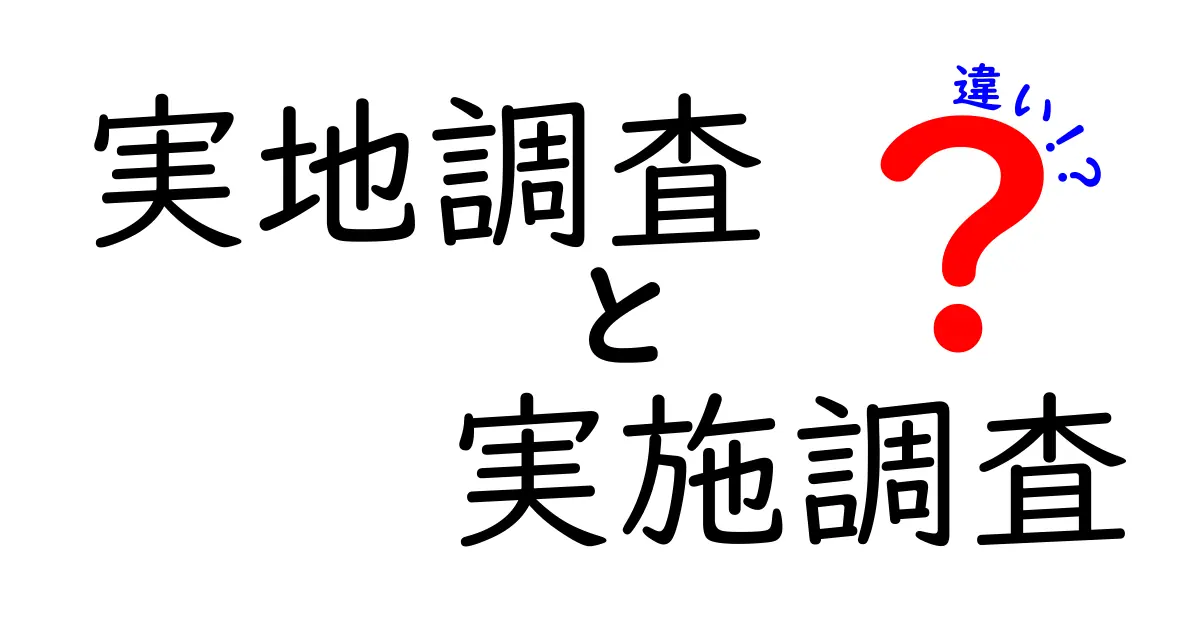

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
この「実地調査」と「実施調査」は、学校の課題や企業の仕事、研究の現場などでよく耳にする言葉です。実地調査は現場に出て、直接見て、測って、証拠を集める作業を指します。現場の空気を感じながら、事実を確かめることが中心です。実施調査は、その集めた情報を使って、計画を立て、データを整理し、結論を出すまでの全体的な流れを指すことが多いです。つまり、実地調査は「現場で何をどう見るか」という観察の部分、実施調査は「観察した結果をどう活用して結論へつなぐか」という過程の部分と考えると分かりやすいです。
この二つの違いをしっかり押さえておくと、現場の仕事だけでなく、学校の研究プロジェクトや地域の調査活動でも役に立ちます。用語の意味は分野や組織によって微妙に異なることがあるので、最初は定義を確認する癖をつけましょう。
例えば、品質管理の現場では「実地調査を実施してデータを取る」というように、順番を強調する言い方をします。研究の分野では「実施調査を設計・実行して結果を分析する」という使い方も多いです。言葉のニュアンスを理解することが、後で誤解を防ぐコツになります。
実地調査と実施調査の違いを詳しく解説
まず大切なのは、境界線をきちんと引くことです。実地調査は現場に足を運び、観察・測定・証拠の収集を最初の段階で行うことを意味します。たとえば学校の社会科の課題で、町の人にインタビューする前に現場を歩いて街の様子を観察するのは、実地調査の準備の一部になります。倉庫で商品の状態を見る、工場のラインを実際に動かして品質を確かめる、野外の植物の成長を直接測る、そうした作業が典型的な実地調査です。これらはデータの質を高めるための重要な第一歩であり、現場のリアルな情報を手に入れることが目的です。一方で実施調査は、その現場で集めたデータをもとに、どのように調査を進めるかを設計し、実行し、分析して報告へとつなぐ過程を指します。計画の立案、調査の手順、データの整理、結果の解釈、課題の抽出、そして最後の報告書作成までを含むため、全体の“流れ”をつくる作業が中心になります。つまり、実地調査が現場という土台を作る作業だとすれば、実施調査はその土台の上に建物を組み立て、住む人にとって意味のある形に仕上げる作業と言えるのです。
これらを混同しないようにするコツは、誰が・いつ・何を・どの段階でやるのかを意識することです。現場での観察が必要かどうか、データの扱いはどうするのか、分析の方法は何を使うべきか、報告書の形式はどんなものか。これらの問いを自分なりに整理していくと、言葉の使い分けが自然と身についてきます。実務の場面では、指示を受けるときにも、まず「これは現場の作業(実地調査)なのか、それとも全体の計画と分析を含む作業(実施調査)なのか」を確認する習慣が役立ちます。
この表は、実地調査と実施調査の基本的な違いを一目で確認できるように作っています。現場の観察をベースにして、データをどう扱い、どう活かすかが実施調査の肝になります。さらに、用語の使い分けが混同されやすい点を覚えておくと良いです。規定された定義がある場合は、それに従うことが大切です。初めは混乱して当然ですが、実例を見て意味を思い出す練習をすると、日常の課題解決にも役立ちます。口頭で説明するときには、現場の話と計画の話を切り替える練習をすると、伝わり方が格段に良くなります。
実地調査を深掘りする小ネタとして、私が現場で気づいたことを話します。現場に出るときは、メモ帳とペンだけでなく、直感も大事です。例えば、床の色や照明の明るさ、周りの人の動き方など、データとしては現れにくい要素も、後の分析で重要なヒントになります。実地調査は“見るだけ”ではなく、“感じる力”が役立つ場面が多いです。実施調査の段取りを考えるとき、現場での直感を参考にしつつ、客観的データとどう組み合わせるかを考えると、説得力のある結論につながります。最初は戸惑うかもしれませんが、現場に慣れてくると、気づきの連続で調査が楽しくなります。





















