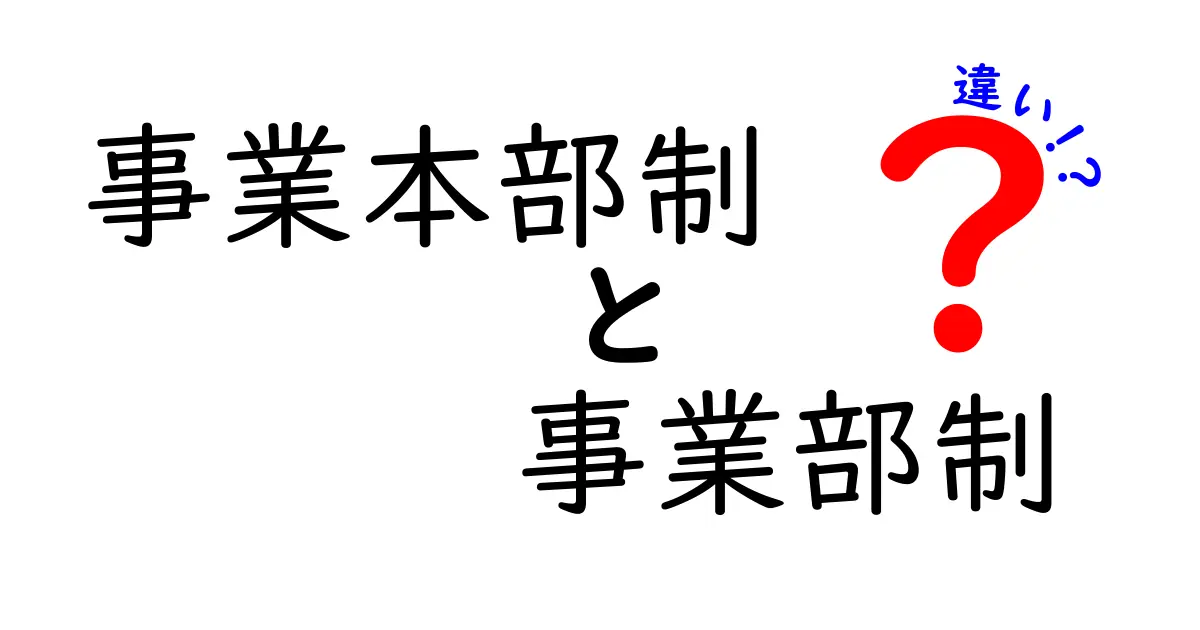

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
事業本部制と事業部制の基本を理解する
事業本部制と事業部制は企業組織の土台となる設計図です。いずれも複数の事業を持つ会社で使われることが多いですが、決定権の置き場所や責任の範囲が異なるため現場の動き方にも大きく影響します。まず事業本部制は企業をいくつかの事業本部に分け、それぞれが戦略と予算のある程度の裁量を持って運営される体制です。全社横断の機能は存在しますが、資源配分や意思決定の中心は本部長を中心とした本部が担います。市場の変化に対して資源を迅速に振り分けられる強さがありますが、全社戦略との整合性を保つための調整が長くなる傾向がある点が留意点です。
一方で事業部制は製品や市場を軸に事業部を独立させる構造です。各事業部は売上と利益の責任を自ら抱え、戦略の立案と実行の多くを自部門で完結させます。機能部門は全社横断のサポートを提供しますが、意思決定の権限は事業部に集中します。市場の変化には迅速に対応できる反面、部門間の連携を保つ仕組みや共通基盤の整備が課題になることがあります。こうした違いを理解しておくと自社の成長ステージに合った組織設計を選びやすくなります。
以下の表は両制度の要点を見比べるのに役立ちます。
総じて言えるのは自社の成長段階と市場環境に応じて最適な設計を選ぶことです。成長が早い場合は統制と資源配分の効率を優先しやすく、競争が激しく新規事業の創出が多い場合は独立性を高める方が機動性を保てます。組織設計は一度決めたら終わりではなく、定期的な見直しと評価が重要です。
友達とカフェで事業本部制の話をしていたときのことです。友人はこう言いました。『事業本部制って、各本部が勝手にやっていいわけ?』私は笑いながら答えました。『そんなことはない。共通の目的と評価指標、資源配分のルールを事前に決めることが大事だよ。そうすれば独立性を保ちながら全社の戦略と整合を取れるんだ。最新の事例では、市場が厳しい分野で本部間の協調を強化するためのデータ共有基盤を整備するケースが増えている。結局は人とプロセスの設計が鍵なんだ。』
話はさらに続く。もし事業本部制がうまく機能していないと感じたら、誰が決定するのかを再確認し、根拠となるデータと指標を整えることから始めよう。共通の評価軸があれば、各本部の裁量と全社の方針の両立がしやすくなる。現場の声を聞きつつ、トップが示す方向性を端末で共有する仕組みを作るだけで、組織の動きはぐんと滑らかになる。これは単なる理論ではなく、日々の業務改善にも直結する実務的なポイントだ。





















