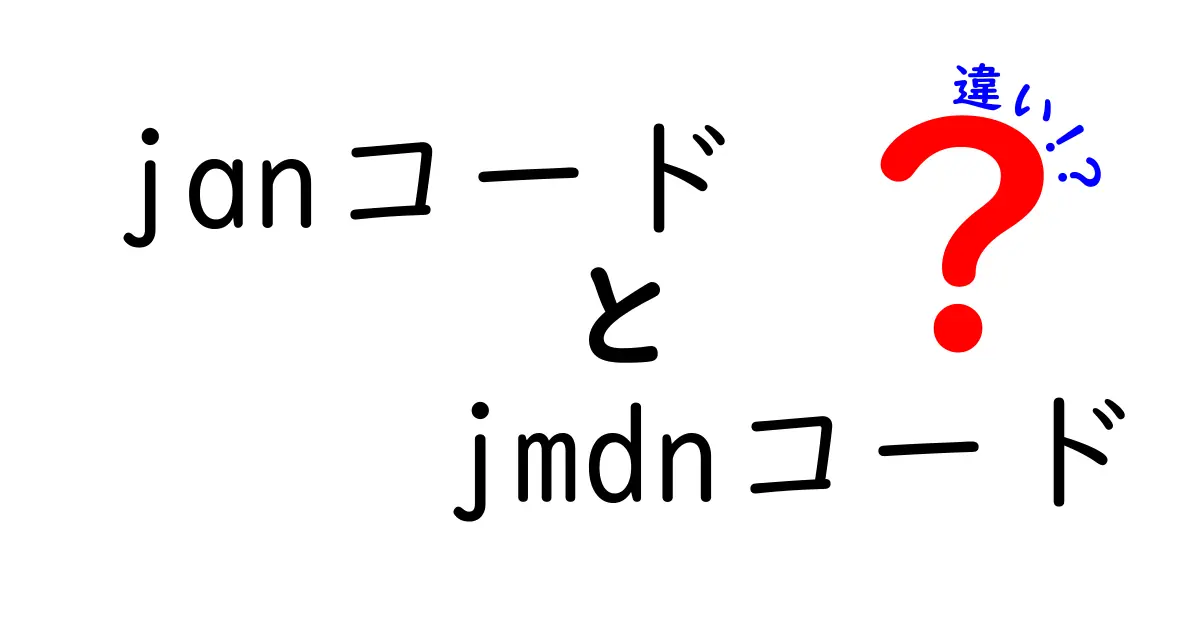

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
JANコードとJMDNコードの違いをわかりやすく解説する
現代の流通や在庫管理では商品を正確に識別することがとても大切です。バーコードやコード体系は商品を追跡し、物流の効率化や消費者サービスの品質向上に直結します。今回のテーマである JANコードと JMDNコードは、どちらも商品を識別するためのコード体系ですが、使われる場面や目的が異なります。 JANコードは日常の小売りや物流で広く使われるグローバル標準のコードで、店舗のレジや倉庫の棚札で読み取られます。一方 JMDNコードは日本の医療機器や関連品目の分類に使われるコード体系で、医療機関の在庫管理やデータベース管理に重要な役割を果たします。これらの違いを知ると、ただ単にどちらが優れているかを争うよりも、用途に応じて適切な体系を用いることが大切だと分かります。本記事では基本的な定義、構造、実務での使い分け、注意点を順序立てて解説します。中学生にもわかりやすいよう、専門用語の説明を丁寧に行い、例を用いながら噛み砕いて説明します。最後には表での比較も添え、視覚的にも違いを確認できるようにします。なおこの知識は商品開発者や倉庫作業員、販売スタッフ、さらには消費者の手元に届く情報の正確さを支える基礎となります。
JANコードとは何か
JANコードは日本の商業流通で広く使われる商品識別コードであり、主な目的は商品の識別と取引の正確性を高めることです。正式名称は Japanese Article Number であり、現在は GS1 によって管理されています。国際的には EAN-13 形式とほぼ同じ要素を持ち、13桁の数字で表現されます。先頭の数値は地域や分類を示すことがあり、中間の部分はメーカーコードと商品コード、最終桁はチェックディジットと呼ばれる検算用の数字です。バーコードとして印刷され、実店舗のレジ端末や物流の追跡システム、倉庫内の棚札などで読み取られます。JANコードを正しく読むことで、在庫の過不足を減らし、価格設定の透明性を保つことができます。実務上は国際貿易や輸入管理にも欠かせず、オンラインショップの出荷情報とも強く結びついています。
なお JANコードは「日本で使われる識別コード」であり、同じ仕組みを持つが別名のコード体系は世界中に存在します。例えば欧州の国コードや北米のコード体系と組み合わせて流通を管理するケースもあり、グローバルなサプライチェーンではこの共通性が大きな利点となります。まとめると JANコードは小売・流通・国際取引の基本となる識別子であり、商品の正確な区分と追跡を可能にする核となる仕組みです。
JMDNコードとは何か
JMDNコードは日本の医療機器分類のコード体系として使われるもので、医療現場の在庫管理や医療情報システムで重要な役割を果たします。正式には日本医療機器分類(JMDN)と呼ばれ、日本国内の医療機器や関連品目の標準化された nomenclature を提供します。JMDNコードは医療機器の名称や機能を統一的に表現するためのデータ要素であり、病院の購買システム、在庫管理、品質監視、医療情報データベースなどに活用されます。
JANコードのようなバーコード識別とは異なり、JMDNコードは主にデータベース内の分類や検索のためのコード体系です。つまり現場の棚で読み取るためのものではなく、医療機器の種類を一貫して記述・検索するための「分類の言語」に近い性格を持ちます。医療現場では JMDNコードと関連するデータが紐づけられ、薬剤情報、機器の保守計画、購買履歴、貸出管理など多様な業務が効率化されます。病院や医療機関だけでなく、医療機器メーカーや流通業者にとっても共通のコード体系を用いることは情報共有の正確さと迅速性を高める要因です。
違いのポイント
JANコードとJMDNコードは似ているようで目的と使われ方が大きく異なります。以下のポイントが大きな違いの核です。
・目的の違い
JANコードは商品を識別して流通を円滑化するための「識別子」です。倉庫での在庫管理やレジでの価格決定、輸出入の表示など、商取引の現場で直接使われます。
JMDNコードは医療機器の分類・名称表現の標準化のための「分類コード」です。医療情報システムや病院の購買データベースでの検索・集計が主な用途です。
・適用範囲の違い
JANコードは食品・日用品・家電などあらゆる商品の識別に使われます。医療以外の分野での普遍的な識別子として機能します。
JMDNコードは医療機器に特化しており医療機関内のデータ運用で中心的役割を果たします。
・読み取りと利用の違い
JANコードはバーコードとして現場でスキャンされ、数量・価格・出荷情報と結びつきます。現場の作業効率を直接高めます。
JMDNコードは主にデータベース検索・統計・在庫管理・保守計画のために用いられ、実際の現場での「読み取り」というよりは情報整理のツールです。
実務での使い分け
実務では用途ごとに適切なコードを使い分けることが重要です。まず小売・流通の現場では JANコードが中心となります。店舗のPOSシステムや倉庫の入出庫、物流の追跡、オンライン販売の出荷管理など、商品を正確に特定し瞬時に処理するためには JANコードが欠かせません。食品や日用品を取り扱う企業は特にこのコードを日常業務の中で活用します。次に医療機関や医療機器メーカーの現場では JMDNコードが中心です。病院の購買部門は医療機器の分類と名称の統一を通じて在庫状況を正確に把握し、保守・点検のスケジュール管理や法規制対応を円滑にします。なお両者は同じ企業が両方の場面を扱う場合もあり、互換性の高いデータベース設計が求められます。具体的には商品情報データベースと医療機器データベースを適切に連携させ、一方で現場のスキャナーやPOS端末の読み取りデバイスは JANコードを優先的に活用し、医療現場の検索は JMDNコードを核に行う、という形が現実的です。これにより、効率的な在庫管理と正確な医療機器のトレーサビリティを両立させることが可能になります。
また新規商品の登録時には両方のコードを体系的に整備します。JANコードは市場での販売・流通の識別を担い、JMDNコードは医療機器の分類と名前の統一を担います。組織内のルールとして、どのデータベースにどのコードを登録するか、どの担当部署がどのコードの更新を行うかを明確にしておくと混乱を避けられます。
よくある誤解と注意点
よくある誤解として「JANコードと JMDNコードは同じものだ」という考え方があります。両者は目的・対象が異なる別のコード体系です。もう一つの誤解は「1つのコードで全てが決まる」というものです。実務ではJANコードは商品単位の識別に、JMDNコードは医療機器の分類・表現・検索のための分類コードとして併用されるのが一般的です。互換性を理解せずに混同すると、在庫データの不整合や検索の困難が生じるおそれがあります。
注意点としてはコードの管理責任者の明確化と更新手順の統一、データベース間のリンク設計です。特に医療機器は法規制や追跡義務が厳しくなる場合があるため JMDNコードの更新が遅れると在庫情報や保守情報がずれることがあります。組織としてはコードの変更履歴を残し、関連するデータ項目を必ず同期させる運用を心がけると良いでしょう。
表で見る違い
以下の表は要点をまとめたものです。実務での判断材料として役立ててください。
koneta: 友だちと話していて janコードと jmdnコードの違いの話題が出た。 janコードは商品を識別してレジを回したり在庫を追跡したりする“実務の道具”で、スキャン一つで価格や在庫数が瞬時に分かる。対して jmdnコードは医療機器の分類を統一する“言語”の役割がある。つまり同じ商品でも医療現場では別のコードで管理されることがある。だから現場に応じて使い分けるのが大事だと感じた。もし混同すると、商品が間違って取り扱われたり在庫がずれたりする可能性がある。だからコードの役割を理解し、データベースと現場の運用がちゃんとリンクしているかを常に確認することが大切だ。





















