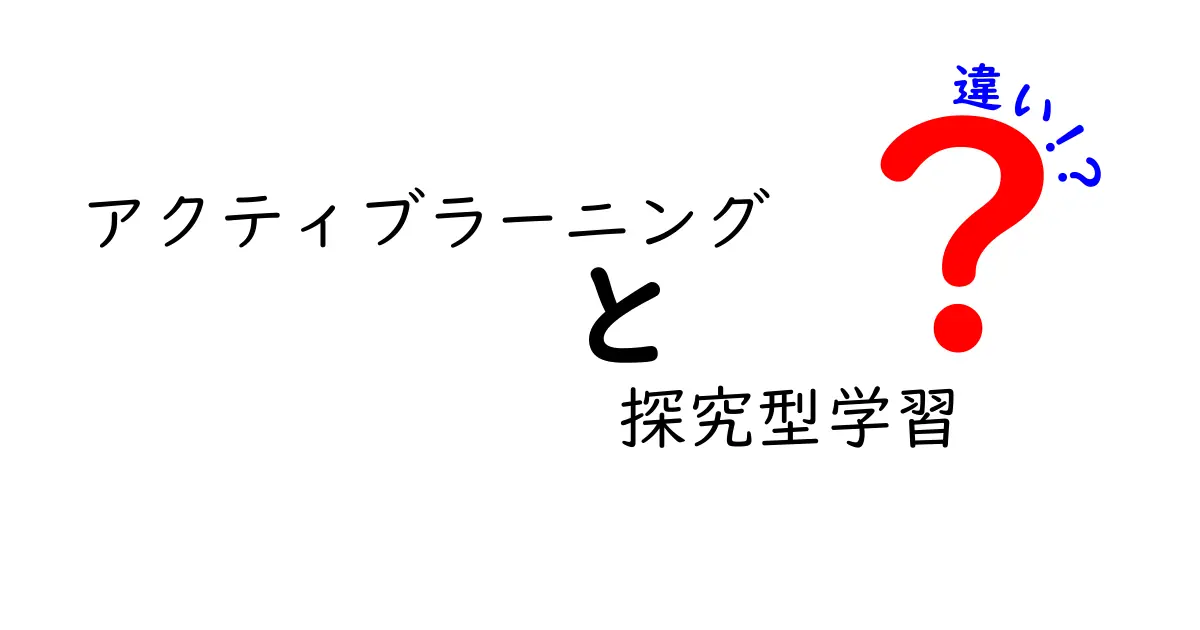

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アクティブラーニングと探究型学習の違いを徹底解説:授業設計の新しいヒント
日本の学校教育でよく耳にする「アクティブラーニング」と「探究型学習」は、似ているようで実は目的や進め方が異なる学習アプローチです。アクティブラーニングは、学習者が主体的に参加して考える機会を増やすことを指します。問いを友人と議論したり、実験を通して体感したり、課題解決の過程を共有したりすることで、知識だけでなく技能や協働力を育てます。対して探究型学習は、より長期的で自分の興味・関心に基づく問いを設定し、情報を集め、分析し、結論を導くまでの過程を重視します。学習の主役は「問いを持つ学習者」であり、教師はその問いを深掘りするための支援者です。こうした違いを理解することで、教室での設計や評価のしかたを変えることが可能になります。
違いの核心と現場での誤解を解く
まず、両者には「学びを深める」という共通の目的があります。双方とも能動的な学習を前提にしている点が大きく、受け身の授業からの脱却を目指します。しかし、目的の違いと評価の視点が異なるため、現場での誤解が生まれやすいのです。アクティブラーニングは「どう考えるか」を問う場を増やし、意思決定力や対話力の育成を狙います。探究型学習は「何を、なぜ学ぶのか」という問いの立て方・検証の方法を大切にし、長期の研究プロセスを経験させます。教師の役割は、問いを設定し、適切な支援を選ぶことにあります。
実践のポイントと設計のヒント
実践の基本は「目的と学習者の現状を正しく結ぶこと」です。まず授業の目標を明確にし、学習者が自分の興味を見つけられる問いを用意します。問いの設計は短期・中期・長期の三段階を使い分けるのが効果的です。短期はミニ課題で基礎を確認、中期はグループでの共同作業、長期は探究プロジェクトとして発表・検証までを行います。評価は「プロセスと成果の両方」を重視し、観察記録・自己評価・他者評価を組み合わせると良いです。教室を安全な討論の場にする工夫(ルールづくり、ファシリテーション、時間管理)も重要です。
また、以下の点を参考にすると実践がスムーズになります。
・学習者の主体性を引き出す問いかけを日常的に行う
・協働の場面で役割分担を明確にする
・失敗を成長の機会として捉える風土を作る
Aさん: ねえ、アクティブラーニングと探究型学習の違いって実際にはどんな場面で現れるの? Bさん: いい質問だね。アクティブラーニングは教室の中で“どう考えるか”をみんなで考える場を増やす方法。発表やディスカッション、グループ作業など、学習の体験そのものを活性化することが目的だよ。探究型学習はもう少し長いスパンで、問いを自分で設定して調べ、検証し、結論を導くまでのプロセスを体験する学習。観察・データ分析・根拠づけが核になる。要は、前者が「行為そのものを深める学習」、後者が「問いと検証を通じて自分の結論を作る学習」になるんだ。なお、両方とも教室の雰囲気づくりや評価の方法を変えると効果が高まるよ。





















