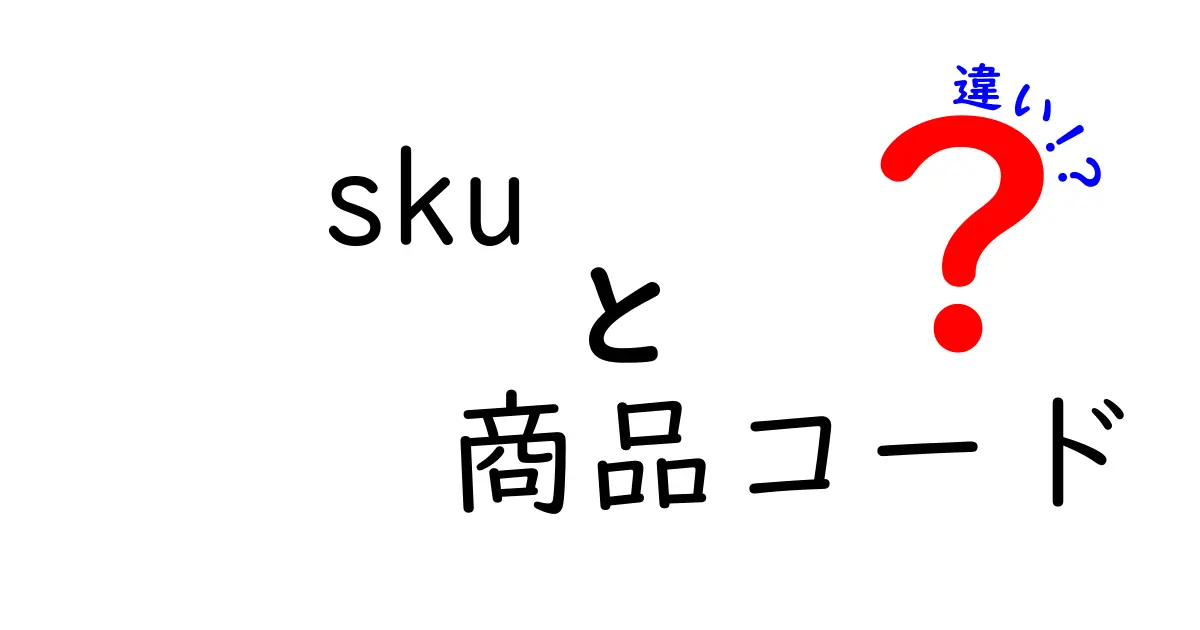

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
skuと商品コードの基本的な違い
skuとはStock Keeping Unitの略で、在庫を正確に把握するために自社で設定する識別子です。SKUは内部のオペレーション用の識別子、商品コードは外部取引の共通識別子という役割分担を持ちます。SKUは自由度が高く、同じ商品でも色・サイズ・素材・シーズンなどの属性を組み合わせて作られるのが特徴です。これにより、在庫の検索・棚割・補充の発注などの業務で迅速な判断が可能になります。一方、商品コードは取引先と共有するためのコードで、バーコードやメーカーの型番、UPCやEANなど、外部規格に沿うことが多いです。SKUは内部のオペレーション最適化、商品コードは外部との共通識別として機能します。
この違いを理解するだけで、在庫管理の基本設計が見えやすくなります。
SKUを正しく設計すると在庫の過不足を減らし、棚卸の時間を短縮できます。
ただし、過度に細分化するとデータの重複や検索性の低下を招くこともあるため、適切な粒度を決めることが重要です。
この基礎があれば、後のデータ分析や需要予測にも活かせます。
混同を避けるための実務のコツ
混同を避けるには、用途別の定義を文書化することが大事です。SKUは内部向け、商品コードは外部向けという基本方針を守り、名称だけでなく役割まで明確にします。データの取り扱いルールを統一して、SKUと商品コードを別々の列で管理します。両者を紐づける対応表を用意し、更新時には必ず両方のデータを同時に更新します。現場の例として、バーコードやメーカー型番のような外部コードと自社用に設計したSKUをリンクさせることで、棚卸・出荷・請求の場面で混乱を回避できます。実務上は、SKUを使って在庫の場所・数量・状態を素早く検索し、商品コードを顧客への請求書や納品書に反映させると、取引先とのやり取りがスムーズになります。二重管理を導入する際には、定期的なデータ整合性チェックを設定し、年度替わりや新商品投入時には一括更新を行うと安心です。こうした取り組みは、現場の人員が変わっても統一された運用を維持するのに役立ちます。最終的には教育と運用の両輪が大事です。
SKUと商品コードの使い分けの実践ポイント
実践的な取り組みとして、最初の一歩は粒度の設計です。描くべき属性の組み合わせを決め、過不足のない適切な粒度を設定します。色・サイズ・素材など、どの属性をSKUに含めるべきかを社内で合意し、検索性を保ちながら過剰な細分化を避ける方針をとります。次に対応表の運用を徹底します。SKUと商品コードを結ぶリンクを作成しておくと、棚卸や出荷時のミスを防げます。現場の運用としては、棚札にSKUを明記し、受注伝票・納品書には商品コードを併記する方法が有効です。デジタル面では、WMSやERPのダッシュボードで両方を表示・検索できる画面設計を心がけ、フィールド名を統一します。最後に教育と継続的な見直しです。新商品投入時のルール更新を怠らず、全員が同じ基準でデータを扱えるようにします。これらの実践を積み重ねると、在庫の正確性が高まり、経営判断にも役立つ信頼できるデータ基盤が築かれます。
今日はSKUの小ネタ話をひとつ。友達とカフェで『SKUって何?』と聞かれて、私はこう答えました。SKUは在庫を管理するための“社内用の地図番号”みたいなものだと。色やサイズが違えば別のSKUになり、同じ商品でも取り扱い方の違いで新しい番号が生まれます。反対に商品コードは外部と共有する識別子で、取引先がそのコードを見て商品を特定します。つまり内部と外部の両方を結ぶ橋渡しのような役割です。実務での活用は、データの紐づけを徹底すること。SKUと商品コードを対応表で結び、棚卸と出荷のタイミングで両方を確認する癖をつけると、ミスが格段に減ります。こうしたちょっとした心がけが、日々の業務をスムーズにしてくれます。





















