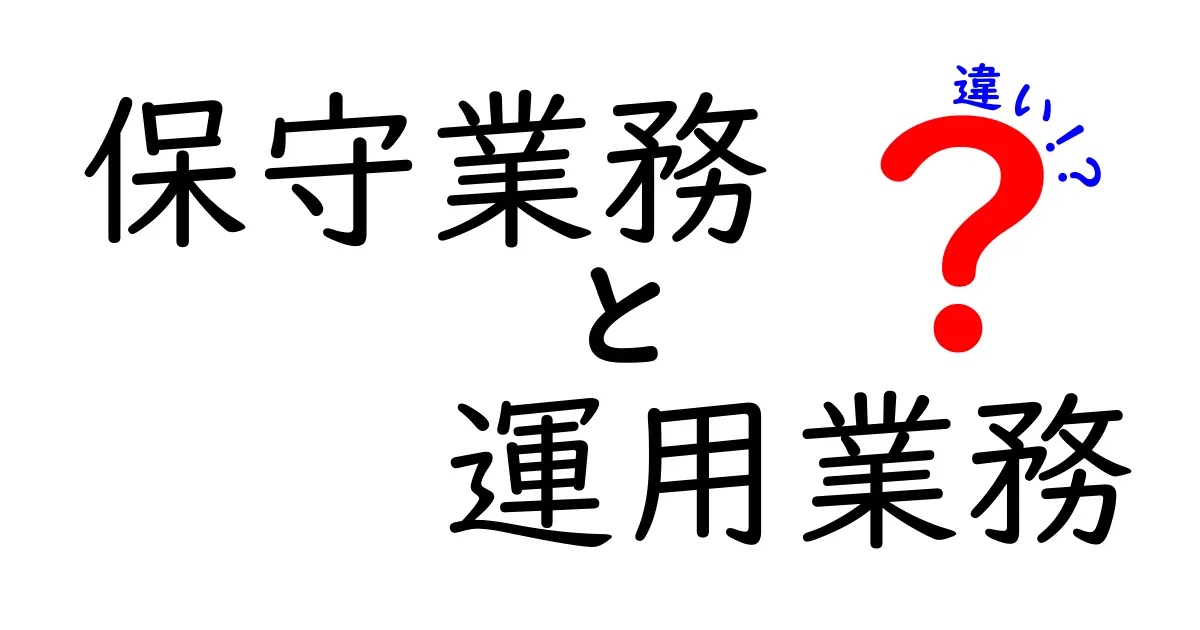

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:保守業務と運用業務の基本を押さえる
はじめに、保守業務と運用業務という言葉はITや製造の現場でよく使われますが、実際には役割が異なります。保守業務は、すでに動いている仕組みを長く安定して動かすために行う作業のことを指します。具体的には、障害が起きたときの復旧対応、セキュリティパッチの適用、ソフトウェアの更新、監視の設計と見直し、定期的な点検、故障の原因を分析して再発を防ぐ仕組みの強化などが含まれます。これらは「問題が起きずに動き続ける」という品質を高めるための地道な作業です。これに対して、運用業務はサービスを外部の利用者や内部の利用者に安定して届けることを目的とした日常の業務です。人員の割り当て、バックアップの実行、データの整理・保全、容量計画、業務プロセスの標準化、レポート作成、手順書の更新、SLAの遵守といった仕事が中心になります。これらは「作業の流れを止めず、適切なタイミングで物事を回す」ための活動で、短期的な対応だけでなく長期的な運用の設計にもかかわります。
ここで重要なのは、保守業務と運用業務は切り離せないが別の視点で動く活動であり、片方だけが過剰だともう片方が機能しなくなることです。保守が十分でなければ安定した運用は難しく、運用が整っていなければ保守も適切に行われず対応が遅れてしまいます。実務では、まず現状の業務を分解して、どのタスクが保守寄りか、どのタスクが運用寄りかを見極め、組織の目標やサービスレベルに合わせて役割分担を作ることが大切です。
違いを生む視点:目的・範囲・日常業務
保守業務の基本的な目的は、信頼性を維持し、可能な限り障害を未然に減らすことです。故障が起きても迅速に復旧できる体制を整えること、セキュリティを強化すること、更新やパッチを適切に適用して脆弱性を減らすこと、監視の設定を最適化して問題を早く検知すること、過去の障害データから再発防止策を作ることが重要です。これに対して運用業務の目的は、サービスを利用者に対して安定的かつ効率的に提供することです。日々の業務は「手順に沿って正確に回す」ことが基本で、バックアップの実行、データのバックアップの検証、容量の監視、リソースの割り当て、業務プロセスの改善提案、運用に関する日報やKPIの集計などが含まれます。ここでのポイントは、運用は“現在のサービスを持続させること”を最優先することであり、保守は“過去の問題を再発させないようにする”ことが軸になるという点です。長期的には、両方の情報を組み合わせてサービス全体の品質を高めるPDCAサイクルを回していくことが求められます。
実務での使い分けと注意点
実務では、日常のタスクを保守寄りと運用寄りに分け、誰が何を担当するかを明確にすることが大切です。朝の監視とアラート対応は保守よりですが、日次レポートの作成は運用寄りです。新しい機能を導入する前には、運用の手順書を更新し、テスト環境での影響を評価してから本番へ適用します。変更管理のプロセスを整えると、障害が起きても迅速な切り分けと再現性の高い対応が可能になります。バックアップの計画と検証を定期的に行い、データの復旧手順を現場の作業者が理解できるようにします。最後に、 チーム間のコミュニケーションが最も重要です。誰が何をしているのか、どのタスクが遅れているのかを透明に共有することで、予期せぬトラブルを減らし、改善提案を現実的なものにできます。
保守業務について友達と話していたら、彼は『保守っていわば車を長く走らせるための点検みたいなものだよね』と言いました。そう、定期的な点検、パーツの交換、壊れそうな箇所の前もって対処することが保守の核心です。彼と私は、パッチ適用を“薬を飲むこと”に例え、更新を怠ると脆弱性が積み重なり危険が増える、と語り合いました。私にとって保守は「いつも動くための裏方作業」で、目に見えなくてもサービスの信頼性を守ってくれる支えだと感じます。自分の学校の文化祭の準備にも、細かな作業が連携する大切さを思い出させてくれ、保守と運用の両輪で未来を作るイメージが広がります。





















