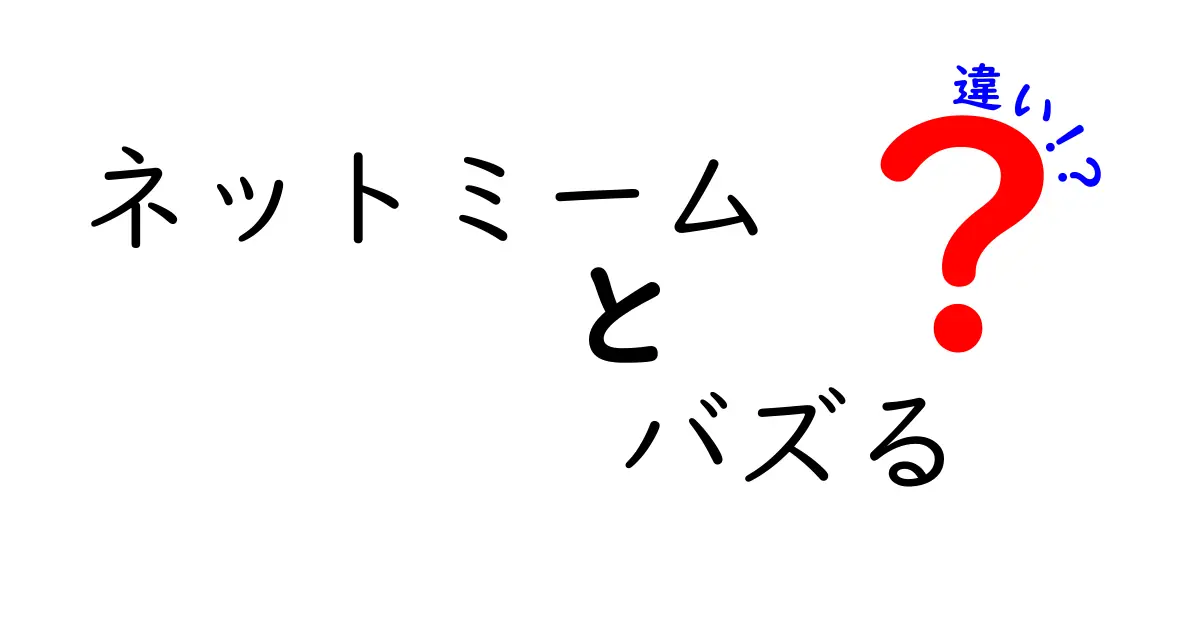

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:ネットミームとバズる仕組み
ネットミームとは人々の間で共有され、場や時代に合わせて形を変えながら拡散していく現象です。
バズるとはその拡散が急増し、多くの人の目に止まり、短時間で連鎖的に広がっていく状態を指します。
なぜ同じネタなのにあるものは急速に広がり、別のものはほとんど広がらないのか。その答えは決して一つではなく、作り手の意図や視聴者の反応、プラットフォームの仕組み、さらには社会の空気感などが複雑に絡み合っています。
このセクションではまず基本を押さえ、続く部分で違いを生む要因を詳しく見ていきます。
ポイントは分かりやすさと再現性、そしてタイミングの三つです。
未来のバズを狙うなら、これらを組み合わせて考えることが大事になります。
違いを生む3つの要因
ここではバズる差を生む要因を三つに分けて解説します。
1つ目は再現性と認識のしやすさです。見る人が「これなら自分も発信できる」と感じると、友だちにコピーされやすくなります。難解な設定や専門用語を連発すると、理解に時間がかかって敬遠されがちです。
2つ目はタイミングと話題性です。流行のらせんを読み、今の出来事と重ねることで共感が生まれ、拡散の核が回り始めます。季節、ニュース、イベント、お馴染みのキャラクターの動きなど、周囲の状況が大きな影響を与えます。
3つ目はプラットフォームのアルゴリズムとコミュニティです。同じ投稿でも、TikTokやTwitter、Instagramなどの仕組みが違えば見られ方が変わります。フォローしている層の好み、コメントの雰囲気、いいねの仕方などが、どの程度広がるかを決めます。
この三つの要因が絡み合って、同じネタでもバズるかどうかが決まります。さらに、繰り返しが生む「テンプレート化」や「フォーマット化」も重要です。
次の章では、実際の例を挙げて、どういう点が成功につながるのかを具体的に見ていきます。
実例を通じて学ぶことが、今後の投稿作りのヒントになります。
koneta: 友達とグループチャットで流れてきたネタがきっかけで、実験してみた話です。まず共通点として、短く覚えやすいフレーズ、すぐに模倣したくなるビジュアル、そしてタイムリーな話題性がありました。私は同じネタを10人に見せて反応を比べました。10人中6人はすぐにいいねを押し、4人はスルー。次に、年齢層や趣味が違うグループで再現性を試すと、成功した人のほうが手軽に自分の言葉で言い換えられる傾向がありました。そこで私は、誰でも作れるテンプレを考え、短い文とアイコンを組み合わせる手法を提案しました。結果、模倣の数が増え、元ネタを知らなくても意味が伝わる形へと進化しました。結局、バズは“再現性”と“受け手の共感”のバランスで決まるのだと実感しました。





















