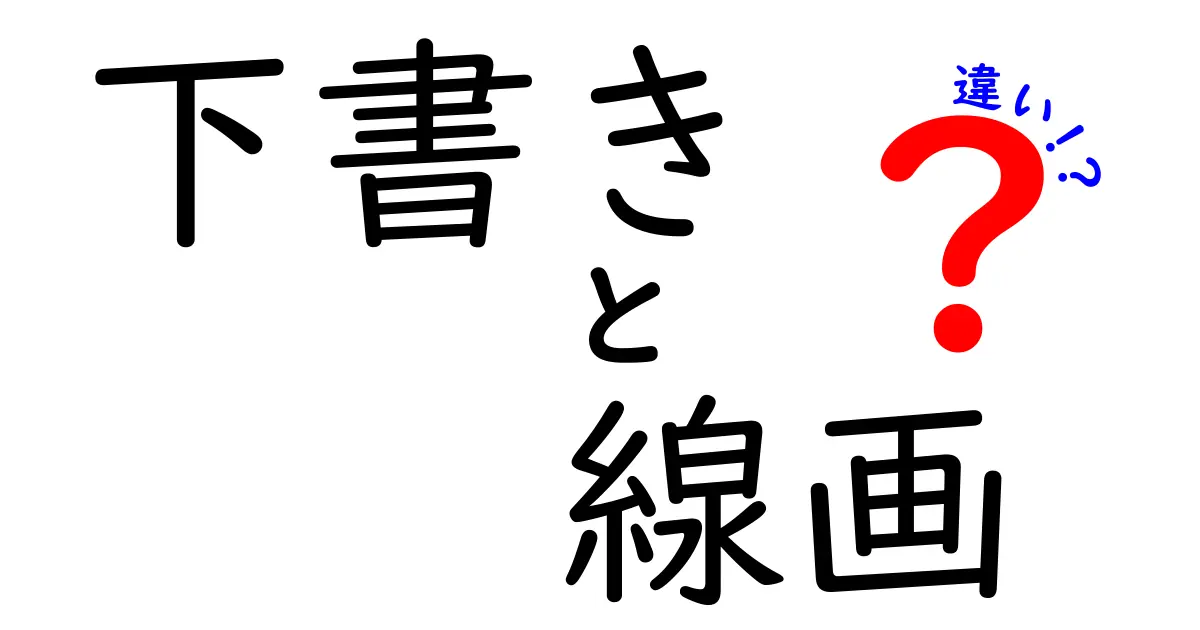

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
下書きと線画の違いを理解する
下書きは作品づくりの最初の段階で、形の仮置きと構図の検討を行います。鉛筆で薄く線を引き、消しゴムで修正しながら大体のバランスを決める作業です。ここで重要なのは「完成形をそのまま描くのではなく、まだ確定していない案を色々試すこと」です。下書きを丁寧に作れば、線画以降の修正が楽になります。なお、線の強さはまだ強く出さず、薄い線で全体の雰囲気を掴むのがコツです。
中学生にも分かりやすく例えると、家の設計図の最初の線を引くときの感覚です。形や比率をまず見て、細かい部分は後回しにします。
線画は下書きの上に描く「最終形の土台」になります。ここではペンやデジタルの線で、形をはっきりと決め、清書に近い状態を作ります。線画は「誰が見ても読める輪郭と情報の塊」を作る行為で、細部の修正は下書きの時点で済ませておくほうが失敗が少なくなります。線の種類としては、外形を太く、内側の補助線を細くするのが基本です。これにより、陰影を乗せるときの情報量が崩れず、描き手の意図も伝わりやすくなります。
また、下書きと線画は作業の順序だけでなく「目的の違い」も持ちます。下書きは構図・比率・動きの確認、線画は読みやすさ・最終的な線の美しさ・着色のベースづくりを担います。したがって、下書きを雑に済ませてしまうと、線画の段階で修正が増え、着色時にも悪影響が出ることがあります。ここでのコツは、下書きの段階で消しゴムの使い方を丁寧にすることと、線画を描く前に「どの線を残すべきか」を意識することです。
線画の完成を想像しすぎず、まずは虚心に描いて、後から修正を重ねる気持ちで作業を進めましょう。
実際の作業フローとポイント
ここでは具体的な流れと注意点を整理します。まずは軽い筆圧で下書きを作ります。重要なのは「崩れそうなバランスを早めに見つける」こと。構図の中心、人物の目線、手足の長さなどを比率の目安として、全体の安定感を優先します。次に、下書きをもとに線画を描きます。線画では無駄な補助線を消し、輪郭を整え、必要に応じてハイライトや影の位置を想像しておくと後の仕上げが楽です。下書きで決まった位置を崩さないよう、線を引く順序にもコツがあります。最後に着色へ移りますが、線画が読みやすい状態であることが大事です。
線の強弱をつけすぎると、色を塗るときに境界が目立ちすぎることがあるため、最初は均一な線から始め、必要な箇所だけ後で強調するとうまくいきます。
このような順序と考え方を守ると、作品全体のクオリティを大きく高めることができます。下書きは恥ずかしがらず大胆に、線画は冷静に整える。これが、初心者からでも美しい絵を作るコツです。
ある日、授業で線画の話をしていた。僕は友達に、線画は絵の“地図”みたいなものだと伝えた。地図がはっきりしていれば、道に迷わないように絵も迷わず進む。下書きはその地図の描き始め、線画はその地図をペンで整えて道標を立てる作業。そんな話をしていると、友達も自分なりの線の太さや強弱を意識し始めた。雑談の中で気づいたのは、技術は結局、使い方のコツと心の余裕の両方で決まるということだった。
前の記事: « 発色と蛍光の違いを徹底解説!色の正体を見抜くポイント





















