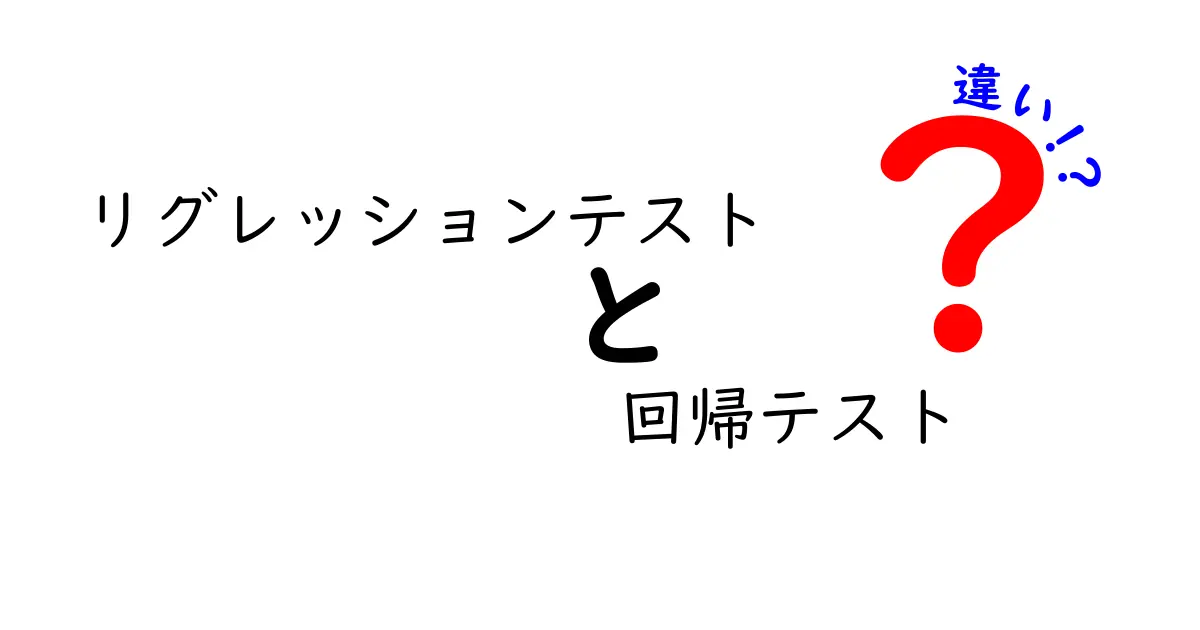

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
リグレッションテストと回帰テストの違いを正しく理解するための基本
リグレッションテストとは何かをまず押さえることが大切です。英語の regression testing を日本語に直した用語で、日々のソフトウェア開発で重要な役割を果たします。新しい機能を追加したりバグを修正したりした後に、すでに動いていた機能が影響を受けていないかを検証する作業全体を指します。つまり修正の範囲を超えた部分にも影響が及んでいないかを確認するための「再検証」のことです。ここでポイントとなるのは、ただ新しい機能が動くかどうかを試すだけではなく、既存の振る舞いが一貫しているかを確認する点です。
この観点からみるとリグレッションテストは広義には結合テストや機能テストを含む場合もありますが、実務上は「修正後の安定性を確保するための広範囲な再検証」という理解で進めるのが一般的です。
反対に回帰テストは日本語の語感としては同義で使われる場面が多い言葉です。日本のQA現場では回帰という言葉を使って、過去に問題が発生した経緯を踏まえた再チェックというニュアンスを含めて説明するケースが多く見られます。
この二つの用語の違いを厳密に区別するよりも、組織やプロジェクトでどの範囲を対象とするのかを事前に決めておくことが現場の混乱を減らすコツです。
以下ではその違いを整理するための表と実務のヒントを紹介します。
混同を招く原因と実務上のポイント
実務では用語の違いよりも実際の検証対象や作業の流れが重視されるため、リグレッションテストと回帰テストの区別が曖昧になることがあります。あるチームではリグレッションテストを広義の再検証として、高頻度リリース時の自動化テスト全般を含めて語ることもあります。一方別のチームでは回帰テストを修正後の最終確認という意味合いで使い、リグレッションテストをその前段の広範囲検証と分ける場合も。結論としては、用語の先にある目的を共有することが大切です。目的を共有すれば言葉の壁は乗り越えられ、検証の品質は保たれます。ここでは混同を避けるためのコツをまとめます。
まずは影響範囲の定義を明確にしてください。次に検証の優先順位を決め、どのテストを自動化するかを決定します。最後に実施タイミングを一定化し、スプリントやリリース周期に合わせて繰り返す体制を作ることが重要です。これらを統一すれば、リグレッションテストと回帰テストの境界線は自然と現場の実務に沿って機能します。
実務での使い分けとチェックリスト
実務での使い分けのコツは、言葉の違いよりも検証の目的と範囲を事前に決めることです。以下のチェックリストを現場で活用しましょう。
・影響範囲を事前に定義すること
・どの機能が壊れていないかを確認する基準を明確化すること
・回帰条件のリストを作成し、過去の不具合発生パターンを参照すること
・自動化の優先度を決め、優先度の高いケースを自動化すること
・リリースサイクルに合わせて定期的な検証を組み込むこと
・手動と自動のバランスを保ち、運用コストを抑えること
・成果物としての報告書やダッシュボードを整備し、関係者が現状を把握できるようにすること
リグレッションテストと回帰テストの実務的なポイントまとめ
実務で最も大切なのは概念の理解よりも日々の運用です。リグレッションテストと回帰テストの違いを過度にこだわらず、目的と範囲を明確にして作業を進めることで、品質を安定させることができます。新機能の追加後やバグ修正後には必ず既存機能を再確認し、影響を受ける可能性のある領域をリスクとして捉える癖をつけましょう。これにより、リリース後の想定外の不具合を減らすことができ、開発とQAの協業も円滑になります。
友人のミキと私は近所のカフェでリグレッションテストと回帰テストの話をしていた。ミキは新機能の自動化を検討していて、私は過去の修正でどこが崩れやすかったかを思い出して雑談を深めた。結局のところ、用語の差よりも検証の目的と範囲を共有することが大事だと気づく。リグレッションテストも回帰テストも、さわる範囲を広くとるか狭くとるかの戦略の違いに過ぎない。現場では仕組みを整えることが先で、名前の違いは役割の一部にすぎないのだ。こうして私たちは、どのケースでも安定した品質を保つ方法を見つけていくのだと思った。





















