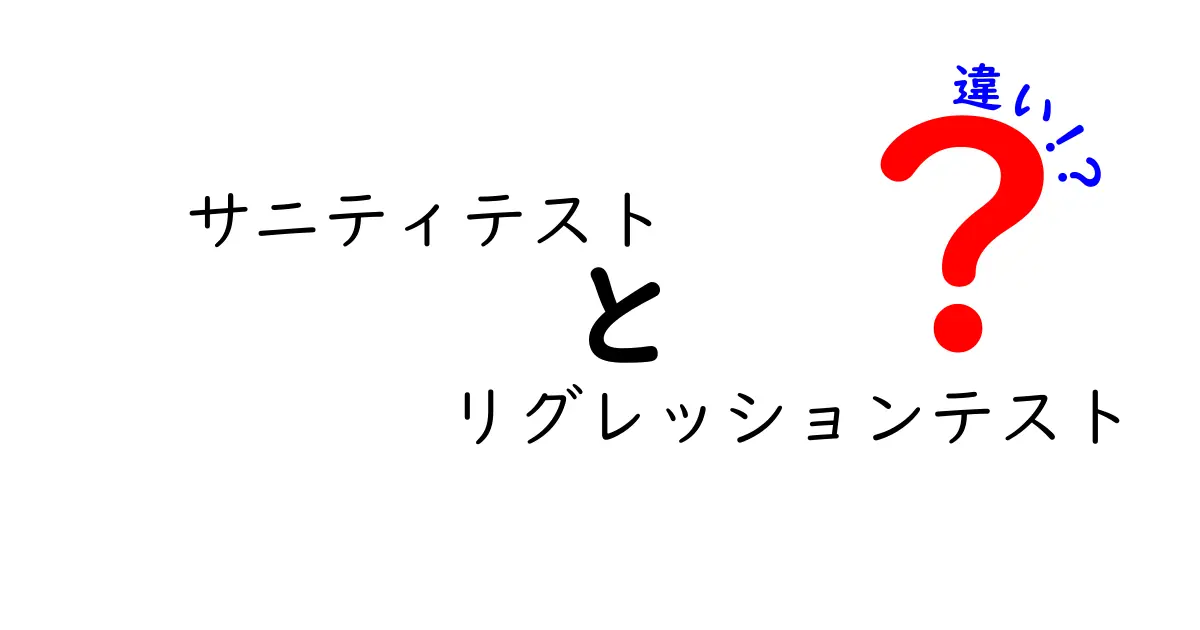

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サニティテストとリグレッションテストの違いを整理して理解する
サニティテストとは、開発者が新しい機能を取り込んだ直後に行う短時間で基本的な機能が動くかを確認するための検証です。目的は「現時点で重大な欠陥がないか」を即座に判断することで、時間を節約し、次の作業に安全に進むための前提を整えることです。これに対してリグレッションテストは、過去に発生した不具合が再発していないか、既存の機能が新しい変更によって影響を受けていないかを広い範囲で検証するテスト群です。サニティは「このビルドは動くか」を見るチェック、リグレッションは「この機能の連鎖に崩れはないか」を確認する総合検査といえます。現場の流れを考えると、まず開発者が新機能を組み込んだビルドを受け取り、サニティテストを回して基本動作が通るかを確認します。これでOKなら次の段階へ進み、エラーが出た場合には修正を優先します。
この時、サニティを回す理由は単純さと速度です。限られた時間の中で「基本動作が壊れていない」という第一の品質指標を確保するのが目的です。リグレッションは、変更がどの機能に影響を及ぼすかを把握し、広く検証するための長い道のりになることが多いです。実務では、規模が大きい変更ほどリグレッションの範囲を広げ、影響範囲が小さい変更ではサニティを中心に据えることが多いです。最後に、両者を組み合わせることで、納期と品質のバランスを取りやすくなります。適切なタイミングで適切なテストを実施することが、チームの信頼性と作業効率を高める秘訣です。
実務での使い分けと具体的な運用例
現場での使い分けは、変更の規模・影響・納期・リスクによって決まります。例えば、UIの見た目変更や文言の修正など、機能自体に大きな影響がない場合はサニティテストだけを回して短時間で品質を確認します。これにより、開発者は次の実装作業へすぐ戻れる利点があります。一方で、新機能の追加や重要なビジネスロジックの変更が絡む場合には、リグレッションテストの範囲を拡大して、既存の機能が正しく動作することを丁寧に検証します。実施の順番としては、まずビルドの健全性を確認し、次にサニティ、最後にリグレッションの順に回すケースが多いです。これには、影響度の評価、過去の不具合履歴、テストデータの整備といった要素が欠かせません。
また効率化のコツとして、テストケースの再利用・自動化の推進・テスト環境の安定化・結果の可視化を挙げられます。以下の表は、サニティとリグレッションの違いを一目で把握するためのガイドです。
この表を現場で使うと、どのテストをどのタイミングで回すべきかが視覚的にわかり、ミスを減らせます。最後に、テストの成功はツールや人の努力だけでなく、組織全体の協力と継続的な改善文化にも大きく左右されます。毎回のリリース前に短時間のチェックと長期の保証の両輪を回せば、ユーザーにとって安心して使える製品が強く育っていくのです。
リグレッションテストを深掘りする小ネタです。ある日のミーティングで、エンジニアの友人が『リグレッションは昔の不具合を見つけるための宝探しみたいだね』と言っていました。そのイメージを借りると、いまの変更が過去のどの不具合と関係するのかを追跡する地図が頭に浮かり、テストケースの作成も過去の履歴に基づく最適化になります。実際、私たちのチームはリグレッションの焦点を「重要な機能の結合部分」と「データ入力と表示の連携部分」に絞ることが多く、時間を効率的に使いながら品質を保てています。たとえば、検索機能の表示順が変わったとき、リグレッションはすぐに効力を発揮し、ユーザー体験の乱れを未然に防ぐことができました。この雑談的視点があると、テストの意味が見えやすくなるのです。





















