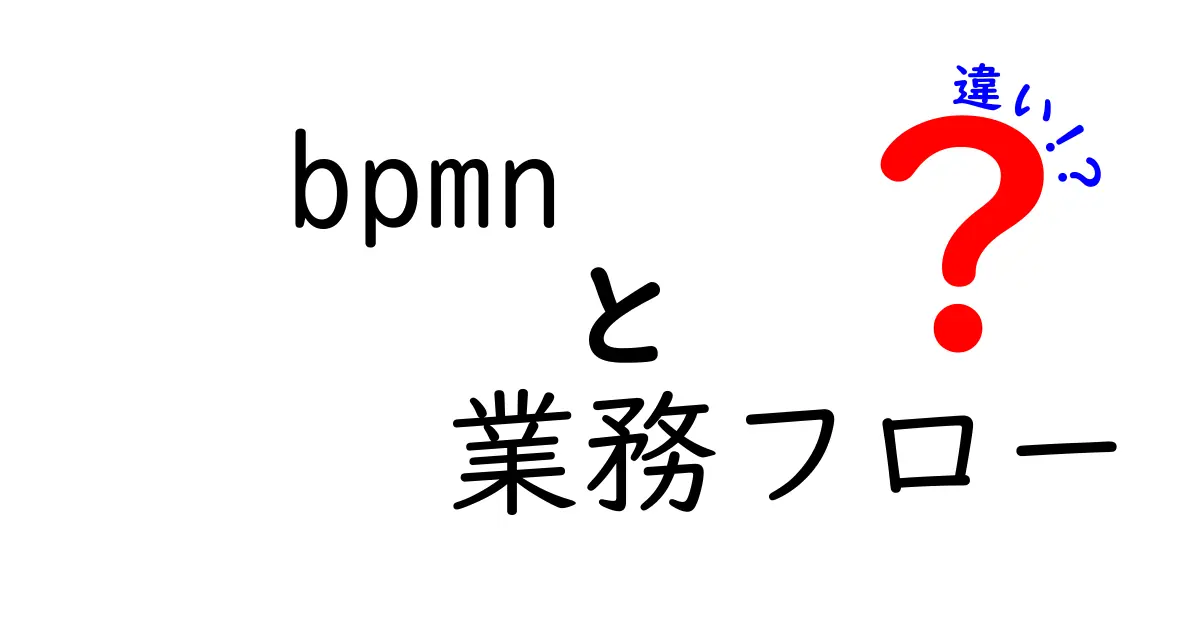

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:bpmnと業務フローの違いを正しく理解する
この記事では、BPMN と業務フローの基本を分かりやすく解説します。
はじめに覚えておきたいのは、BPMN は“標準化された図記法”であり、業務フローは“実務の伝達用の図”と考えると分かりやすいという点です。
この違いを知ることで、プロジェクトの初期段階で適切な記法を選べるようになり、混乱を避けられます。
また、学習の順序としては、まずBPMNの基本要素(開始イベント、タスク、ゲートウェイ、終了イベント)を押さえ、次に実務で使う業務フローの実例を見て、どちらの記法が適しているかを判断します。
重要なポイントは、目的と対象者を明確にすること、そして“共有のための図”か“実装のための図”かを分けて考えることです。これにより、作成物が現場で長く活躍する道筋が見えてきます。
BPMNとは何か?その基本と目的
BPMN とは Business Process Model and Notation の略で、業務プロセスを視覚的に表すための国際的な記法です。OMG が標準化しており、イベント、タスク、ゲートウェイ、データの流れなどさまざまな要素を同じ図記法で表現します。目的は“共通の理解”と“可換性”で、異なる部門や外部パートナーと流れを共有する際に誤解を減らします。BPMN の基本的な形には開始イベント、終了イベント、タスク、ゲートウェイがあります。
学習のコツは、まず全体の流れをざっくり描き、次に各要素の意味を確認することです。たとえば開始イベントはプロセスの始まり、タスクは実際の作業、ゲートウェイは分岐や結合を意味します。
ただし、BPMN はその分岐の組み合わせが複雑になるほど図が大きくなり、初心者には難しく感じられます。そこで多くの企業はツールを使い、テンプレートやレイヤーを使って階層的に整理します。BPMN を活用することで、プロセスの欠陥を見つけやすくなる点が大きな魅力です。
業務フローとは何か?実務の現場での使い方
業務フローとは日常の仕事の流れを、順序・条件・担当者を示して整理する手法です。紙のフローチャートでも、PowerPoint でも、現場の会議メモでも、"作業の道筋" を描くのが目的です。BPMN ほど厳密な記号は必要なく、必要な情報だけを取り出して伝えることができます。たとえば「購買プロセス」なら、承認、発注、納品、支払いの順序と、誰が承認するか、どの条件で分岐するか、を矢印とボックスで示します。
業務フローは誰が見ても理解できることを最優先に設計され、素早く共有・更新できることが特徴です。現場の実務では、変更が起きやすいので、見やすさと更新の手軽さが重要です。
違いのポイントと使い分けのヒント
ここでは両者の違いを具体的な観点で比較します。
まず第一のポイントは目的の違いです。BPMN は標準化された記法で共有と再利用を重視し、業務フローは日常の伝達と実務の遂行を重視します。
次に表現の厳密さです。BPMN は形式が厳密である分、細かな分岐まで正確に描けます。一方、業務フローは柔軟で、急いで伝える時には大雑把な表現でも許されることが多いです。
三つ目は対象者です。BPMN は分析者・エンジニア・PM などの専門家を想定し、業務フローは現場担当者を主な対象とします。
四つ目は実行性です。BPMN 自体は実行エンジンに接続されることを前提に設計されることが多いのに対し、業務フローはそのまま自動化を目的としていない場が多いです。
五つ目はツールと運用です。BPMN は専用ツールを使って階層化・検証・共有を行います。業務フローは紙・ホワイトボード・スプレッドシートなど身近な道具で素早く作成・共有できます。最後に、更新の頻度と教育コストも大きな差です。
このような特徴を理解したうえで、実務では「目的に合わせた使い分け」を意識します。新規プロジェクトの初期段階では BPMN で全体像を作成し、部門内の合意を取りやすくします。その後、日常の運用やチーム間の情報共有では業務フローを活用して実務の透明性と迅速な対応を確保します。
ねえ、今日は BPMN の話を雑談風に深掘りしてみよう。BPMN は業務の地図みたいなものだ。僕らが授業で描く地図は、道しるべの矢印に従って作業が進む様子を示す。BPMN には開始イベント、タスク、ゲートウェイ、終了イベントといった要素があって、それぞれの意味をきちんと理解しておくと、同じ図を見ても誰が見ても同じ流れを想像できる。例えば「注文を受けて承認→発注→納品」という流れを描くとき、ゲートウェイで条件分岐を入れると、どういうケースで次のステップが変わるかが一目で分かる。僕がいつも思うのは、難しく考えすぎるより、まず手を動かして描いてみること。すると、小さな本質、つまり「何が決定され、誰が責任を持って進めるか」が浮かび上がってくる。
前の記事: « アラームとブザーの違いを徹底解説!中学生にもわかる使い分けと実例





















