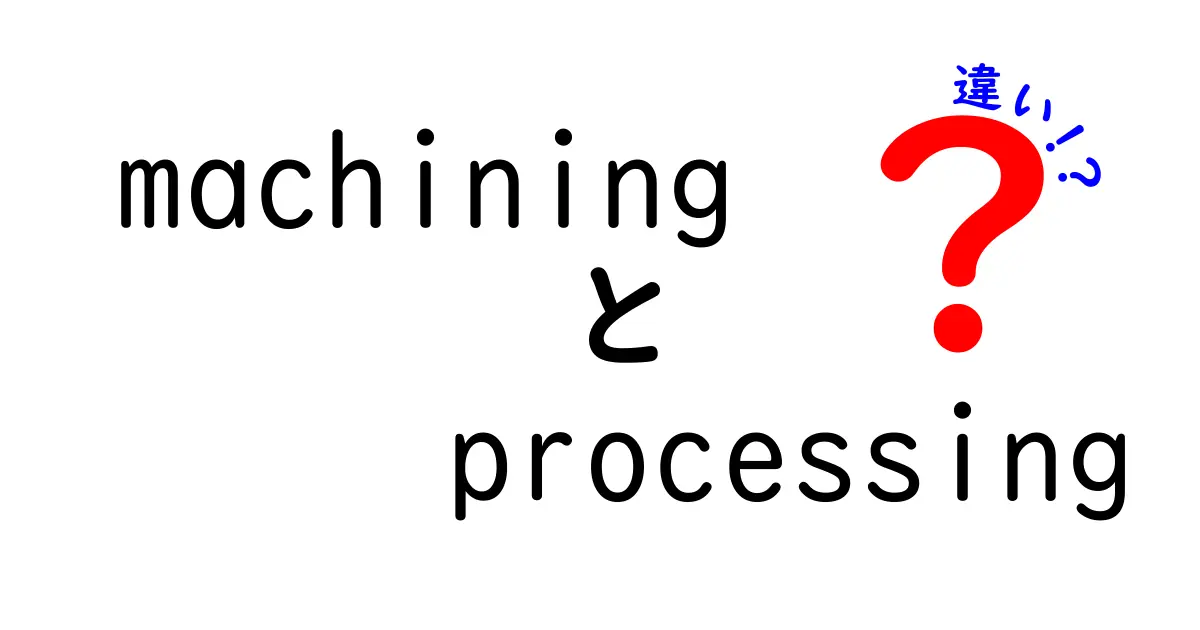

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
machiningとprocessingの違いを徹底解説:現場で使える基礎と実例
machiningとは英語で機械加工を指す言葉です。具体的には回転や切削、削り出す作業など、工作機械を使って素材を取り除くプロセスを指します。機械加工の魅力は高い再現性と寸法の正確さ、そして複雑な形状を短期間で作れる点にあります。ですが、その反面、初期設備投資が大きく、加工条件の設定や工具選択が難しい場面も多いです。
さらに、加工面の仕上がりや公差の管理は専門知識が必要で、熟練した職人の技術と計測器の精度に大きく依存します。
一方でprocessingとは何か?processingは英語で加工全般を意味する広い概念で、材料の変化を伴う作業全般を含みます。熱処理、表面処理、成形、積層造形、化学的処理、機械的な分野をまたぎます。
つまり、machiningは“削る・削り出すための機械的な作業”を指す専門用語であり、processingは“材料を変形・加工・仕上げして目的の形状や特性に近づける全体的な活動”を指す広い用語です。
具体的な使い分けと実務上の違い
現場の会話での違いを、実務の例を交えて説明します。設計図に従って部品を作る場合、部品の形状を作るのがmachiningの役割です。例えば自動車のエンジン部品や精密機械のシャフトは、機械加工で高い公差と滑らかな表面を得ます。対して部品の表面を美しく仕上げる、または材料自体の性質を変える作業はprocessingの範囲です。例えば熱処理で硬さを出したり、表面をコーティングして耐食性を高めたり、焼結・積層造形などの新しい手法を取り入れるのもprocessingの一部です。
このような違いを頭に入れておくと、外部のサービスを選ぶときにも役立ちます。必要なのは正しい用語の使い分けと、それぞれの手法の限界を理解することです。例えば公差の要求が非常に厳しい部品ならmachiningの選択が妥当ですが、複雑な形状を作るときは加工以外の方法を検討することも重要です。
またコストとリードタイムの観点でも違いがあります。一般に機械加工は工具費や治具のセッティングに初期投資がかかりますが、量産時には安定した工程で再現性が高く、品質管理もしやすい傾向があります。processingは初期コストが低く始めやすい場合もある一方で、複数の工程を組み合わせるケースが多いため、工程管理が複雑になりやすいです。結局のところ、用途、求める公差、材料、量、コスト、リードタイムを総合的に判断して、machiningとprocessingを適切に組み合わせるのが現代の設計と製造のコツです。
ある日、工場の見学で同僚が machining と processing の違いを混同していたんだ。ぼくはその場で、まず machining は“形を削って作る作業”を指す機械加工の専門用語で、加工とは別物ではなく、むしろ加工の中の一手法だと説明した。話をすると、実際には部品の寸法の公差や表面粗さが重要になるため、設計者と現場の技術者が協力して適切な手法を選ぶ必要がある。加工という広い言葉を使うと混乱するので、machiningは機械加工、processingは材料の変化を伴う全体の工程と理解するのが現場では無難だ。そう伝えると、彼らは自分たちの作業イメージがクリアになり、次の受注での選択がスムーズになった。





















