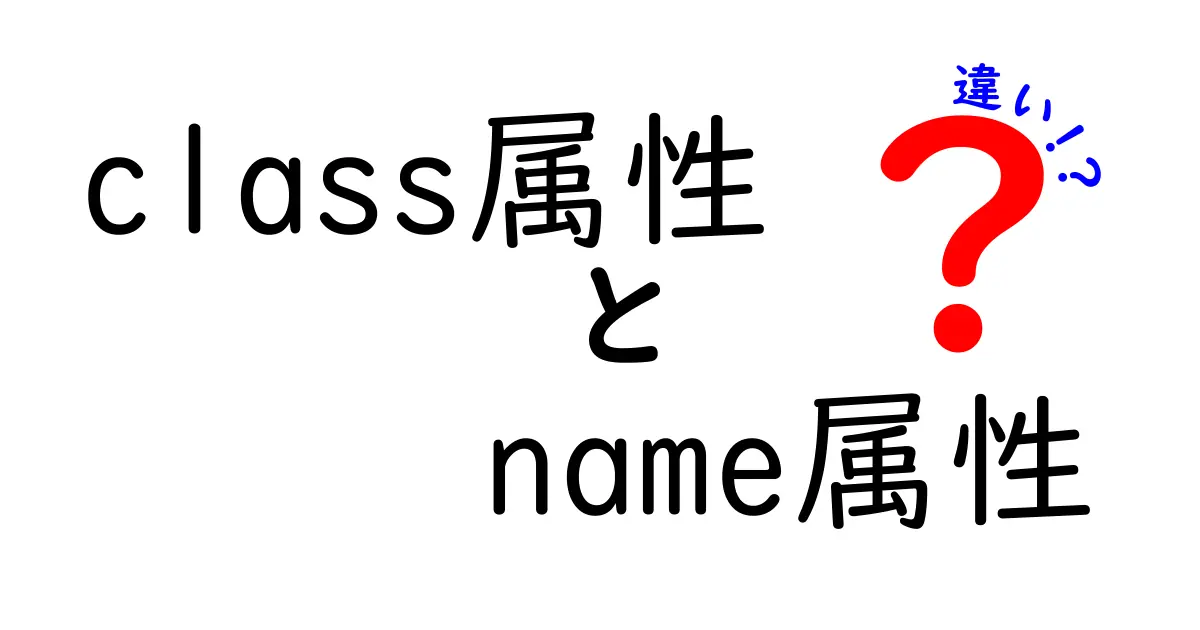

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
第1章:class属性とname属性の基本と違いをマスターする
HTMLの属性には様々な種類がありますが、私たちが日常的に使う基礎の1つが class属性です。class属性は要素に名前をつけて、CSSのルールを適用したりJavaScriptで操作したりするための道具です。たとえば <span>class="note"</span> のようにでき、それをベースにスタイルを一括変更できます。ここでのポイントは、同じ class名を複数の要素につけられる点と、class名は英数字とハイフンの組み合わせで決めるのが一般的だという点です。classを使うと、デザインの再利用性が高まり、サイト全体の見た目を統一しやすくなります。さらに、クラスはCSSセレクタの中で最も柔軟に働くため、複数のスタイルを組み合わせて使うことも簡単です。
一方で name属性は別の目的を持っています。name属性は主にフォームのデータをサーバーへ送信する際の「キー」として機能します。入力欄やチェックボックス、ラジオボタンなどには name を付けることで、サーバーに送られるデータの名前を特定します。やや技術的な話になりますが、同じ名前を持つ複数の入力がある場合、送信されるデータは通常配列のようにまとめられます。名前が違えば、サーバー側で個別の値として扱われ、データの受け取り方が変わります。
ここまでをまとめると、class属性は見た目と動作の対象をグループ化するための指標、name属性はデータをサーバーに送るときの識別子という点が大きな違いです。ウェブサイトを作るとき、この二つを混同するとデザイン崩れやデータの取りこぼしが起こります。実務では、クラスはスタイルと動作の視点で、名前はデータ送信の視点で使い分けるのが基本です。
以下に、両属性の違いを視覚的に整理する表を置いておきます。この表は要素がどの属性で何を意味づけるかを一目で確認するのに役立ちます。
また、コード例も後で紹介しますので、実際のHTMLを書きながら理解を深めてください。
次の章では、実際のコード例を使って使い分けのコツを具体的に見ていきます。コードの形としては、属性を表示するテキストと、ブラウザ上でどう見えるかの違いを比べる形がわかりやすいです。まずはコードで理解を深め、次にベストプラクティスとしてのルールをまとめましょう。
実践的な使い分けのコツと注意点
ここから先は、日常のウェブ制作で実際にどう使い分けるかの具体的なコツを紹介します。まず第一に、デザインの更新を容易にするためには「クラス名の命名規則」を決めておくと良いです。例として「button、card、header」などの意味が分かる短い英語名を使い、ハイフン区切りで見やすくします。次に、name属性はフォームごとに一意の識別子を付けます。複数の入力が同じ name を持つのは、データをグループ化したい場合です。ラジオボタンのグループ化にも name を使いますので、混同しないようにしましょう。なお、現代のウェブでは name 属性の代わりに id 属性を使って要素を識別するケースもあります。JavaScriptから値を取得する時には、document.getElementById で特定の要素を参照することが多いですが、送信データとしての役割は name が決めます。
さらに、実際のコード例を参照します。以下はテキストだけの説明ですが、HTML書き方のコツを掴むのに役立ちます。 <input class="form-input" name="username" type="text">と、 <input class="form-input" name="newsletter" type="checkbox" checked>の違いは、前者がデータを送るための名前を持つ一般的な入力、後者は同意などのフラグを送るためのものです。
このように、属性の目的を整理して使い分けると、コードが読みやすくなり、チームでの協働もしやすくなります。最後に、混乱を避けるためのルールを一つだけ挙げるとすれば、「スタイルと動作の識別は class、データ送信の識別は name」という基本原則を貫くことです。これなら、後から見返したときにも意図がすぐ伝わり、保守もしやすくなります。
実際のコード例と使い分けのコツ
実際のHTMLでの違いを、コード風の説明で確認しましょう。<!-- ここではあくまで表示用のコードを示します -->
1つのボタンを例にします。<button class="btn primary">送信</button> この場合、class によりボタンの見た目と挙動を決められます。<input type="text" name="user_name" class="input-field"> この input はサーバーへ送信する際のキーが user_name になります。
このように、属性の目的を整理して使い分けると、将来の修正時にも迷わずに対応できます。実務で大切なのは、コードを読む人がすぐに意図を理解できるような命名と構造を作ることです。
| 属性 | 用途 | 主な対象 |
|---|---|---|
| class | スタイルの適用とJSの操作の対象をグループ化 | 要素全般 |
| name | フォームデータの送信時のキーとして機能 | フォーム部品 |
表の要点をもう一度整理します。
class はデザインと機能の集合を整理する道具、name はデータの送受信時の識別子です。実務ではこの二つを別々に考える癖をつければ、後の拡張や別デバイスでの表示変更にも対応しやすくなります。
class属性はデザインの名札、name属性はデータの住所みたいなもの。テストで気づいたのは、同じ名前の入力を並べると送信データがまとまって取り出せる点。そんな地味な違いが、サイトの見栄えと機能の安定性を左右します。私が覚えたコツは、最初に役割を分けて設計すること。デザイナーはclassで属性を決め、開発者はnameでデータを管理する。これだけで、後の修正がぐっと楽になります。





















