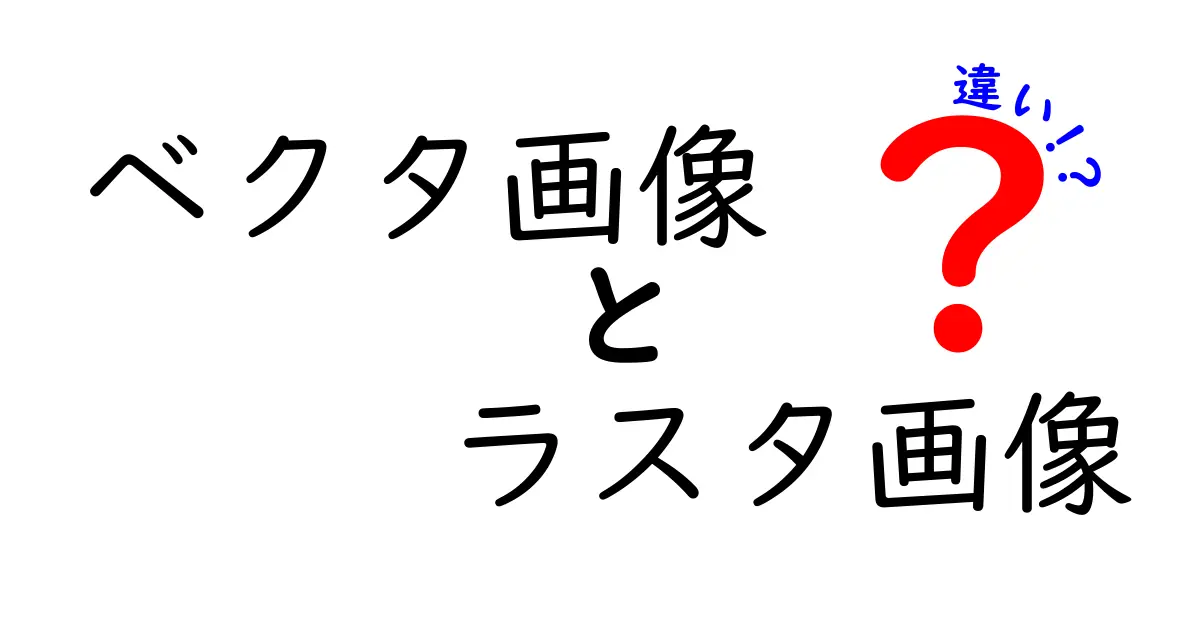

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:ベクタとラスタの基本を押さえよう
デザインを学ぶとき、写真のようにピクセルで描く方法(ラスタ)と、形を数式で描く方法(ベクタ)の二つがよく出てきます。どちらを使えばいいのか迷うことも多いです。この記事では、中学生にもわかりやすい言葉で、ベクタ画像とラスタ画像の違い、長所と短所、そして実務での使い分けを解説します。まず大事なポイントを先にまとめておくと、ベクタは拡大しても形が崩れず、ラスタは拡大するとピクセルが見えてしまうことが多い、という二つの特徴です。
この知識は、学校の美術の課題だけでなく、スマホやパソコンでのポスター作成、ウェブデザイン、ゲームなど、さまざまな場面で役に立ちます。
さっそく、それぞれの仕組みと実際の使い方を詳しく見ていきましょう。
ベクタ画像とは?その仕組みと特徴
ベクタ画像は、図形を数式で表します。直線、曲線、円、ポリゴンなどの“パス”を結んで形を作るイメージです。描く情報は「この点からこの点へ線を引く」「この曲線の動きをどう制御するか」といった命令の集まりです。そのおかげで、サイズを変えても形自体は崩れません。拡大してもエッジにギャップが生まれず、シャープな線を保つのが強みです。
代表的なファイル形式には SVG、AI、 EPS などがあり、デザインソフトで編集しやすいのも特徴です。
ただし、写真のようなリアルな表現には向かず、複雑な色の階調を表現するのが苦手な場合があります。
このセクションでは、「どうして拡大で崩れないのか」や「色の表現方法」など、基礎を丁寧に解説します。
ラスタ画像とは?その仕組みと特徴
ラスタ画像は、画面上の各ピクセルを並べて絵を作るタイプです。写真のようなグラデーションや細かな模様、影の表現は、ピクセルの集まりで表現します。解像度が高いほど滑らかに見えますが、拡大するとピクセルの粒が見える“ピクセル化”が起こります。よく使われるファイル形式には JPEG、PNG、 GIF などがあり、写真風の表現やウェブ用の画像に最適です。
ラスタは編集や修正が直感的で、カラーの階調を細かく扱えます。
ただし、解像度を上げてサイズを大きくするとファイルサイズが大きくなり、ウェブページの読み込みにも影響します。
このセクションでは、「解像度と品質の関係」や「ピクセルが崩れる仕組み」を詳しく解説します。
2つの違いを詳しく見てみよう
ここまで読んで、ベクタとラスタの違いは何となくわかってきたかもしれません。次に、具体的な比較ポイントを整理します。
以下の表は、拡大時の見え方、編集のしやすさ、ファイルサイズ、用途の目安など、実務で迷ったときに役立つポイントを並べたものです。
この表を見て分かるように、使う場面によって向き不向きが変わります。結論としては、「形をはっきりさせたいときはベクタ、写真のような複雑な色を再現したいときはラスタ」という基本が押さえられると、デザインの選択がずっと楽になります。
データ比較表
この表を使えば、どの場面でどちらを選ぶべきか判断がしやすくなります。
最後に、実務での選択のコツをまとめます。
使いどころと実務での選択ポイント
実務では、作品の性質に合わせて使い分けることが大切です。以下のポイントを覚えておくと、デザインの意思決定が早くなります。
・ロゴやアイコン、シルエット系のデザインにはベクタが最適
・写真風の表現、複雑なグラデーションにはラスタが適している
・印刷とデジタルの両方を考える場合、それぞれ最適な形式を別々に用意するのが安全
・ファイル管理では、元データの階層を維持しておくと後の編集が楽になる
・作品の使用目的を最初に設定することが、正しい形式選択の近道です。
友だちとの放課後の雑談風小ネタです。拡大時の品質を巡って、デザイナーのミナとケンが話します。ミナはベクタの強みを語り、ケンはラスタの現実的な美しさを認めます。会話の中で、拡大時の品質に関心を寄せる二人のやりとりを通じて、なぜベクタとラスタが別々の道を進むのかを自然に理解できます。例えば、看板デザインはベクタで拡大してもシャープ、写真はラスタで滑らかなグラデーションという結論に至ります。
前の記事: « dpiとppiの違いを理解して印刷・表示の品質を整える完全ガイド





















