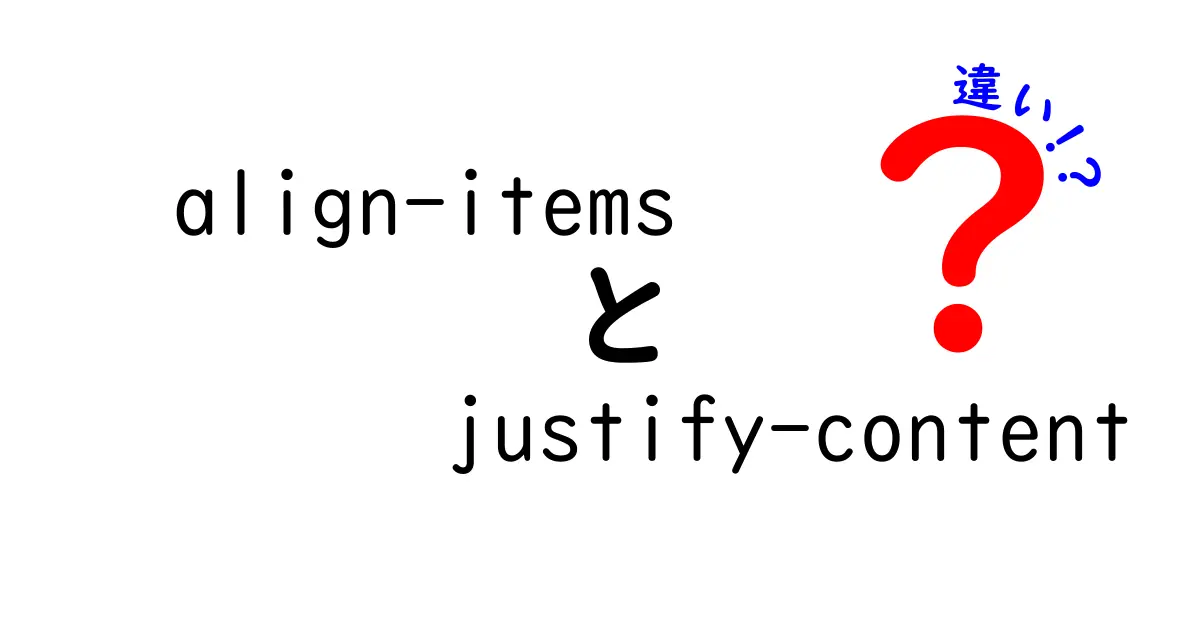

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
セクション1:align-itemsとjustify-contentの違いを正しく理解する
CSSの世界にはFlexboxという強力な仕組みがあります。その中でも align-items と justify-content は、要素をどう揃えるかを決める基本中の基本です。ここでは、2つのプロパティがそれぞれどの軸を動かすのか、どういう値を取るのか、そして日常の作業でどう活かすのかを、できるだけ身近な例を交えて分かりやすく説明します。
まず覚えておきたいのは、main axis(主軸)と cross axis(交差軸)という考え方です。Flexboxのデフォルト設定では、水平方向に並ぶボックス群を想定すると、justify-content が主軸方向の揃え方、align-items が交差軸方向の揃え方を担当します。これを理解すると、横に並んだ要素を上下左右にどう配置するかが見える化され、複雑なレイアウトでも崩れにくくなります。
次に、各プロパティが取り得る代表的な値をイメージで押さえましょう。justify-content の代表値には flex-start、center、flex-end、space-between、space-around などがあり、横一列の列の並び全体をどう配置するかを決めます。対して align-items の代表値には stretch、center、flex-start、flex-end、baseline などがあり、縦方向の配置を決定します。ここでの違いは「どの軸を動かすか」と「どんな揃え方を使うか」という点に集約されます。
この二つの違いを押さえると、例えばカードを横並びに並べて、カードの中身は上下中央に揃えるといった複合的なレイアウトも、迷うことなく実現できるようになります。基本ルールを覚え、混乱する場面では軸の名前を思い出すことが、デザインの安定につながります。
セクション2:実践的な使い方と注意点
実際のコードを見ていきましょう。まず container に display:flex を設定します。すると主軸は水平方向に広がるのが普通です。ここで justify-content を使って横方向の整列を決めます。例えば、カードを左寄せにしたいなら justify-content: flex-start;、中央寄せなら justify-content: center;、右寄せなら justify-content: flex-end;。同時に align-items を使うと縦方向の揃え方を決めることができます。例えばアイテムを縦方向に中央寄せしたい場合は align-items: center;、全体を上部に揃えたい場合は align-items: flex-start; などを使います。
ここで覚えておきたいのは「主軸と交差軸は常にセットで考える」ということです。片方だけいじってもう一方が想定と違う挙動になる場面が多く、初心者のうちはここで混乱しがちです。実践のコツとして、まずは3つの代表値を1つずつ試して挙動を観察すると、感覚がつかめてきます。
また、値の組み合わせには注意点があります。例えば justify-content: space-between は要素の間を等間隔に開けますが、端の要素と容器の端との間には空白が生まれます。空白の取り方はデザイン全体のバランスに影響するため、目的に合わせて使い分けましょう。さらに、flex-start や flex-end の挙動は文字打ちや多言語対応時の微妙なずれを生むことがあるので、フォントの高さや行間にも注意が必要です。
セクション3:理解を深める実例と図解
まずは身近な例から考えましょう。想像してみてください。学校の掲示板に3枚の写真カードが横に並んでいます。justify-content で横の並び全体を中央寄せにすると、カードの列が画面の真ん中に集まります。次に align-items を centre にすると、各カードの中身は縦方向にも中央に位置します。ここがポイントです。横並びで整えつつ、カード内のテキストやアイコンを縦方向にも美しく配置する。この両方を使いこなせると、デザインの自由度が大きく広がります。
以下の表は値の感覚をつかむのに役立つ簡易表です。
・justify-content の主な値の感覚:flex-start は左寄せ、center は中央寄せ、flex-end は右寄せ、space-between は要素間を等間隔、space-around は要素の前後にも等間隔を作ります。
・align-items の主な値の感覚:stretch は要素の高さをコンテナいっぱいに引き伸ばします。center は縦の中央、flex-start は縦の上部、flex-end は下部、baseline は文字のベースラインに揃えます。
このように、軸ごとの挙動を分解して理解することで、レスポンシブデザインや異なる画面サイズへの対応が楽になります。
実務では、これらの値を組み合わせて柔軟なレイアウトを作る機会が多いです。はじめは地味ですが、慣れるとデザインの幅がぐんと広がり、崩れにくい作業が可能になります。
最後に、重要なポイントをもう一度まとめます。主軸と交差軸の理解を基礎とする、代表値を体で覚える、組み合わせの影響を常に意識する、この三つを守れば、あなたのCSSは格段に扱いやすくなります。
ある日、友だちのケンが新しいウェブページのレイアウトに悩んでいました。彼は align-items の挙動がよく分からず、justify-content だけをいじってしまっていました。私が横から見て、こう言いました。まずは主軸と交差軸という“道すじ”を決めることが大切だと。例えば写真を横並びにして、横方向は中央寄せ、縦方向は中央寄せにするには、justify-content: center; と align-items: center; を同時に使えば良い。すると、カードは画面の中心に美しく収まります。最初は難しく感じるかもしれませんが、軸を分解して考える癖をつければ、どんなレイアウトでも整合性が取れるようになります。私たちは実験を重ね、値を変えながら画面の反応を観察しました。結局、デザインの良さは「揃い具合の心地よさ」に集約されます。
結論はシンプル。難しく考えず、まず軸を決め、次にその軸に沿って要素をどう並べるかを考える。これだけで、あなたのCSSはぐっと使いやすく、見た目も安定します。





















