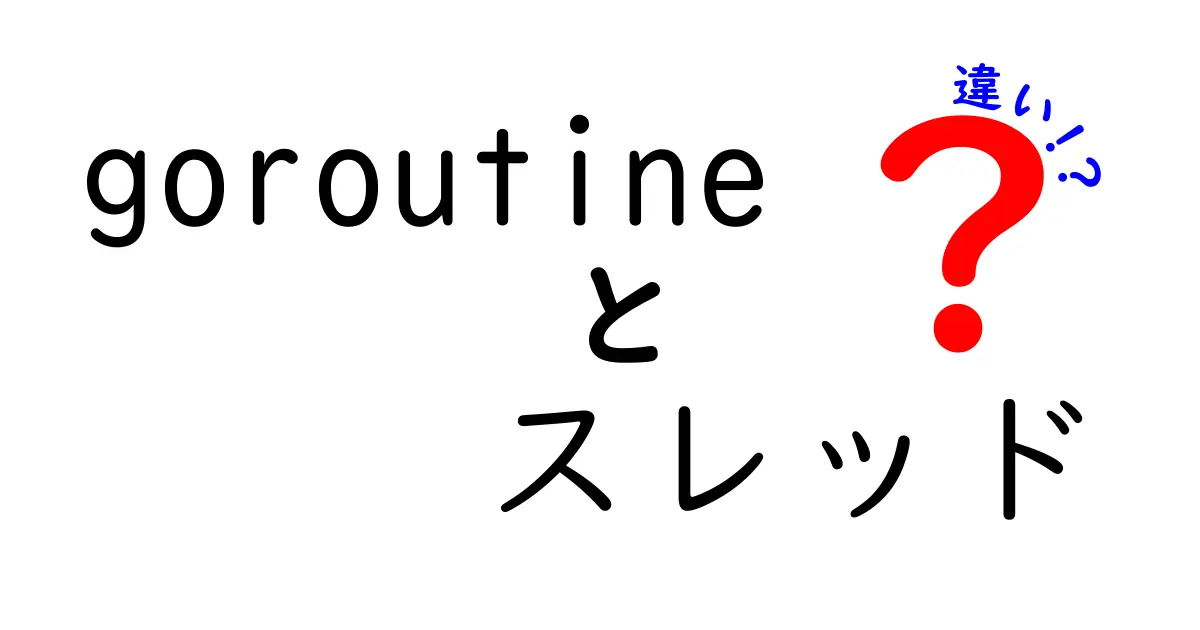

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
goroutineとスレッドの違いを徹底解説:初心者にもわかる並行処理のはなし
このページではgoroutineとスレッドの違いを丁寧に説明します。初心者にもわかるように、専門用語を控えめに使い、身近な例えで語ることを心がけました。まず大事な点は結論です。goroutineはGoの中で使われるとても軽い並行実行単位であり、OSが管理するスレッドの上に乗って動く仮想的な存在だという点です。これを理解すると並行処理の世界がぐっと身近になります
対してOSが直接管理するスレッドは実体のある実行単位であり、作成や切り替えのコストが高いことが多いです。Goの世界ではこの重さを回避するためにgoroutineという軽量な枠組みを提供しています。実際にはgoroutineを数千から数万作っても問題になりにくい設計であり、一方でスレッドは現実的には数十から数百程度の同時実行を想定して使われることが多いのです
この違いを日常の作業に置き換えてみると理解しやすくなります。たとえば学校の文化祭を例にします。全部を一人の先生が回せば大変ですが、先生が何人もいてそれぞれが役割を分担して動くと効率が上がります。goroutineはこの分担をプログラムの中で行う仕組みであり、スレッドは実際の人のように動く実体です。ここが大きな違いの肝となります
Goのランタイムはgoroutineの実行をスケジュールします。つまり走る順序や実行時間を細かく管理してくれるのがランタイムです。これがあるおかげで私たちは複雑な並行処理を自分で低レベルの管理をしなくてもよくなり、コードはシンプルに保てます。逆にOSのスケジューラに任せるスレッドの実行は、言い換えればOSの都合に左右されやすい部分があり得ます
このセクションの要点をまとめると goroutineは軽量で多く生成できるという点と スレッドはOSが管理する実体であり重いという点です。実務ではこの二つの性質をうまく使い分けることが重要です。配信系のアプリやウェブサーバーのように多くの並行処理が必要な場面ではgoroutineを主力に置き、専用の低レベル処理やデスクトップアプリの細かなOS連携が必要な場合はスレッドの使い分けを検討します
現場での使い分けと注意点
現場ではgoroutine の活用に際していくつかの注意が必要です。まず 並行性のバグと呼ばれる現象は race condition のような状況が発生しやすいので適切な同期を使うことが大切です。Goにはチャンネルという強力な通信機構があり、goroutine 同士のデータ共有を安全に行えます。
チャンネルは値を送る箱のようなものだと考えるとイメージしやすいです。値を渡すたびに同期が生まれ、データ競合を避けることができます
またデッドロックの回避にも注意が必要です。goroutine を数多く作ると各タスクの完了を待つ仕組みが複雑になり、時には全体が止まってしまうことがあります。設計段階でデッドロックの可能性を減らすために、タスクの境界をはっきりと決め、必要な場合だけ待機を行うような構造を作ることが重要です
最後に実務での学習のコツとして、まずは小さな例題から始め、段階的に複雑なケースへ移行することをおすすめします。簡単な同時処理の例を書いて、どう動くかを観察するだけでも理解は深まります。
オンラインの学習リソースや公式ドキュメントに目を通すと、概念と実装の結びつきがはっきりと見えてきます





















