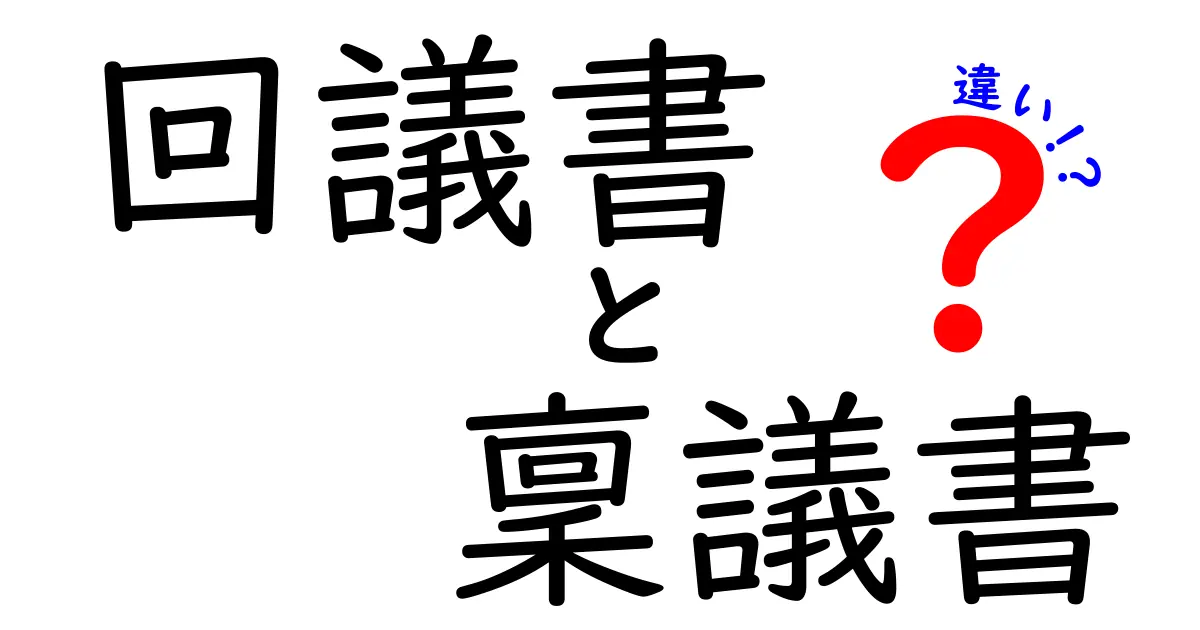

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:回議書と稟議書の基本を知る
回議書と稟議書は似たような名称で混同されがちですが、実務の現場ではそれぞれ別の役割と使われ方をします。ここではまず両者の基本を整理します。
「稟議書」は正式な決裁を得るための文書で、案件を検討する人たちを順番に回覧して承認を得る仕組みです。回覧の順序は組織によって異なりますが、基本的には提出者が起草し、部門長・課長・部長・役員などの段階を経て最終的な判断を受けます。
承認の可否は金額、リスク、期限、法的な影響などを含む条件とセットで判断され、金額が大きいほど上位の承認が必要になることが多いです。
一方で「回議書」は会議の決定事項を関係部署に伝えるための文書です。会議で出た結論や割り当てられたタスク、実行のスケジュールなどを文章に落とし、理解のズレを防ぐ役割を持ちます。
このように稟議書は“承認は誰が何を決めるか”を明確にする道具、回議書は“決定を実務へ落とし誰に何を伝えるか”を明確にする道具だと覚えると違いが見えやすくなります。
企業のルールや組織の慣例によって名称が異なる場合もありますが、基本的な考え方は変わりません。
この記事を読めば、初めて見る人でも稟議書と回議書の役割をすぐに理解できるようになるはずです。
稟議書の特徴と使い方
稟議書の特徴は「承認を得るための正式な回覧」だという点です。作成時には案件の目的、背景、予算、影響範囲、リスク、代替案、スケジュール、決裁者の署名欄を盛り込みます。
使い方の流れはおおまかに次のとおりです。まず提案者が文案を作成し、関係部署の担当者を含む関係者に回覧します。次に「承認可否」と「理由」を添えて各人が署名または押印します。最終的には部門長や経営層の承認が得られれば正式に決裁となり、実行計画へ移ります。
回覧中には期限を設定して、遅延を防ぐ工夫をします。
以下に典型的な構成の例を挙げます。
例:新しいパソコンの導入、契約更新、社内制度の改定など、金額が一定以上になる案件を対象にするのが一般的です。
承認の過程では「どの部門が責任を持つか」「予算の出所はどこか」「代替案はあるか」など、のちの運用で支障が出ないように詳しく確認します。
企業によっては回覧の順序が先に決められており、先に人事部、次にIT部、最後に財務部の順で回すといった定型が存在します。
さらに実務では稟議書を使って新規プロジェクトの予算枠の確保や契約条件の承認を同時に進める場合もあります。
回議書の特徴と使い方
回議書の特徴は「会議で決まったことを伝える通知文である」という点です。会議の結論、決定事項、担当者、期限、必要なフォローアップの手順を明確に書くことで、実務の現場で混乱を防ぐ役割を果たします。
使い方の流れは、まず会議後に議事録と合わせて作成します。次に関係部署へ回覧し、内容を理解したことを確認します。特に実行担当者へ「いつまでに何をどうするか」を具体的に指示することが重要です。
回議書は「決定事項を速やかに伝え、実務の着手を速める」ことが目的であるため、曖昧な表現は避け、期限・責任者・成果物をはっきりと書くのがコツです。
ただし組織によっては回議書の代わりに「決裁済み通知」や「議事録の補足文」など別の形式を用いることもあります。慣例を尊重しつつ、分かりやすさを優先しましょう。
回議書と稟議書の違い:比較と使い分けのコツ
実務での使い分けを理解するためには、具体的な場面を想定して整理するのが近道です。ここでは代表的な違いを要点として表にまとめ、どのようなケースでどちらを使うべきかの判断基準を示します。
以下の表は一般的な傾向を示すものであり、組織ごとに異なる運用がある点に注意してください。表の読み方を身につけると、文書の準備時間を短縮でき、誤った書式で提出するミスを減らせます。
この違いを意識して使い分けるだけで、組織内の意思決定プロセスがより透明で効率的になります。稟議書は“権限を持つ人の決断を集める場”として機能し、回議書は“決定を実務に落とし込み周知する場”として機能します。
実務ではこの二つを組み合わせて使うケースも多く、予算の承認を稟議書で取りつつ、会議後には回議書で実行計画を全社へ共有する流れがよく見られます。
まとめ
この記事では稟議書と回議書の基本的な役割と使い方、そして違いを分かりやすく解説しました。
要点を整理すると、稟議書は承認を得るための道具、回議書は決定を伝える道具であることが分かります。組織によって呼び方は異なるかもしれませんが、基本的な考え方は同じです。
文書を作成する際には目的を頭に置き、決裁者や実行担当者、期限を明確に書くことが大切です。これを実践すれば、ビジネスの現場でのコミュニケーションが円滑になり、意思決定のスピードも上がるでしょう。
ねえ、今日は稟議書と回議書の違いについて雑談風に話してみよう。稟議書は案を正式に“承認してもらうための回覧文書”で、金額が大きいときは特に上位の人の合意が必要になることが多い。対して回議書は会議で決まったことを実務に落とすための通知文。つまり稟議書は決裁を取りに行く道具、回議書は決定を伝え実行を進める道具という二つの役割を持つんだ。文化祭の予算を例にとると、稟議書で使う予算承認を取り、会議後の回議書で「いつまでに誰が何をするのか」を全員へ伝える、そんな使い分けが基本になる。初めは難しそうに見えるけど、用途を分けて覚えると文書作成が断然楽になるよ。
前の記事: « 原義書と稟議書の違いを徹底解説:ビジネス文書の基礎を押さえる





















