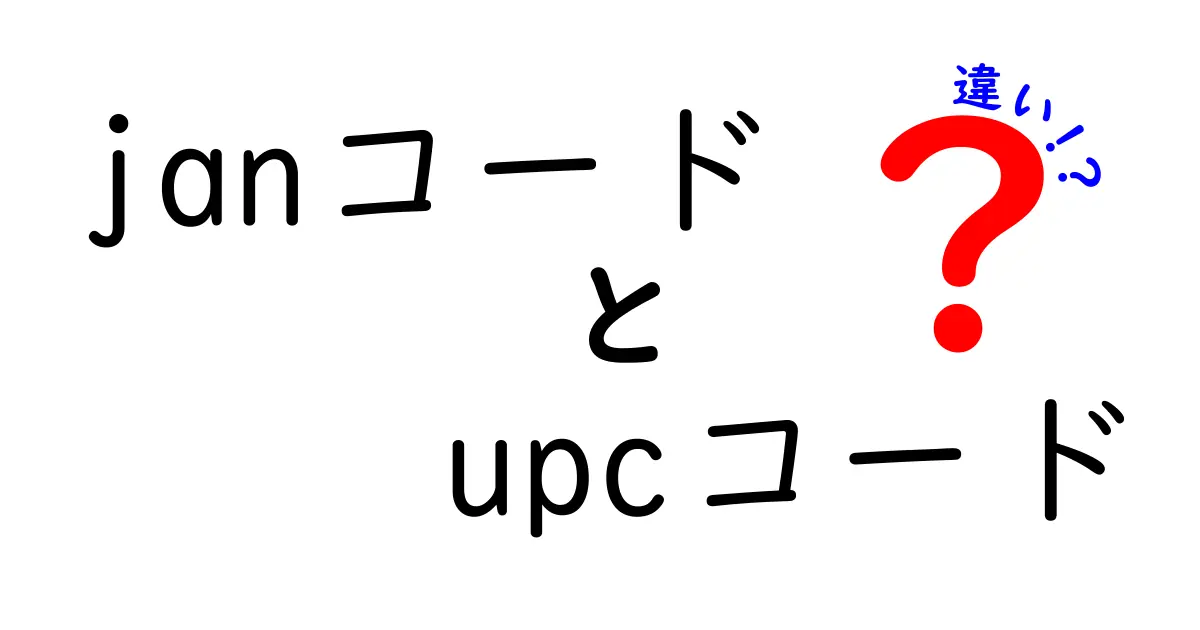

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
janコードとUPCコードの違いを徹底解説!意味・用途・使い分けを中学生にもわかる解説
まず前提として、JANコードとUPCコードはどちらも「商品を識別するための番号」です。日本では主に商店や製造者が使い、UPCコードは北米やヨーロッパの一部地域で広く使われます。これらは別の体系のように見えますが、実は同じ世界の中で動くしくみで、GS1という団体が定めた標準をもとに運用されています。
この二つの大きな違いは、長さと地域の呼び名くらいに思えますが、実務では「同じデータを別のコード表現として持つ」という点がとても重要です。
JANコードは日本で主に使われる表記で、UPCコードは北米で主に使われます。実際にはJANコードはEAN-13の日本向け表記として扱われ、読み取り自体は世界中のスキャナで可能です。
つまり、UPCコードを読むときには読み取り側の調整が必要になることがありますが、多くの場合は「左に0を追加してEAN-13へ変換する」ことで互換性を作ります。
ここがポイントです。別々の命名ではありますが、 データ構造やチェックディジットは同じアルゴリズムを使い、物品の識別番号として機能します。
したがって実務上は、日本国内の流通でも海外との取引でも、読み取りの際の混乱を避けるために「別コード名を使い分けつつ、データは同じものを扱う」という運用が一般的です。
この考え方は、流通の効率化と正確性の両方を守るために欠かせません。
最後に覚えておくべきことは、JANコードとUPCコードの違いは「使われる地域と呼び方の違い」に過ぎず、世界中の物流を支える共通原理に結びついているという点です。
違いのポイントと使い分け
では具体的にどんな点が違い、どう使い分けるべきかを見ていきます。まずUPCコードは通常12桁で、北米中心の流通で使われます。一方、JANコードは13桁の表記となり、日本の市場で広く採用されています。実はUPCコードとEANの組み合わせの間には、相互変換の関係があり、例えばUPC-Aをそのまま13桁のEANとして扱うには前に0を付けるだけで済むケースが多いです。こうした変換ルールは、海外パートナーとデータを共有するうえでとても役立ちます。
もうひとつのポイントは、チェックディジットの計算方法が同じである点です。13桁でも12桁でも、末尾の桁は他の桁の組み合わせから決まります。商業の現場では、GS1という団体が定める標準規則に従い、識別番号を正しく割り当て、商品の情報と照合しています。
また、日本国内の小売現場ではJANコードを中心に在庫管理や価格表示が行われ、海外ではUPCコードが頻繁に見られますが、データベース上は同じ「商品を識別する番号」として結びつけられています。
実務で覚えておくべき実用ポイントは、コード名の違いに惑わされず、読み取り可能な形でデータを統一することです。
この考え方があると、輸出入の際の検品や棚卸し、在庫管理、POSでの表示など、日常の業務をぐんとスムーズにします。
JANコードについての小ネタを一つ。友達と買い物しているとき、レジの前で『このバーコードは日本のJANコードだね』と話していると、別の友達が『でも海外の棚にはUPC表記も混じってるよね』と答えます。すると、店員さんは0を前に付けて読み取りソフトを調整してくれることが多いと教えてくれました。つまり一つの数字が、異なる地域のデータとつながる入口になるのです。GS1という国際的な標準機関がこの仕組みを支え、私たちの買い物体験を滑らかにしているという話は、日常の細かいところにも大事なヒントを与えてくれます。身近なものほど、世界の仕組みとつながっているという実感が得られるのが、この雑談風の話の魅力です。





















