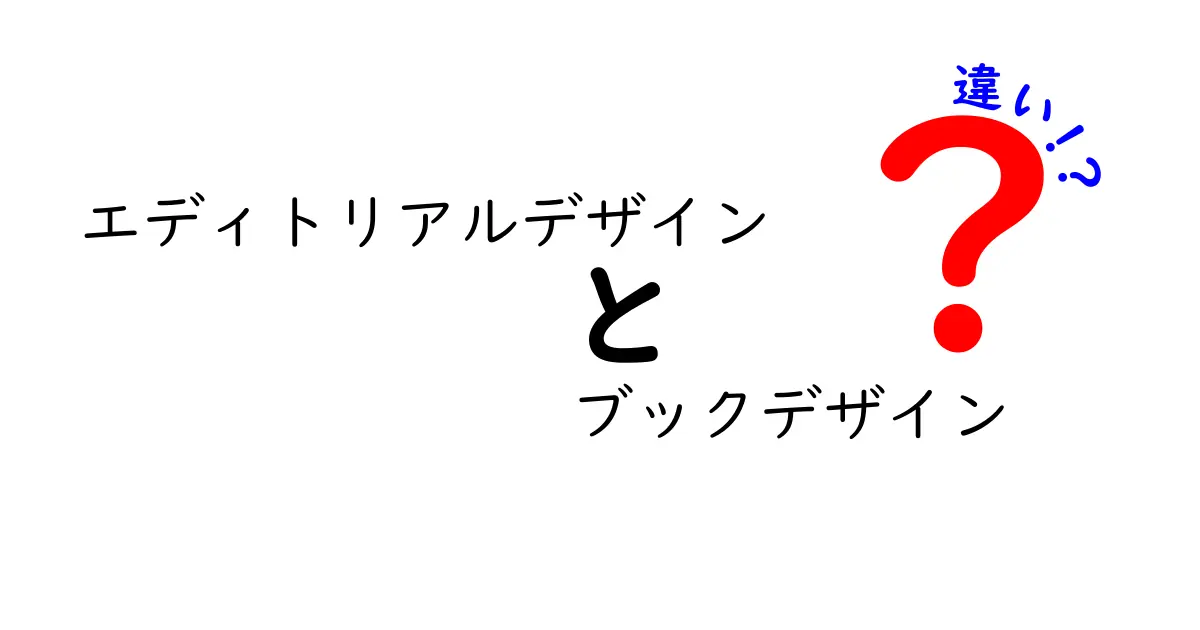

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
エディトリアルデザインとブックデザインの基本的な違いを理解する
エディトリアルデザインは、雑誌・新聞・ウェブなど、情報を読み手に伝えるためのページ設計を中心に行う分野です。ここでは情報の読みやすさ、視線の動き、情報の階層性を整えることが最優先になります。グリッドのルール、タイポグラフィの階層、色の組み合わせ、写真と図表の配置など、見出しから本文、キャプションに至るまで一連のデザイン設計が統一感を生み出します。読者が情報を素早く受け取り、正しい順序で理解できるようにするための「道具立て」を作るのがエディトリアルデザインの役割です。
一方でブックデザインは、書物という物理的な artefact を設計する作業です。本文の長さや段落の分量、行間や字幅、紙質や印刷の色再現、装丁や背表紙、表紙・扉のデザインといった要素が作品全体の体験を決定します。ブックデザインは「読むことそのもの」を支える装置であり、紙の触感や製本の品質が読書体験に深く関与します。
この二つは似ている点も多いです。どちらも読みやすさを第一に考え、情報を整理して伝えるための美しさと機能性を両立させる必要があります。しかし対象媒体が異なるため、設計の優先順位や制約が変わります。エディトリアルデザインはページ間の連続性と情報の流れを重視し、ブックデザインは長時間の読書体験と物理的な本の魅力を重ね合わせます。
この違いを理解することは、デザインの学習を始める人にとって最初の大きな一歩です。読者がどのように情報を受け取り、どの場面で感動するのかを意識して作ることが、両分野の基礎を固める鍵になります。
エディトリアルデザインには、読者の視線誘導を設計する能力、情報の整然とした階層化、そして印刷現場との連携を前提にした色管理が求められます。雑誌のページでは、見出しと本文のサイズ差、図版の大きさ、キャプションの位置関係、読み進める順序を計画します。写真と本文の関係性を保ちつつ、誤解を招かないようなレイアウト設計が重要です。さらに、オンライン媒体ではレスポンシブデザインやタイポグラフィの可読性も重要で、デジタルと紙の両方を想定して設計を進めます。
ブックデザインは、長文を読むことを前提にした設計であり、紙の選択、印刷方法、色再現、そして製本の仕方までが大きな要素になります。読みやすさを保つための字間・行間・段組みのバランス、章立てのリズム、目次・索引の使いやすさ、扉ページや見返しのデザインなど、全体の体験を通して一冊の本としての完成度を高めます。背景の色味や紙の白さ、インクの発色は、読者が文字を追いやすく感じるかどうかを直接左右します。ブックデザインはこれらの物理的な要素を統合し、読者が「この本を読みたい」と思う気持ちを引き出す力を持ちます。
総じて、エディトリアルデザインとブックデザインは、情報の伝え方と読書体験の両方を豊かにする仕事です。違いを理解することで、デザインの学習者は媒体ごとの適切なアプローチを身につけ、読者にとって最適な視覚体験を提供できるようになります。
ブックデザインの特徴と実務上の要点
ブックデザインは、長時間の読書を前提にした「物理的な読みやすさ」を最優先します。本文の行間や字詰め、段組みの幅、活字の選択と組み合わせ、章の分かれ方、見出しの配置など、読者が自然に目で追えるリズムを作ることが目的です。紙の紙質や色、印刷の濃度、インクのにじみといった物性の要素も、読み心地に直結します。扉ページや扉のデザイン、背表紙の耐久性、表紙の素材など、手に取った瞬間の印象も重要な要素です。
実務では、デザイナーと編集者の連携が強く求められます。本文の流れを崩さず、章ごとの統一感を保つためのガイドライン作成、印刷所への入稿データの作成、色の管理、プリプレスの段取り、紙の厚みや表紙の仕上げの選択など、製本までを考慮した総合的な設計力が必要になります。読者が本を開くたびに「丁寧に作られている」と感じられるような設計を心がけることが、良いブックデザインの根底です。
また、ブックデザインはその本のジャンルやターゲット層に応じて設計方針を変える柔軟性も求められます。学術書と児童書、ノンフィクションとフィクションでは適切な字形、行間、段組み、そして装丁の選択が異なるため、ケースバイケースの判断が重要になります。結局のところ、ブックデザインは「読みやすさ」と「触れてみたくなる魅力」の両方を両立させることが最終的な目的です。
以下は、エディトリアルデザインとブックデザインの違いを視覚的に整理するための簡易表です。要素 エディトリアルデザイン ブックデザイン 目的 情報を素早く伝えること 長時間の読書体験を設計 対象媒体 雑誌・新聞・ウェブなどのページ 本の紙面・装丁・製本 主な考慮点 グリッド、タイポグラフィ、可読性 紙質、印刷、背表紙、ページ割り 成果物 ページデザインのガイドライン、版面 一冊の本としての完成品
このように、似ている点は多いですが、現場で直面する課題や作るものの性質は異なります。どちらの分野も「読者に伝える力」を高めることが目的であり、目的と媒体に合わせた設計の感覚を身につけることが重要です。さらに、実務で役立つスキルとして、デザインツールの使いこなし、プリプレス・印刷の基本知識、色管理、タイポグラフィの基礎、マニュアル作成能力などを積み重ねていくと良いでしょう。
ある日の放課後、本屋で友達と話していたときのこと。彼は『ブックデザインは表紙だけをきれいにすればいいと思っていたんだ』と言い、私は『それだけじゃなく、本文の行間や紙の手触りが読み心地を決めるんだよ』と答えた。表紙の印象と本文の読みやすさ、この二つのバランスが取れて初めて“本としての完成”が生まれる。ブックデザインは、視覚だけでなく触覚もデザインする、そんな会話だった。
私たちは本を手に取り、ページをめくる瞬間の感覚を大事にしている。デザインは決して表面的な装飾ではなく、長い旅の途中で読者を支える“伴走者”の役割を果たすのだと気づかされる雑談でした。
次の記事: デグー モルモット 違いを徹底解説!見分け方と飼い方のヒント »





















