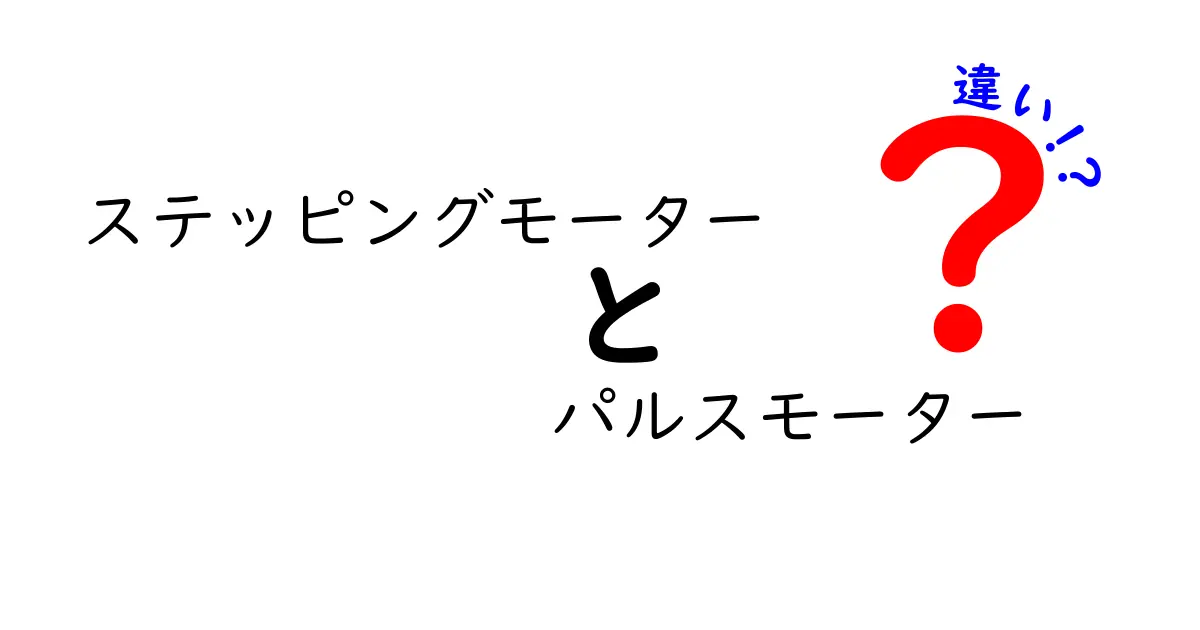

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ステッピングモーターとパルスモーターの違いを理解する基本
ステッピングモーターは回転をひとつずつ刻む仕組みの電動機です。
コイルに電気を順番に流すと、 rotor の磁石が一定の角度だけ動き、カクカクと進みます。
1回のパルスで1ステップ進むのが基本で、回転角は設計によって決まっています。
代表的な角度は 1.8 度で、1周は 200ステップと呼ばれます。
パルスの数を増やしたり、微小なパルスを連続して出す「マイクロステッピング」という技術を使うと、動きは細かくなり、角度のずれを減らせます。
利点は構造が比較的シンプルで、フィードバックがなくても位置決めが可能な点です。
小型装置やロボット、プリンタの紙送り、正確な停止位置が必要な機器で広く使われます。
ただし欠点として、回転速度を上げるとトルクが急に落ちやすく、共振や振動が出やすいことがあります。
音がうるさくなることもあり、連続走行には適していない場合があります。
用途で言えば、正確な位置決めと小さな動きの再現性が重要な機械に適します。
場合によっては マイクロステッピング で滑らかな動作を実現することも可能です。
仕組みと使い分けのポイント
パルスモーターはパルス信号を受けて角度を進めることが基本ですが、構造や設計思想はステッピングモーターと重なる点もあります。
しかし現代の産業では ステッピングモーター+マイクロステッピング の組み合わせが、低速時の高トルクと滑らかな動作の両立として広く使われています。
パルスモーターという言い方は昔は多く使われましたが、現在では ステッピングモーター の呼び方が普通になってきています。
重要なのは、どのような条件で回転を制御したいかです。
速度、トルク、精度、コストのバランスをみて選ぶとよいです。
結論として、正確な位置決めと滑らかな動作を両立したい場合は ステッピングモーター+マイクロステッピング が現在の標準的な選択肢です。
一方でパルス信号で回転を制御する古い設計や特定の機器では、パルスモーターという呼び方が使われ続ける場面もあります。
放課後の理科室で流れる会話をそのまま再現します。僕と友達は机の上の小さなロボットを囲み、ステッピングモーターとパルスモーターの違いについて話しました。友達のユウは言いました—「ステッピングモーターは回転を一歩ずつ決めるから、プログラムどおりに動かせるのが強みだよね。でも振動が出やすいから、静かに動かしたいときは工夫が必要だよね」僕は続けて「パルスモーターは古い言い方だけど、パルス信号を増やせば連続的な動作も可能になる。結局はどんな機械で、どんな速度が必要かで選ぶべきだと思う」と答えました。先生は後ろから「まず目的を決めることが大事」と言い、僕らは実際に同じモーターを使って回転速度を変えながら、トルクの変化を体感しました。この雑談のようなやり取りが、モーター選びの第一歩を楽しくしてくれたのです。





















