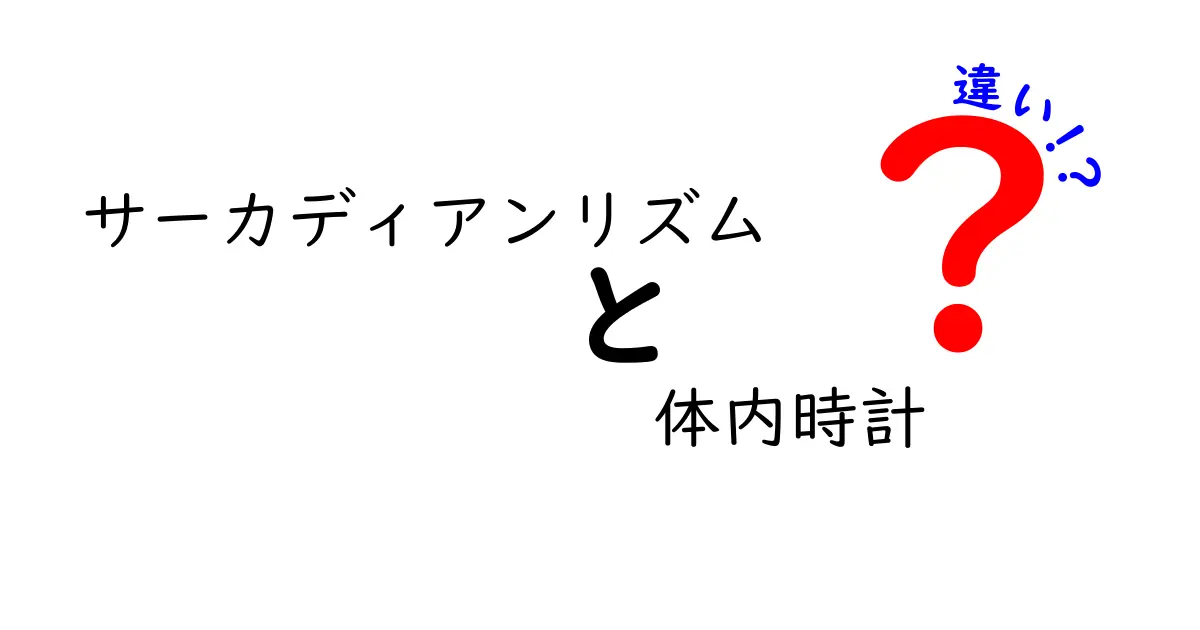

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
サーカディアンリズムと体内時計の違いを理解する基本
私たちの体には、毎日おおよそ24時間のリズムが自然と存在します。これをサーカディアンリズムと呼び、眠気の波、体温の変化、ホルモンの分泌タイミングなど、日常のさまざまな現象に影響します。
サーカディアンリズムは観察できる現象であり、睡眠時間や活動のリズムとして私たちの生活の中に現れます。いっぽう、体内時計とはそのリズムを作り出す“機械”のことを指します。脳には視床下部のSCNという部位があり、そこから全身の細胞へ信号を出して、眠るべき時、起きるべき時を教えます。この“機械”が正しく働くことで、私たちは眠りを取り、目を覚まし、体を動かす準備を整えられるのです。しかし、実際にはSCNだけでなく、全身の細胞にも時計遺伝子があり、各部位が協力してリズムを微調整しています。つまり、サーカディアンリズムは全身の"時刻表"、体内時計はその時刻表を作る"機械"というイメージを持つと分かりやすいです。外部の光、食事の時間、運動、睡眠の習慣など、日々の生活のささやかな変化がこの機械の動きを変え、結果として私たちの活動時間や睡眠の質に現れます。現代社会では、夜更かしや室内の人工光が体内時計を混乱させ、眠りが浅くなったり朝の目覚めが悪くなったりすることが多いのです。こうした迷いを減らすためにも、次の表でサーカディアンリズムと体内時計の違いを整理しておくと理解が進みます。
日常生活での実感とリズムを整えるコツ
日常生活の中で、サーカディアンリズムと体内時計の違いを意識すると眠りの質を高めやすくなります。朝日を浴びる時間を意識することは、体内時計を正しくリセットする最も手軽な方法です。夜に強い光を浴びると時計が遅れてしまい、朝の目覚めがつらくなることがあります。したがって、朝起きたらすぐに窓を開けたり外を歩いたりして、自然光の力を取り入れましょう。就寝前にはスマホやテレビの画面を避け、就寝前の30〜60分を静かな時間にすると眠りに入りやすくなります。さらに、毎日同じ時間に眠る習慣をつくると、体内時計が安定して日中の集中力や元気さが高まります。週末に大きく生活リズムを崩さないこともポイントです。以下のリストは、実生活で使えるコツの一例です。
- 朝起きたらできるだけ早く外に出て日光を浴びる
- 就寝前は強い光を避け、静かな時間を作る
- 毎日できるだけ同じ時間に就寝・起床を心がける
- 規則的な食事時間を保つ
- 睡眠を妨げるカフェインの摂取を午後以降控える
koneta: サーカディアンリズムという言葉を初めて聞いたとき、私は『体の24時間時計のリズム』と『その時計を動かす中の仕組み』の違いを一緒に考える機会だと思いました。友だちと話していると、夜更かしが翌日の眠気や集中力に直結する話題が出ます。そこで私は、光が時計をリセットする力を持つこと、朝日を浴びると脳の司令塔が正しく働くことを強調したいと感じました。スマホのブルーライトや夜のテレビは時計を狂わせがちですが、優しく時計を整える習慣を身につければ、日々の眠気や体温の変動が自然と整います。これが日常生活の中でできる“小さな時計修正”のコツです。
次の記事: 正の強化と負の強化の違いを徹底理解!中学生にもわかる行動学の基本 »





















