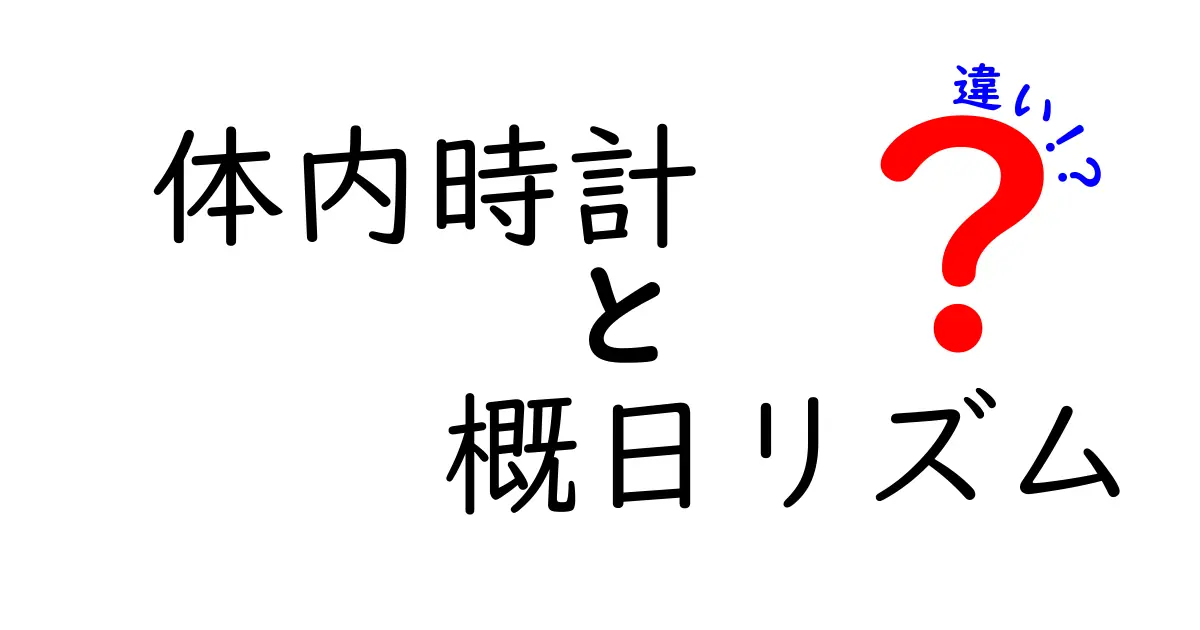

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
体内時計と概日リズムの基本と違い
体内時計とは何かを理解することから始めましょう。体内時計は私たちの体の中にある約24時間のリズムを生み出す機械のようなものです。この機械は脳の視床下部にあるSCNと呼ばれる部位を中心に働き、眠りと覚醒、体温、ホルモンの分泌といった生理的な流れを日々指示します。一方、概日リズムはこの内部の機械が作り出す日々のリズムそのもの、つまり睡眠のタイミングや食事のリズム、覚醒のパターンといった生活の表れです。言い換えれば、体内時計は内部の仕組み、概日リズムはその仕組みが外に表れる姿だと理解すると分かりやすくなります。
私たちは朝日を浴びると体内時計をリセットし、眠気を誘うホルモンであるメラトニンの分泌を抑え、体温を上げて日中の活動を活発にします。夜になるとこのリセットが逆方向に働き、眠気を作る物質が優位になります。このリセット機能が乱れると睡眠不足や日中の集中力低下が起きやすくなります。生活リズムが不規則だと、体内時計と概日リズムのズレが生じ、朝の起床が難しくなったり夜の眠りが浅くなることがあります。
以下の表は二つの概念の違いを整理するのに役立ちます。さらに、後のセクションでは生活に取り入れる工夫を詳しく紹介します。
なぜ違いが生まれるのか
体内時計は基本的に遺伝的に設定された約24時間のリズムを持っていますが、環境要因がこのリズムを微調整します。日照や食事、運動、生活習慣などの信号が体内時計をリセットする力を持っています。特に光の強さとタイミングが重要で、朝の光は眠気を抑え日中の活動を促進します。一方で夜の強い光は睡眠の質を低下させる原因になります。これらの信号が乱れると、体内時計は徐々にズレ、日中の眠気や夜の睡眠の質の低下に直結します。
さらに概日リズムは体内時計だけでなく、肝臓・腸・心臓など全身の臓器と連携しています。食事の時間や内容、運動の種類もリズムに影響します。規則正しい生活は脳と身体の“協奏曲”を作る鍵です。
生活へ応用と日常の工夫
日常で体内時計と概日リズムを整えるには、まず毎日同じ時間に起きることが基本です。週末も遅く起きすぎないよう心がけ、朝は外の光を取り入れましょう。食事は眠る2~3時間前には控えめにし、夜遅い時間のカフェイン飲料はできるだけ避けます。規則正しい睡眠時間と朝の光が体内時計のリセットに最も効果的です。
学習やスポーツのパフォーマンスを高めたい人には、起床後すぐの軽い運動や朝食のタイミングを整えると良い効果が出ます。夜遅くまでスマホを使うと睡眠の質が落ち、翌日の集中力が低下します。スマホの画面の光を夜は控えることも大切な習慣です。
ねえ、体内時計ってただ眠くなる時間を決めているだけじゃないんだよ。実は胃腸の動き、ホルモンの分泌、体温の変化まで仲良くリズムを組んで動かしているんだ。僕たちが朝起きて顔を洗うとき、朝日を浴びることが体内時計をリセットする信号になって、日中にはエネルギーが湧く。夜は光を控えめにすることで睡眠の準備がきちんと進む。友だちが夜更かしして翌日眠気に苦しむのを見ると、体内時計のズレがこんなにも日常生活に影響するんだと実感する。だからこそ、朝の光を取り入れ、夜は暗めの環境で過ごす、そんな小さな習慣が体のリズムを守る鍵になるんだ。





















