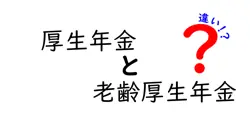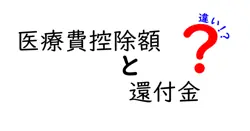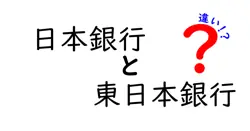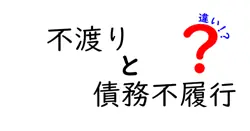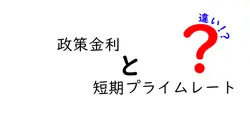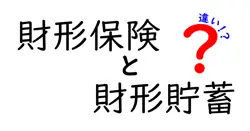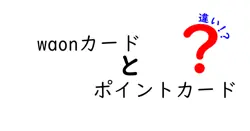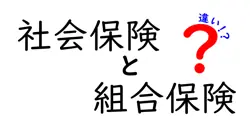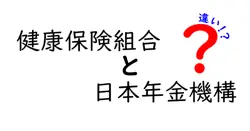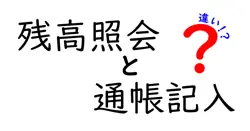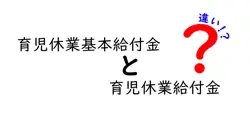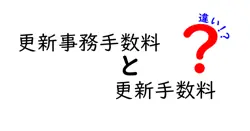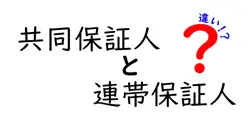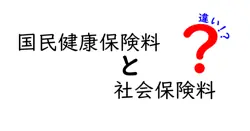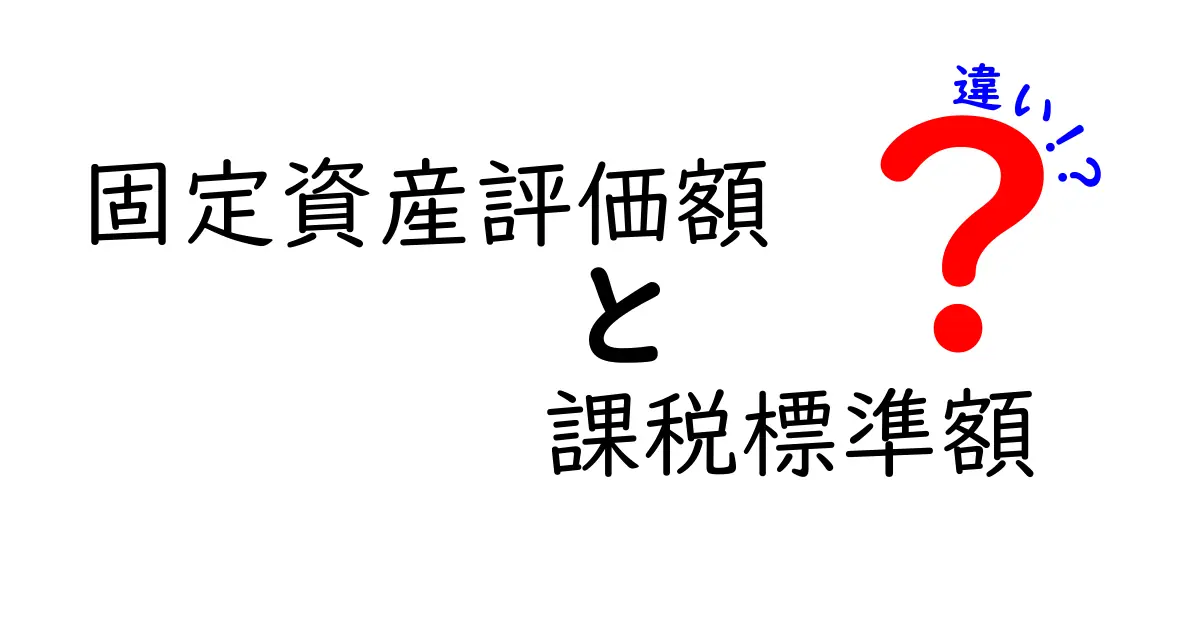
固定資産評価額と課税標準額の違いとは?
固定資産評価額と課税標準額は、税金に関わる重要な言葉ですが、似ているようで違います。
まず、固定資産評価額とは、土地や建物などの固定資産がどれくらいの価値があるかを専門の機関が評価した金額です。これは、基本的に資産の価値そのものを示しています。
一方、課税標準額は、その固定資産評価額から一定の控除を差し引いたあとに、税金をかけるもとになる金額です。つまり、実際に税金の計算に使われるのが課税標準額です。
この2つは、評価額と税額計算のための基準額として使われ、それぞれ異なる役割を持っています。
わかりやすく言うと、固定資産評価額は商品の値札、課税標準額は値札から割引をして実際に払う値段の基準というイメージです。
この違いを理解すると、固定資産税の仕組みがよく見えてきます。
固定資産評価額の決まり方と特徴
固定資産評価額は、各市区町村が3年に一度固定資産の評価替えを行います。
国の定めた固定資産評価基準に従って、土地なら地価、公示価格などを参考に評価され、建物なら建築費用などから評価額が決まります。
専門の評価員が現地調査をしたり、地域の市場価格を参考に算定したりします。
重要なのは、固定資産評価額は市場価格よりも低めに設定されることが多いこと。これは税負担を考慮した配慮のためです。
評価額が変わると、毎年の固定資産税にも影響するため、評価替えの年は特に注目されます。
固定資産税を理解する上で、この評価額は基礎となる数字なので覚えておきましょう。
課税標準額の計算方法と特徴
課税標準額は、固定資産評価額から各種控除や減免を差し引いて計算されます。
たとえば、住宅用地の特例によって一定の減額措置が適用される土地は、税負担を軽くするために課税標準額が大幅に減らされます。
また、新築住宅には建物の評価額の一部を減額する場合もあります。
このような控除や特例は、地域や対象物件によって違います。
つまり、課税標準額は実際に税金を計算するときの基準額で、固定資産評価額よりも低くなることが多いのです。
税率をかける元の額であるため、この金額が大きければ税金が高くなり、小さければ税金は安くなります。
ここで重要なのは、課税標準額が固定資産評価額と異なっている理由は、税負担を公平かつ適正にするための措置だということです。
固定資産評価額と課税標準額の違いを表で比較
| 項目 | 固定資産評価額 | 課税標準額 |
|---|---|---|
| 意味 | 資産の価値を評価した金額 | 税金計算の基準となる金額 |
| 決定方法 | 自治体が評価基準に基づき評価 | 評価額から控除・減免を適用後の額 |
| 金額の傾向 | 市場価格よりやや低め | 固定資産評価額より低くなることが多い |
| 役割 | 評価の基準 | 税額計算の基準 |
まとめ:違いを知って固定資産税を正しく理解しよう
このように、固定資産評価額と課税標準額は似た言葉ですが、役割や計算方法、数字の意味が違います。
固定資産評価額は資産自体の価値の目安で、課税標準額はその評価額から控除などを引いた、実際の税金計算に使う金額です。
固定資産税の通知書などを見るときも、この違いを知っていると混乱しにくくなります。
税が高すぎると思ったら、この課税標準額に対しての控除や特例の内容を調べてみるといいでしょう。
今後、税金や不動産に関わる際の参考になれば幸いです。
固定資産評価額は、不動産の価値を示す大切な数字ですが、この評価は実は市場価格とは少し違います。なぜなら税金の計算に使うため、国が定めたルールに従ってやや低めに評価されるからです。つまり、家の『本当の売値』よりも優しく見積もった値札みたいなもの。これは税負担を少し軽くして市民の生活を守る工夫なんですね。なので『評価額=売値』とは思わないことがポイントですよ!
次の記事: 公示価格と取引価格の違いとは?初心者にもわかりやすく解説! »